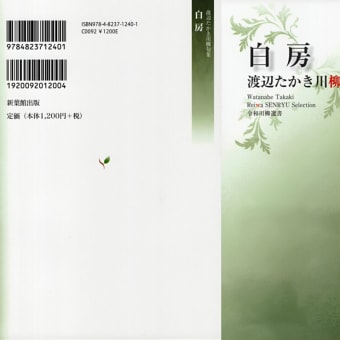□本日落語二席。
◆入船亭扇遊「明烏」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和3(2021)年5月28日(第635回「TBS落語研究会」)。
◆柳家金語楼「子供の酔つぱらひ」(日本文化チャンネル桜『落語動画』)。
※SPレコード(テイチクレコード)。
母親が買物に行くので、子どもの金坊に留守番をしろと言う。金坊がついていきたがるので、母親は隣のみっちゃんを呼ぶから、二人でままごとをしていろと言ってなだめる。
そして、ままごとは夫婦の体で、金坊はみっちゃんに一本つけろと言って徳利を出させたところ、本当に酒が入っていて金坊が酔っぱらうという噺。
最後は、父親が帰ってきて、父親が金坊に寝てしまえと言う。ちゃんと寝たら、明日キャラメルを買ってやるからと父親が言うと、金坊は、キャラメルなんかいらねえから「朝の膳に一合願いてえ」と言って落げである。
いったいこの金坊は何歳という設定なのか、落語のなかでは語られない。こんな落語(漫才でも)は、さて現代だったらできるのか否か。興味深いところである。
さて、隣からみっちゃんを呼んできたときも、母親は金坊の相手をしてくれたら、キャラメルを買ってあげるからと母親は言った。ここでもキャラメルだ。このころは、キャラメルが、よほど子どもの気をひく菓子だったのか。
また、みっちゃんは、キャラメルをもらえると聞いたとき、「5銭のですか?10銭のですか?」と尋ねた。母親が「10銭のを買ってあげますよ」と言うと、みっちゃんは「まあ、とんだご散財」と。
5銭のと10銭のというのは量の違いか質の違いか。ちなみに、森永のHPにはミルクキャラメルの歴史年表がある。これで見ると、明治30(1897)年からキャラメルの歴史がスタートしているが、このときは一粒0.7銭とある。バラ売りも量り売りもあった由。
そして、ずっと時代が下って、大正3(1914)年だと、二十粒入りが10銭とある。母親とみっちゃんがやりとりしていたのは、ここらあたりの時代だったろうか。値段が量のことだとすると、5銭は十粒か。
◆入船亭扇遊「明烏」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和3(2021)年5月28日(第635回「TBS落語研究会」)。
◆柳家金語楼「子供の酔つぱらひ」(日本文化チャンネル桜『落語動画』)。
※SPレコード(テイチクレコード)。
母親が買物に行くので、子どもの金坊に留守番をしろと言う。金坊がついていきたがるので、母親は隣のみっちゃんを呼ぶから、二人でままごとをしていろと言ってなだめる。
そして、ままごとは夫婦の体で、金坊はみっちゃんに一本つけろと言って徳利を出させたところ、本当に酒が入っていて金坊が酔っぱらうという噺。
最後は、父親が帰ってきて、父親が金坊に寝てしまえと言う。ちゃんと寝たら、明日キャラメルを買ってやるからと父親が言うと、金坊は、キャラメルなんかいらねえから「朝の膳に一合願いてえ」と言って落げである。
いったいこの金坊は何歳という設定なのか、落語のなかでは語られない。こんな落語(漫才でも)は、さて現代だったらできるのか否か。興味深いところである。
さて、隣からみっちゃんを呼んできたときも、母親は金坊の相手をしてくれたら、キャラメルを買ってあげるからと母親は言った。ここでもキャラメルだ。このころは、キャラメルが、よほど子どもの気をひく菓子だったのか。
また、みっちゃんは、キャラメルをもらえると聞いたとき、「5銭のですか?10銭のですか?」と尋ねた。母親が「10銭のを買ってあげますよ」と言うと、みっちゃんは「まあ、とんだご散財」と。
5銭のと10銭のというのは量の違いか質の違いか。ちなみに、森永のHPにはミルクキャラメルの歴史年表がある。これで見ると、明治30(1897)年からキャラメルの歴史がスタートしているが、このときは一粒0.7銭とある。バラ売りも量り売りもあった由。
そして、ずっと時代が下って、大正3(1914)年だと、二十粒入りが10銭とある。母親とみっちゃんがやりとりしていたのは、ここらあたりの時代だったろうか。値段が量のことだとすると、5銭は十粒か。