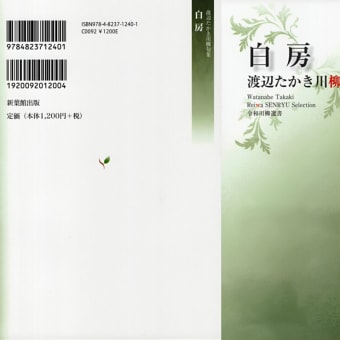□本日落語一席。
◆立川談志「堪忍袋」(CD『家元の軌跡 談志続30歳』DISC-2)。
紀伊國屋ホール、昭和41(1966)年5月25日収録(第6回「談志ひとり会」)。
東宝名人会の音源を集めたこのCDのなかにあって、唯一「談志ひとり会」の高座が入っている。解説によれば未発表音源とのこと。あらためて立川談志「ひとり会」の落語全集を確認してみると、確かにネタとして「堪忍袋」自体の収録もない。存命中の談志家元には、「堪忍袋」の音を残すことを良しとしていなかったのだろうか。
昭和からの落語マニアでない自分にとって、「堪忍袋」というと、どうも上方落語ではないかと思えていた時期もあった。それだけ上方の落語家に多く演じられる機会にふれて、東京の落語家が「堪忍袋」を演るのを聴く機会が少なかったという経験からくる感覚である。
しかし、この落語は益田太郎冠者という東京の劇作家(または実業家または貴族院議員)による東京由来の新作落語である。
だから、昭和では何人かこの落語が東京の落語家によって演じられている(三代目三遊亭金馬・八代目春風亭柳枝など)。これを上方に移したのが誰かはわからないけれど、上方では独自に「堪忍袋」が改変されていったようだ。
昨今は、東西交流がさかんになってきているなかで、東京の落語家が演る「堪忍袋」も、上方の型で演ったものを聴いたことがある。
今回、家元の「堪忍袋」を聴いて、あらためて「堪忍袋」の原型を聴いた気分でもある。東西どちらが良いと言うこともできないけれど。
◆立川談志「堪忍袋」(CD『家元の軌跡 談志続30歳』DISC-2)。
紀伊國屋ホール、昭和41(1966)年5月25日収録(第6回「談志ひとり会」)。
東宝名人会の音源を集めたこのCDのなかにあって、唯一「談志ひとり会」の高座が入っている。解説によれば未発表音源とのこと。あらためて立川談志「ひとり会」の落語全集を確認してみると、確かにネタとして「堪忍袋」自体の収録もない。存命中の談志家元には、「堪忍袋」の音を残すことを良しとしていなかったのだろうか。
昭和からの落語マニアでない自分にとって、「堪忍袋」というと、どうも上方落語ではないかと思えていた時期もあった。それだけ上方の落語家に多く演じられる機会にふれて、東京の落語家が「堪忍袋」を演るのを聴く機会が少なかったという経験からくる感覚である。
しかし、この落語は益田太郎冠者という東京の劇作家(または実業家または貴族院議員)による東京由来の新作落語である。
だから、昭和では何人かこの落語が東京の落語家によって演じられている(三代目三遊亭金馬・八代目春風亭柳枝など)。これを上方に移したのが誰かはわからないけれど、上方では独自に「堪忍袋」が改変されていったようだ。
昨今は、東西交流がさかんになってきているなかで、東京の落語家が演る「堪忍袋」も、上方の型で演ったものを聴いたことがある。
今回、家元の「堪忍袋」を聴いて、あらためて「堪忍袋」の原型を聴いた気分でもある。東西どちらが良いと言うこともできないけれど。