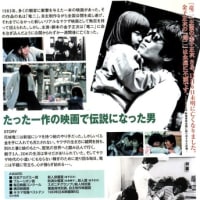古き良き日本に戻れ でしょうか!
+++
水と緑の地球環境:環境教育の国際ラベル「エコスクール」、日本上陸
◇「グリーンフラッグ」に挑戦
環境教育の国際ラベル「エコスクール」の認定を受ける取り組みが、熊本県や首都圏の一部の学校で始まった。国際NGO「環境教育基金」(FEE、本部・デンマーク)が実施する事業で、子どもたちのエコ活動を通した持続可能な社会へのアプローチだ。認定校には「グリーンフラッグ」が授与され、この活動への参加で海外の「エコスクール」のネットワークの仲間入りができる。【明珍美紀】
◇学習プログラム「七つのステップ」 生徒主体、目標も自由に設定
◇レジ袋削減で効果「見える化」--熊本県立水俣工業高校
FEEが定める環境学習プログラムには、(1)エコスクール委員会をつくる(2)環境についての調査をして目標を決める(3)行動計画を立てる--など「七つのステップ」があり、それに基づき、子どもたちが環境のために何ができるかを考え、行動していくのが主な目的だ。
日本では「エコスクール」への登録が昨年から始まり、熊本県立水俣工業高校や神奈川県の私立湘南学園小学校、東京都江戸川区立東葛西小学校など計6校が「グリーンフラッグ」の取得を目指している。
水俣工業高では昨年6月、各学級の美化委員らによる約20人のエコスクール委員会を設けた。メンバーで話し合った結果、「レジ袋の削減」「紙パックのリサイクル」「ものづくりによる環境教育」の三つを目標に据えた。
全校生徒(約250人)と教職員に「マイバッグ」の使用を呼びかけ、レジ袋の削減調査に乗り出した。生徒たちは毎週末、スーパーやコンビニエンスストアなどでレジ袋をもらわなかった枚数を自己チェックシートに記入する。委員会のメンバーが集計したデータをパソコンに入力してCO2(二酸化炭素)の削減量などを算出し、効果の「見える化」を図った。同校オリジナルの「マイバッグ」もつくって昨秋、生徒全員に配った。
「生徒に啓発され、教職員のマイバッグ持参率も高まった」と同校環境教育係の本山和広教諭(31)は言う。
紙パックのリサイクルは、売店の横に生徒が考案した紙パックの乾燥棚を設置。乾いたパックは掃除当番が開いてリサイクルに回す。ものづくりの活動は、電化製品の修理や廃材を利用した家具の製作などを地域で行う技術ボランティアだ。
「ここは水俣病という公害問題が発生した場所で、僕も患者の語り部の方から話を聞いたことがある。みんなで住みよい街にしていきたい」と委員長の富永武志さん(17)=電気科3年=は意欲的だ。
◇地域の人々もサポート
◇屋上にビオトープ、腐葉土作り--神奈川・湘南学園小
湘南学園小(生徒数617人)では昨年末、5、6年生を中心にエコスクール委員会が発足。「エネルギー、水、紙を大切にしよう」と「植物や生きものを増やそう」の二つを目標に掲げた。
ごみの分別や省エネなどのエコ活動を呼びかけるポスターを描き、委員会のメンバーが手分けし校内に掲示。屋上にビオトープ(動植物の生息空間)を置き、ミミズや微生物を増やすために落ち葉を集めて腐葉土をつくる活動も始めた。海に近いので海岸での清掃活動にも取り組んでいる。
この春には、地元で環境活動に携わるサーファーや音楽家らによる「エコスクールサポート委員会」も結成。始動のキックオフイベントとして先月、視察で来日したスウェーデンの自然学校の教師らを招いたワークショップを開催した。
スウェーデンでは、「自然も子どもたちの学びの場」との考えから、NGO「自然学校協会」が自治体と協力して野外教育を推進。レクリエーションやフィールドワークだけではなく、理科や英語など学科の授業も外で行うことがあるという。
ワークショップには、民間団体「持続可能なスウェーデン協会」教育プロジェクトコーディネーターのバルブロ・カッラさんや、スウェーデン・ファールン市の自然学校の教師で、「エコスクール」プログラムの普及に努めるミア・ブッシュトさんら5人が参加。実際に落ち葉や枝など自然の素材を用いて、同小の子どもたちに算数などの授業を行った。
「スウェーデンでは70年代のオイルショックや原発問題などで市民の環境意識が高まった。学校教育にも『持続可能な発展』の視点を入れている」とブッシュトさんは説明。「日常のなかでの環境教育が大切。子どもたちが自然とかかわるようになれば、生き物を大切にしたくなる」
同小の冨田靖子教諭(44)は「エコスクールへの参加をきっかけに、世界の子どもたちがどんなことを学んでいるかを知ることができ、視野が広がります」。
NPO法人「環境ネットワークくまもと」(熊本市)の代表理事で、熊本学園大の宮北隆志教授(57)=生活環境学=は「エコスクールのプログラムは、子どもたちが主体的に環境問題にかかわることを後押しする仕組み。学校を通して持続可能な暮らしに対する意識が地域に広がり、海外の学校とも情報交換ができる」と話していた。
◇キッズファームで給食に新鮮食材--熊本・山東保育園
「旬産旬消」などを提唱し、独自の食育活動で知られる熊本市の山東保育園でもエコスクールへの登録を準備中だ。
保育園の周辺の畑を借り受けた「キッズファーム」で無農薬の大豆や小麦、野菜などを栽培。農作業は地元の農家に依頼し、種まきや収穫のときは、園児や家族も手伝っている。
ファームで収穫された新鮮な野菜がその日の給食の食材となり、調理クズは畑の堆肥(たいひ)に活用。3分づきの玄米をかまどで炊き、みそや梅干しも自家製だ。「地産地消から一歩進んだ旬産旬消を目指している」と村上千幸園長(55)は強調する。
省エネの面では、夏は日よけや遮光ネットを張りめぐらすなど工夫し、暑い日は園児を室内プールで遊ばせる。昨夏は冷房を使わずに済み、「CO2の削減に役立った」という。先月には「地域共同発電所」として、保育園の屋根にソーラーパネルを取り付けた。売電して得た利益は、「環境ネットワークくまもと」や地元の環境活動に充てる予定だ。
+++
水と緑の地球環境:環境教育の国際ラベル「エコスクール」、日本上陸
◇「グリーンフラッグ」に挑戦
環境教育の国際ラベル「エコスクール」の認定を受ける取り組みが、熊本県や首都圏の一部の学校で始まった。国際NGO「環境教育基金」(FEE、本部・デンマーク)が実施する事業で、子どもたちのエコ活動を通した持続可能な社会へのアプローチだ。認定校には「グリーンフラッグ」が授与され、この活動への参加で海外の「エコスクール」のネットワークの仲間入りができる。【明珍美紀】
◇学習プログラム「七つのステップ」 生徒主体、目標も自由に設定
◇レジ袋削減で効果「見える化」--熊本県立水俣工業高校
FEEが定める環境学習プログラムには、(1)エコスクール委員会をつくる(2)環境についての調査をして目標を決める(3)行動計画を立てる--など「七つのステップ」があり、それに基づき、子どもたちが環境のために何ができるかを考え、行動していくのが主な目的だ。
日本では「エコスクール」への登録が昨年から始まり、熊本県立水俣工業高校や神奈川県の私立湘南学園小学校、東京都江戸川区立東葛西小学校など計6校が「グリーンフラッグ」の取得を目指している。
水俣工業高では昨年6月、各学級の美化委員らによる約20人のエコスクール委員会を設けた。メンバーで話し合った結果、「レジ袋の削減」「紙パックのリサイクル」「ものづくりによる環境教育」の三つを目標に据えた。
全校生徒(約250人)と教職員に「マイバッグ」の使用を呼びかけ、レジ袋の削減調査に乗り出した。生徒たちは毎週末、スーパーやコンビニエンスストアなどでレジ袋をもらわなかった枚数を自己チェックシートに記入する。委員会のメンバーが集計したデータをパソコンに入力してCO2(二酸化炭素)の削減量などを算出し、効果の「見える化」を図った。同校オリジナルの「マイバッグ」もつくって昨秋、生徒全員に配った。
「生徒に啓発され、教職員のマイバッグ持参率も高まった」と同校環境教育係の本山和広教諭(31)は言う。
紙パックのリサイクルは、売店の横に生徒が考案した紙パックの乾燥棚を設置。乾いたパックは掃除当番が開いてリサイクルに回す。ものづくりの活動は、電化製品の修理や廃材を利用した家具の製作などを地域で行う技術ボランティアだ。
「ここは水俣病という公害問題が発生した場所で、僕も患者の語り部の方から話を聞いたことがある。みんなで住みよい街にしていきたい」と委員長の富永武志さん(17)=電気科3年=は意欲的だ。
◇地域の人々もサポート
◇屋上にビオトープ、腐葉土作り--神奈川・湘南学園小
湘南学園小(生徒数617人)では昨年末、5、6年生を中心にエコスクール委員会が発足。「エネルギー、水、紙を大切にしよう」と「植物や生きものを増やそう」の二つを目標に掲げた。
ごみの分別や省エネなどのエコ活動を呼びかけるポスターを描き、委員会のメンバーが手分けし校内に掲示。屋上にビオトープ(動植物の生息空間)を置き、ミミズや微生物を増やすために落ち葉を集めて腐葉土をつくる活動も始めた。海に近いので海岸での清掃活動にも取り組んでいる。
この春には、地元で環境活動に携わるサーファーや音楽家らによる「エコスクールサポート委員会」も結成。始動のキックオフイベントとして先月、視察で来日したスウェーデンの自然学校の教師らを招いたワークショップを開催した。
スウェーデンでは、「自然も子どもたちの学びの場」との考えから、NGO「自然学校協会」が自治体と協力して野外教育を推進。レクリエーションやフィールドワークだけではなく、理科や英語など学科の授業も外で行うことがあるという。
ワークショップには、民間団体「持続可能なスウェーデン協会」教育プロジェクトコーディネーターのバルブロ・カッラさんや、スウェーデン・ファールン市の自然学校の教師で、「エコスクール」プログラムの普及に努めるミア・ブッシュトさんら5人が参加。実際に落ち葉や枝など自然の素材を用いて、同小の子どもたちに算数などの授業を行った。
「スウェーデンでは70年代のオイルショックや原発問題などで市民の環境意識が高まった。学校教育にも『持続可能な発展』の視点を入れている」とブッシュトさんは説明。「日常のなかでの環境教育が大切。子どもたちが自然とかかわるようになれば、生き物を大切にしたくなる」
同小の冨田靖子教諭(44)は「エコスクールへの参加をきっかけに、世界の子どもたちがどんなことを学んでいるかを知ることができ、視野が広がります」。
NPO法人「環境ネットワークくまもと」(熊本市)の代表理事で、熊本学園大の宮北隆志教授(57)=生活環境学=は「エコスクールのプログラムは、子どもたちが主体的に環境問題にかかわることを後押しする仕組み。学校を通して持続可能な暮らしに対する意識が地域に広がり、海外の学校とも情報交換ができる」と話していた。
◇キッズファームで給食に新鮮食材--熊本・山東保育園
「旬産旬消」などを提唱し、独自の食育活動で知られる熊本市の山東保育園でもエコスクールへの登録を準備中だ。
保育園の周辺の畑を借り受けた「キッズファーム」で無農薬の大豆や小麦、野菜などを栽培。農作業は地元の農家に依頼し、種まきや収穫のときは、園児や家族も手伝っている。
ファームで収穫された新鮮な野菜がその日の給食の食材となり、調理クズは畑の堆肥(たいひ)に活用。3分づきの玄米をかまどで炊き、みそや梅干しも自家製だ。「地産地消から一歩進んだ旬産旬消を目指している」と村上千幸園長(55)は強調する。
省エネの面では、夏は日よけや遮光ネットを張りめぐらすなど工夫し、暑い日は園児を室内プールで遊ばせる。昨夏は冷房を使わずに済み、「CO2の削減に役立った」という。先月には「地域共同発電所」として、保育園の屋根にソーラーパネルを取り付けた。売電して得た利益は、「環境ネットワークくまもと」や地元の環境活動に充てる予定だ。