
演奏:アンネ=ゾフィー・ムター、トロンヘイム・ソロイスツ
とあるコラムに、ムターのこの四季は好き嫌いが別れるだろうと書かれてあったが、初めて聴いたときにはなるほどと納得した。
「四季」はイ・ムジチ合奏団の模範的演奏をリファレンスとして、もっぱら他の演奏を聴いているが、その観点からのムター盤は、強烈なパンチと癖の強さにまず驚かされた。これは最初の印象として決して心地よいものではなかった。しかし人の驚くべき順応性はどのような場合にも働くようで、苦手なものもやがて好物に変わっていくのは不思議としか言い様がない。もう二度と口にしたくないと思ったミョウガが、今では冷奴には欠かせないと思ったり。
ともかく、多少の我慢をこらえて何回か聴いているうちに、うまうまとムターの思うつぼにハマった。これが世に言うところのムター節なのであろう。こうなってしまうと、イ・ムジチの模範演奏ではまったくもって、もの足りない。
ムターの四季は非常に人間臭い、つまり音楽の中にムターの主張がふんだんに投入されているのだ。これはおのずと、共感する人と拒絶する人に別れるだろう。これはソロ部において最も顕著であるから、春の二楽章、夏の二楽章、冬の二楽章は、現時点ではムター以外のものは聴きたいとは思わない。玄人好みの「秋」。イ・ムジチの演奏ではつまらないので、よく「秋」だけを飛ばして聴いていたが、ムターなら聴ける。そして、実は「秋」がソリストが最も頑張る曲であったことに初めて気づいた。「秋」は、これくらいのインパクトが必要なのだ。(余談だがカルミニョーラの秋もいい)
「冬」の一楽章では、ムターは思い切った試みをしている。これにはまいった。あんた、いくらなんでもこれはないでしょと最も違和感が強かったが、それも今では、これもあり得るなと思うようになった。むしろ一般的な演奏と同様に心地よい。その他、ムターのすべての演奏について言えることだが、演奏に込められた生々しく強い主張、つまりムター節、これにハマるかどうかということだろう。
(関係ないが、一度ムターに指揮棒を持たせてブラームスなどをやらせてみたい気がする。すごいことになるのではないだろうか。)
とあるコラムに、ムターのこの四季は好き嫌いが別れるだろうと書かれてあったが、初めて聴いたときにはなるほどと納得した。
「四季」はイ・ムジチ合奏団の模範的演奏をリファレンスとして、もっぱら他の演奏を聴いているが、その観点からのムター盤は、強烈なパンチと癖の強さにまず驚かされた。これは最初の印象として決して心地よいものではなかった。しかし人の驚くべき順応性はどのような場合にも働くようで、苦手なものもやがて好物に変わっていくのは不思議としか言い様がない。もう二度と口にしたくないと思ったミョウガが、今では冷奴には欠かせないと思ったり。
ともかく、多少の我慢をこらえて何回か聴いているうちに、うまうまとムターの思うつぼにハマった。これが世に言うところのムター節なのであろう。こうなってしまうと、イ・ムジチの模範演奏ではまったくもって、もの足りない。
ムターの四季は非常に人間臭い、つまり音楽の中にムターの主張がふんだんに投入されているのだ。これはおのずと、共感する人と拒絶する人に別れるだろう。これはソロ部において最も顕著であるから、春の二楽章、夏の二楽章、冬の二楽章は、現時点ではムター以外のものは聴きたいとは思わない。玄人好みの「秋」。イ・ムジチの演奏ではつまらないので、よく「秋」だけを飛ばして聴いていたが、ムターなら聴ける。そして、実は「秋」がソリストが最も頑張る曲であったことに初めて気づいた。「秋」は、これくらいのインパクトが必要なのだ。(余談だがカルミニョーラの秋もいい)
「冬」の一楽章では、ムターは思い切った試みをしている。これにはまいった。あんた、いくらなんでもこれはないでしょと最も違和感が強かったが、それも今では、これもあり得るなと思うようになった。むしろ一般的な演奏と同様に心地よい。その他、ムターのすべての演奏について言えることだが、演奏に込められた生々しく強い主張、つまりムター節、これにハマるかどうかということだろう。
(関係ないが、一度ムターに指揮棒を持たせてブラームスなどをやらせてみたい気がする。すごいことになるのではないだろうか。)
















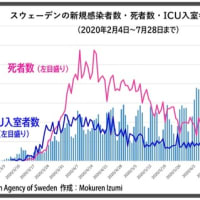









私のは「ギター」によるもので、ソプラノ・テナー・アルトと混在した「アンサンブル」ものです。
クラッシックギターはもちろんアコースティックなわけですが、アンサンブルともなるとかなりの音量となります。
でもやっぱり「キンキン」した印象は否めないかなぁ~?と思います。
こういうのはやっぱり「弦楽四重奏」くらいないと貫禄つかないかなぁ~?
まぁ、もともと「弦楽四重奏」の構成が好きなんですけどね・・・。落ち着く音色なんですよ・・・。
それはお買い得のような。
「四季」は室内楽の名曲ですね。時代は違いますがモーツアルトの「アイネクライネ」くらいに広く親しまれている曲です。
私も大好きで、演奏家違いでCDは10枚ほどありますよ。
それも名曲ですねぇ~、たしか持っていたかな?どこやったろ?
たしかに天才モーツァルト、名曲がたくさんありますね!
モーツアルトはほんとに名曲のてんこ盛りですね。どの曲の楽想も天才的です。
本日、ハードオフからレコード盤を仕入れて(?)きました。
「新世界より」と「田園」です。あわせて210円、安すぎる!
ダイナミックレンジが低かろうとスクラッチノイズがあろうとプレーヤが貧相であろうとも、私にとってのその価値感には変わりがないので問題なし!
どちらもフル収録!こういうことができる機会はそうはないと思うので・・・。
CDが登場する直前。オーディオが一番楽しかった時代ですね。音質を左右する多くのファクタがありました。カートリッジ、トーンアーム、ターンテーブル、どれにも音のノウハウがあるんですよね。
そのあたりがごっそりCDに置き換わってしまったので、オーディオの楽しさが激減してしまいました。
私は正直、現時点ではよく分からないのですが、kaoaruさんはやはり、ディジタルの音はあまり良くないと思われますか?
しかし、音の良し悪し以前に「音楽の価値観」が優先されるべきでしょうね!19、20才の若造でないならば。
若い人は今のメディアで存分にひたればいいわけですし、みんながそうですから、人に変な目で見られるのもイヤでしょうし、最先端にいたいと思うのは今の人である証拠!
しかし、私には過去の経験があるので、別に最先端である必要もなく、テープヒスが気になるわけでもないしスクラッチ音もあって当然。
音がいいとか思う以前に、その当時のニオイというかそういうものを感じるのがいいのかな?
それに、よく耳にする「当時のテープをPCに取り込む」とか「手持ちのレコードを取り込む」とか一生懸命やっているのを見かけると「何やっててんだろうね?」って思ってしまいます。
音質とか気にするんならCDじゃないとダメなんだけどね!
テープのダイナミックレンジって裸特性なんかノーマルテープで50dBとれればいいほうです。
レコードにしても、よほどの高級システムじゃないとダイナミックレンジはかせげません。
それを廉価版プレーヤとADコンバータにUSB接続するようなオモチャで一生懸命やる姿は滑稽に思えます。
わざわざPCに取り込まなくてもいいんじゃないの?っていうのが私の考え方です。
ただ、ディジタル化するメリットというものは否定しません。
なぜなら、オーディオ処理をPCでできるからです。
「オーディオの楽しさ」というのは昔も今も変わっていないと思います。
人間が変わってしまった・・・そういうことなんだろうと思います。
それは、あなたがオーディオアンプを作ろうと目論んでいるとします。それはとても楽しいことですよね?
その発想は、かつて私が高校生時代にさんざんやっていたことです。
だから、人間自体が変わらないのであれば、昔も今も変わらないんですよ!
楽しめるモノで楽しめばいい、ただそれだけのことですよ!
もし、そうでなければ、あなたがアンプを自作すること自体を私が否定していると思いますが、そういうモノではないのですよ・・・フフフ・・・。
ダイソーで105円で売っていた「俗に言うパンツのゴムひも」をなんとかカットアンドトライでいいところをさぐって対処したのが今の状態です。
一応、簡易型のストロボ板を自作してチェックできるようにしてあります。
音質的にはものすごく不満です。過去にイロイロやってきてますからそれは重々承知の上!
でもねぇ~、とりあえず当時の雰囲気だけは再現できているからいいかなぁ~?ってね!
まぁ、そんなところです。
ハードオフにいくとまだまだ使えそうないいプレーヤがゴロゴロしているので、そのうちなんとかするかもしれませんが・・・。
かつて一部のオーディオマニアを揶揄して言われたものですが、「100万円も機材に金をかけてレコードは2,3枚しかもってないんだ」と。見方によればこれはホントに馬鹿げていますが、私はこれはこれで、この価値観もありだと思います。
一方、これは私も高校生くらいだったと思いますが、安物のラジカセでフルトベングラーのブラームスやベートーヴェンを聴いて、震えるほど感動したことがあります。つまり音楽を聴いて楽しむことに「音の良し悪し」はあまり関係ないともいえますね。たぶんこのあたりがkaoaruさんの言われる「音楽の価値観が優先されるべき」という話に近いのではないでしょうか。
こう考えると、音楽とオーディオは明確に切り分けることができますね。そして今の私のマイブームはオーディオということなのでしょう。
ベルトドライブのターンテーブルをパンツのゴムで回されましたか。(^^)
オーディオ的にはこのゴムにも拘りたいところですね。明確に音質に影響しますものね。
分解すると「テクニクス」の文字が出てきます。
ほんとに安物のフルオートプレーヤなんです。
モータのトルクがなさすぎで、これではワウの解消はムリな製品です。だからテクニクスブランドでは販売できなかった・・・と見ている私です。
まぁ、フルオートプレーヤにロクなものはありません。
過去にトリオのフルオートを使っていたことがありましたが、メカ音がターンテーブルを伝ってトーンアームにまで伝わり音となって出てしまう・・・そんなモノです。
安物のマニュアルでもSL-20のほうがはるかに良かった。イコライザは自分で用意すればナンボでも自由でしたし・・・。
イコライザだけはローノイズトランジスタのほうが楽でしたね!乾電池駆動してたんで電源ハムにも悩まされなかったし・・・電池代なんてそう大したものではありませんでしたし・・・。
まぁ、こだわればいくらでもこだわれる・・・それがゼイタクというモノなんじゃないでしょうか?