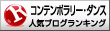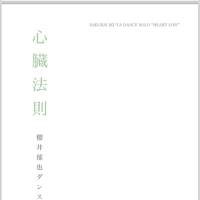どこへ、、、。
行くべき所へ、、、。
「もうすぐ誰もが通訳を必要とする。自分の言葉を理解するために。
「人は生まれてすぐに他者になる。
「私は、ノン、というために居る。
「私たちは互いが夢見る人だ。
いづれも、『さらば愛の言葉よ』という映画の台詞。ゴダールの映画のなかで、僕が好きになれた一本。勝手にしやがれ。パッション。ドイツ零年。そしてこれ。
空の雲の陰影、川の流れ、男と女の居場所、それらに言葉が重なってゆく。これは言葉についての映画。つまり関係についての、愛についての映画だ。
ウイルスによって切断の危機にあるものについてのさまざまを、この映画から感じてならない。おもえば映画とは切断されたものの再構築でもある。
結末から逆算したような映画が多くていやになるが、この映画には結末がない。あらゆる会話にも結末がない。
会話は会話を生みつづけ、イメージはイメージを生みつづける。
それが僕らのいまの日々にダブる。
僕らにとって、すべては始まりの連続なのだということを、この作品から確かめる。
これはダンス的な映画だと思う。冒頭5分そこそこで、そう感じる。
愛の問題と政治の問題、政治の問題と現在の問題が、混在する。
僕らの現在に関係している。
多くの映画が世界を解釈しようとするのに対して、この映画は解釈を捨てる。
これは、ひたすら世界を見て聴いている映画だと、僕は思う。
画面のどれもが、これみよがしでない。
すべては通過点、流れのなかにある。
そう感じ、そこに共感する。
ゴダールは、クリエイターではなく「引用者」であろうとする。
これが、すこぶる重要だと思う、連帯する。
世界を聴きたい、世界を見たい。
「おお言語よ」という台詞もあった。
心に焼き付く。
言葉について考える、ということは、革命者であろうとすることに近しいと僕は思う。
ふと思う。現代史は革命史なのかもしれない。
停滞や絶望もふくめて、どこかでなにかに抵抗するかぎり、革命は現在進行中なのではないか、、、。
そんな声が、画面から聴こえてくる。
ゴダールの映画の奥には、反抗がある。
尊敬する。
【追記】
トップダウンによる東京自粛に震えつつ、いくつもの映画やダンス映像を見まくり本を読みあさる、そのなかの一本が上記の映画だった。
ときめいたものについて順次書きたい。