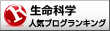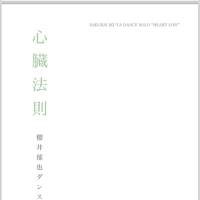嘘つき、、、
という言葉に興味がある。なぜか、面白い言葉と思う。
「ほんとうのことを知りたければ劇場へ行け」という一言がアポクリファ(聖書の外典)にあって、とおい昔から「ほんとうのこと」を探している人が劇場には集まっていたのだとわかる。
劇場とは、嘘ばかりつきながら実のところ本当の本当を探している場所なのだと僕は思っている。だからテロリストは劇場を攻撃するのかもしれず、だからファシストは劇場を占有しようとしたのかもしれないとも思う。(そして多くの反抗もまた、劇場で続けられてきた。)
トリュフォーの『終電車』はまさにそのような〈劇場〉をえがく映画で、僕はそれを何回も観ている。きょうまた観たが、おそろしく素敵でこまった。シャンソン、つづく最初の台詞のやり取り数秒で、とりこになった。男と女の歌、そして、男と女の会話。いきなりドパルデューだ。テンポ、言葉選び、つまり呼吸の音楽に胸がいっぱいになってしまった。
あらゆることが言葉にされてゆくがそれは説明のための言葉ではなく、ともにあるための言葉にきこえる。ともにあるための、というのは呼び交すことだったり、互いを感じ合ったりすることだったりする。それゆえ、あらゆる言葉がエロチックになってゆく。息が聴こえる。そうすると、演劇もやはりダンスなのでは、と勝手にひきよせてしまう。逆さでも良いにちがいない。つまりダンスもまた演劇つまり関係なのかもしれない。関係し、からまり、むすぼれ、ときほぐされ、、、。そんなことを思う間にあのカトリーヌ・ド・ヌーヴの登場をみる。セリフが、仕草が、そして、ためいきが始まる。
いつしか、すべての言葉がリズムで、すべての仕草が流動で、すべての物語が劇場を生成する。呼吸の映画だと感じながら観ている。観ながら歴史の物語だということを僕は忘れている。ナチ占領下のパリ、パリの劇場の葛藤と誇りの物語なのだが、それをこえて男や女の魅力に酔っている。言葉と、光と闇と、モンタージュの呼吸とともに、いつしか心踊っている。ダンスシーンはないけれど、この映画には誰かとダンスするときのような心地が、すこし漂っている。なにもわからなくていい、と思い始める。この時間がもっと続けば、とも思っている。解釈や批評はだれかに委ねて、じっとじっとただ見つめていたくなる。それもダンスに似ている。
ダンスの舞台は一回性が強い。ダンスは生きた肉体の踊りと生きた観客の眼差しと生きたスタッフの呼吸で出来ている。ダンスは二度おなじものを観ることが出来ない。記録を視ることはできても全身で感じているわけではない。肉体に封印された無数の何かが舞台でどっと露出する。作品が引き金になって意図されたものも無意識も何もかもが解放され照らし出され響き出る。それらを肌が感じる。映画は何回も見ることができて何回見ても新たな発見がある。映画には沢山の何かが光と闇に封印されている。映画には生命の軌跡が光と闇によって刻印されてゆく。
映画は世界を世界に語ろうとするのだろうか。ダンスは存在と存在を関係しようとするのだろうか。この似て非なる力学はとても面白いと思う。そんなことを、思いながらトリュフォーの終電車をみつめる。みつめながら思う。芝居のことを、踊りのことを、劇場のことを、嘘のことを、本当というもののことを、、、。