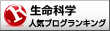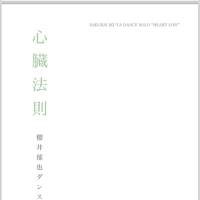この数ヶ月、グスタフ・マーラーのいくつかの楽曲を聴きこんでいました。直弟子であったブルノ・ワルターによる録音は非常に古い音源ですが、やはり凄いと思いました。
マーラーは高校生の頃に来日したバーンスタインの演奏会に度肝を抜かれてしばらく聴きまくったのですが、いろいろな出来事のなかで、距離ができていきました。
世界の底から這い出てくる情念をつきつけてくる音の嵐の、あの絡まりついてくるような執拗さを、ある時期の僕は疎ましく思い、遠ざけてしまいました。そして30年ちかくも疎遠になっていました。
再び聴いたのは東日本大震災の直後でした。あの日の東京で極めて少数の人々を前に行われた演奏会の記録映像を観たのです。第5交響曲。断片的だったのですが、心に深く食い込みました。
今年は緊急事態宣言のころから、稽古でいくつかの曲を踊りました。突然の異常事態と不意打ちの空白にとまどっていたときの稽古の選曲に、直感的に出てきたのがマーラーでした。そして、すっかり距離が空いていた彼の音楽との出会い直しは、ほかにも遠ざかっていた様々なものやことに、再び耳や目を澄ますきっかけにもなっていきました。
マーラーの、虚無と闘うかのような過剰な音の波は、いま経験している時代/日々/困惑にも、どこか重なる気がします。
独舞の稽古で踊ったのは、5番の葬送曲、2番の『復活』に含まれる歌曲、そして『大地の歌』。
『復活』は演奏時間が1時間半におよぶシンフォニーですが、深刻で仰々しいほど劇的です。不気味な下降音のしつこい波から始まり、押し寄せてくる「圧」の中から、次第に、悩ましい「歌」が湧き上がってくる。悩ましく絶望的な歌が光を獲得してゆく最終楽章は、音楽による「嗚咽」にさえ思えます。
レッスンでは、5番のアダージェットを紹介し、みんなで踊りました。トーマス・マンの『ベニスに死す』はコレラ禍のヴェネチアを舞台とする小説ですが、これを映画化したルキノ・ビスコンティが非常に印象的に挿入した曲です。
特別な力を感じるのは『大地の歌』です。この音楽のなかで繰り返し歌われる「生ハ暗ク、死モマタ暗イ」(Dunkel ist das Leben, ist der Tod!)という言葉は、まさに現代的な響きで、胸に突き刺さります。
つい数日前に掲載した稽古写真はこれを踊っている一瞬間でした。
今、あらためてこの作曲家のいくつかの曲を聴きこみながら、やはり何か異様な重さが吹き込んでくるのを感じています。歌曲にも、室内楽にも、交響曲にも、何かが過剰で、へたをすれば滑稽になってしまうほどに荘厳で、それゆえ、混乱と痛覚に満ちていて、聴きながら、心が深く深く落下するのです。
マーラーの音楽群からは、ごまかしのない心の震えや迷路や絶望感が、洪水のように押し寄せてきます。それゆえに、そこはかとなく恐ろしく、悩ましく、しかし、陶酔的な、危うい美しさが漂うのかもしれません。
_____________________________________