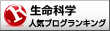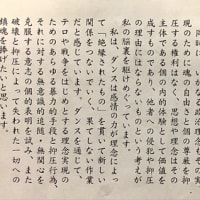真っ青な空に、
ゆっくりと一本の白線が描かれてゆく。
飛行機雲だとわかっているのだが、
空が裂けてゆくように、思える。
まぶしい。
ある映画の始まりを思い出した。画面いっぱいの青空に飛行機雲がずっとのびてゆく。流れる音楽は左手のためのコンチェルトだ。低い持続音の高まりをピアニストが左手でキャッチすることから壮大なリズムが沸き起こる。ゴダールの『パッション』という映画の最初だ。
ゴダール作品のなかでも特に鮮明におぼえている一本で、目を奪われたシーンが多い。10回以上は観たと思う。観るたび、映画の内容とはまるで無関係に、そしてランダムに、僕は、さまざまなことを思い考える楽しみを感じた。好きなダンサーのダンスを見つめる時と、どこか似た時間の感覚なのだ。物語よりも映像を、映像そのものよりも映し出されたコップや人の肌や髪が、台詞の意味よりもそれを発音しようとする人の息音が、つよく感覚に働きかけてくるように、僕には思えた。
ゴダールの作品は、わかるようでわからない。わからないがなにかを感じる。つまり生身の人間にちょっと近いのかしら。だから何回も観たくなるのかもしれない。
海が嫌なら、
山が嫌なら、
勝手にしやがれ。
だっけ、、、。初めて見たのはそんな台詞に始まる白黒映画だった。物語というよりは、出来事のリズムを視ているようだった。
すこし前に観た最近作『イメージの本』はすべてが始まりのような映画だった。断片がおびただしく繰り出され続けた。見終わってもまだ自分が何を見ているのか、見ていたのか、釈然としなかった。これは何だろう。そう問いつづける。想像しつづける。見終わっても想起し続けようとしている。何を見ているのか。何がそこに起こりつつあるのか。つまり見終わってなお映画は始まり続けているのだった。
ゴダールの映画群は一種のルネッサンスだったのでは、とこのごろ思う。沢山の感動を僕は映画からもらったが、ゴダールの映画には感動というようなものが沸き起こった記憶はない。光の波が、影の呼吸が、網膜を激しく叩いた。そして、ある種の思考が、映画の中で、あるいは明滅するスクリーンの光と影のリズムとともに、ドキドキと脈を打ち始めるのだった。視ることから始まる思考がある。その味を知った。他の映画に、その経験はなかった。
ゴダールの映画はいつも断片で出来ている。スクリーンに時間の破片が散りばめられている。あらゆるストーリーは夢のようにバラバラになって並行している。辻褄合わせは困難で馬鹿馬鹿しいことにさえ思えてくる。何も分からなくたって、沢山のことを感じているからだ。つまりすべては「今」ということなのだと思う。
じっさい、僕らの現在には連続と非連続が混在していて、さまざまな出来事が繋がらない断片のまま並行している。僕たちも、僕たちの周囲の出来事も、バラバラだから繋がりたがっているのだろう。世界はひとつではない。とても沢山の世界が、生まれては消えている。この世界の隣には、別の世界が、きっとある。そんなことを想像しながら、僕は生きているし、そんなことを想像しながら、僕は踊ったり書いたりしている。