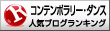踊りをしたり観たりしていると、消えてゆくのが何だか勿体無い感じがすることがあるが、生きている人がやるしか無いことだから、それも良さの一つと腹を決めている。踊りだけでなく、舞台はやはり消えものなのだから、その体験は全部、二度とないものだ。
今迄に観ることが出来たなかでも、そんな二度とない体験という感覚が強烈だったのは、僕の場合は、ポーランドの「クリコット2」というカンパニーの舞台で美術家としても著名な演出家タデウシュ・カントールがリーダーだった。何回も思い出して、観ることが出来て良かったなぁと思う。
取り分け代表作の『死の教室』はまだ高校生で初めてだったのもあって、こんな面白いものが世の中にあるんだと興奮した。上演はパルコだったが、テレビでもやったしアンジェイ・ワイダが映画にしたから、何度も観たが、やはり舞台の興奮度は異様なものだった。
この舞台は長く話題を呼び研究や評論も沢山あるが、僕には第一印象がそのまま残っていて余り色々解釈したら壊れてしまうと勿体無い感じのものだ。
黒い色調で統一された舞台は学校の教室になっている。出演者たちと一緒に、演出家のカントールが舞台にずっと居る。自らの記憶を見つめている人のようだ。
しかしカントールは、あまり落ち着いていない。端っこで座って眉間に皺をよせて舞台の上や客席を見つめてみたり、かと思ったら、のそのそと舞台美術をいじり直したりもする、そして何より頻繁に演者のそばに行って何か耳打ちしたり、指揮者みたく手を振って合図をしたりを繰り返し続ける。要は、この作品は上演しながら創り続けているものなのだ。
思い出しながら記憶を再生させてゆくみたいでもあるし、逆に誰かの記憶が生き物のように勝手気侭に変化して別の物語を作り出そうとしているようでもある。
時には出演者どうしでだって、話しが通じたり通じなかったりしているみたいな感じもあったからアナーキーだった。だから、沢山のアクションや身体の接触や、わめいたり笑ったりも特別な個性でやるのだ。
言葉そのものが舞台の上で発明されていくようなその感じは、赤ちゃんと赤ちゃんがもとから通じない言葉で交流してるみたいなもので、それは声も身体も全部使っていて、お喋りとか踊りとか歌などが混ぜこぜのママで噴出している感じだ。知識なんか仕方がないから、却って僕ら外国人には親切な語りかけかただなぁ、と感じながら観ていた。
あのとき、言葉というのは元々は、こんなふうな、気持ちを刺激しあって想像しあう行為全部なのかなと思った。
舞台にはいつもワルツが響いている。しかし、盛んに笑い歌い踊り喧嘩し、破茶滅茶な行為を展開する人物たちは皆んな青ざめたような灰色の顔で、皆んな老齢で、皆んな古びた子供人形を連れている。
長い時間を過ごしてゆくうちに、奇妙で破茶滅茶な舞台展開の背景にある膨大な死のイメージが押し寄せている。
直接は表現されていないのに、戦争や抑圧の匂いが漂う、かと思うと深い孤独が襲う。そして言葉もなにも判らないのに、そこはかとない哀しさと怒りとがして不可思議な懐かしさが渾然一体になって、胸騒ぎとしか言いようのない感情が湧き上がっていた。
判らないほうが却って深く感じてしまうことが、この舞台にはぎっしりとあった気がする。あのような舞台は未だ他に体験したことがない。
今迄に観ることが出来たなかでも、そんな二度とない体験という感覚が強烈だったのは、僕の場合は、ポーランドの「クリコット2」というカンパニーの舞台で美術家としても著名な演出家タデウシュ・カントールがリーダーだった。何回も思い出して、観ることが出来て良かったなぁと思う。
取り分け代表作の『死の教室』はまだ高校生で初めてだったのもあって、こんな面白いものが世の中にあるんだと興奮した。上演はパルコだったが、テレビでもやったしアンジェイ・ワイダが映画にしたから、何度も観たが、やはり舞台の興奮度は異様なものだった。
この舞台は長く話題を呼び研究や評論も沢山あるが、僕には第一印象がそのまま残っていて余り色々解釈したら壊れてしまうと勿体無い感じのものだ。
黒い色調で統一された舞台は学校の教室になっている。出演者たちと一緒に、演出家のカントールが舞台にずっと居る。自らの記憶を見つめている人のようだ。
しかしカントールは、あまり落ち着いていない。端っこで座って眉間に皺をよせて舞台の上や客席を見つめてみたり、かと思ったら、のそのそと舞台美術をいじり直したりもする、そして何より頻繁に演者のそばに行って何か耳打ちしたり、指揮者みたく手を振って合図をしたりを繰り返し続ける。要は、この作品は上演しながら創り続けているものなのだ。
思い出しながら記憶を再生させてゆくみたいでもあるし、逆に誰かの記憶が生き物のように勝手気侭に変化して別の物語を作り出そうとしているようでもある。
時には出演者どうしでだって、話しが通じたり通じなかったりしているみたいな感じもあったからアナーキーだった。だから、沢山のアクションや身体の接触や、わめいたり笑ったりも特別な個性でやるのだ。
言葉そのものが舞台の上で発明されていくようなその感じは、赤ちゃんと赤ちゃんがもとから通じない言葉で交流してるみたいなもので、それは声も身体も全部使っていて、お喋りとか踊りとか歌などが混ぜこぜのママで噴出している感じだ。知識なんか仕方がないから、却って僕ら外国人には親切な語りかけかただなぁ、と感じながら観ていた。
あのとき、言葉というのは元々は、こんなふうな、気持ちを刺激しあって想像しあう行為全部なのかなと思った。
舞台にはいつもワルツが響いている。しかし、盛んに笑い歌い踊り喧嘩し、破茶滅茶な行為を展開する人物たちは皆んな青ざめたような灰色の顔で、皆んな老齢で、皆んな古びた子供人形を連れている。
長い時間を過ごしてゆくうちに、奇妙で破茶滅茶な舞台展開の背景にある膨大な死のイメージが押し寄せている。
直接は表現されていないのに、戦争や抑圧の匂いが漂う、かと思うと深い孤独が襲う。そして言葉もなにも判らないのに、そこはかとない哀しさと怒りとがして不可思議な懐かしさが渾然一体になって、胸騒ぎとしか言いようのない感情が湧き上がっていた。
判らないほうが却って深く感じてしまうことが、この舞台にはぎっしりとあった気がする。あのような舞台は未だ他に体験したことがない。