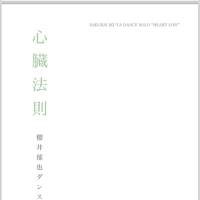疲れが出たからスカッとする映画でもと「Ones upon a time in Hollyhood 」を観た。ブラピとデカプリオのあれだが、勘違いだった。えらく味わい深い作品だった。それは、欲望と悪についての、それゆえそれは友情についての映画に思えた。
うそとほんと、こことむこう、つまり境目の世界に迷い込んだ気分だった。ばかでかいスクリーンに映し出されるその映像のすべてがキメあらく乾いている、おもしろい、眼もざらつく。
この映画のなかでは、笑いの正体が暴露されているし、凶悪と狂気と快楽の接近が、それとなく臭う。ぼくは、いろいろな立派なお説教よりも、夜明け前の街の汚れや白々とした気温に神聖さを感じてしまう。だから、こういう映画が好きなのかもしれない。
タランティーノ監督の映画から、これほど深い味わいを感じたのは初めてだった。
じつはキル・ビルのあと、なぜか見てなかった。だから、ずいぶん長い間あの印象のまま僕のタランティーノ観は停止していた。でも、これからは全部、観るかもしれない。最初からエンドロールの最後の一瞬まで、感心しっぱなしだった。感動じゃなくて感心ってこの心地だ、と思った。おおげさに言えばサドを読んだあとみたいだ。
音も画も編集もパルプフィクションからずっと継続的に探求されているのだろう。息をのむ、膝を打つ、そんな瞬間が2時間以上つづく。そして映っているもの全てが、えげつなく強い。力に満たされた映画だと思った。そして、芝居に心おどった。デカプリオもブラピも激しくいい芝居をしつづけるが、チャールズ・マンソン一味のひとりを演じた俳優たちが、ダコタ・ファニングをはじめ、神がかり的。半端ではない。
物語の展開も、シャロン・テート事件を扱っているというから、どうなるのかとは思っていたが、あんなふうに来るとは思いがけなかった。最後のほうのメチャクチャのめちゃくちゃさに、とんでもなく無関係なんだろうけれど、僕は勝手に沖縄やベトナムの映像を重ねてしまった。アメリカ、、、。
物語も映像も、すさまじい展開だが、レクイエムを感じた。タランティーノの眼差しに才気を感じた。深い深い痛みが、軽やかさや洒落っ気を生み出すのだろうか。現実に対する絶望の深さが、光を生み出そうとするのだろうか。だから、ああいうふうになるしかないんだなと、思った。ひどく共感してしまう。
憂さ晴らしに映画でも、と思ったが、奇妙な刺激を受けて脳ミソの中枢に何かが入り込んでしまった。これを観たせいで、なんだか眠れない。
____________________________________________________
OPEN !!
11/9〜10 plan-B(くわしいご案内・チケット情報など、上記LINKよりご閲覧ください)
SAKURAI IKUYA DANCE SOLO 2019 :9th-10th Nov.
(detail and ticket information)