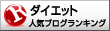・植物ホルモンPlant hormone しょくぶつほるもん
以前のホルモンとは動物体内の内分泌系で作られ、ごく微量で標的器官に対しシグナル伝達物質として働き影響を与える有機化合質としてのことであり、植物についての定義はなされていませんでした。
しかし、植物に関しての生理的な研究が進むにつれて、植物の細胞内でも動物ホルモンと同じような働きをする物質を複数発見するに至っています。発見の当初は植物ホルモン=動物ホルモンの植物版という定義でした。さらなる研究の進展により、現在では動物ホルモンとの差異を多数発見しています。
植物ホルモンは植物自身が作り出し、低濃度で自身の生理活性・情報伝達を調節する機能を有する存在で、植物にすべてのものに共通し普遍的に存在し、その化学的本体と生理作用とが明らかになった物質です。
動物におけるホルモンとは異なり、分泌器官や標的器官が明確ではなく、また輸送のメカニズムも共通していません。
主にオーキシンAuxin、ジベレリンGibberellin、サイトカイニンCytokinin、エチレンEthylene、アブシジン酸Abscisic acidなどが知られます。
◇オーキシンは一番最初に確立された植物ホルモンです。発見のきっかけは植物に光を当てると、茎が光の方向に屈曲する現象をヒントに多くの研究者が携わり発見しています。
1928年にオランダのウェントFrits W.Wentという科学者がマカラスムギ(エンバク)の幼葉鞘を用いて光屈性について研究していた際にこの物質の存在を示唆し、彼はそれをオーキシンと名づけています。オーキシンは芽でつくられ、重力方向に移動しながら濃度によって各部位で成長促進として働きます。
茎の伸長生長促進、根の生長阻害、頂芽・腋芽優先生長させます。頂芽を切断するとオーキシンの濃度が低下し、側芽の成長が促進します。
◇ジベレリンは、植物ホルモンの中で、日本人が唯一発見し、構造を決定したものです。1926年、当時台湾総督府の農事試験場に勤務していた黒澤栄一により、カビが寄生することによって稲の植物体を徒長・枯死させる馬鹿苗病の原因毒素として報告していました。
なお、この時点ではジベレリンという命名ではなく、1938年に東京帝国大学教授、薮田貞治郎(やぶた ていじろう)と住木諭介(すみき ゆすけ)によって馬鹿苗病の完全世代(学名Gibberella fujikuroi)から単離した際に、ジベレリンと命名しています。
やがてカビだけでなく、豆科植物の種子、筍からからも見つかり植物を成長させるホルモンであることがわかっています。構造が似ているものが数十種見つかり休眠打破、開花促進、結実などの作用があることも分かりました。
これらを利用し1959年に岸光夫によってデラウェアの種無しブドウが花穂をジベレリン処理して得られています。発芽促進に種子、種芋に、ミカンの落下防止、花の開花促進などの農作物に広く応用しています。ジベレリンは現在も発見が続く植物ホルモンであり、その数は100種以上です。
◇サイトカイニンは1913年と早くに見つかっていましたが生合成などの分野で研究が進展し始めたのは21世紀に入ってからといいます。
初めてサイトカイニンという名称が世界に認められたのは、1965年で、1963年にサイトカイニンの命名者となるオーストラリアのリーサムD. S. Lethamによって、未熟なトウモロコシ種子からゼアチンZeatinという物質を発見しています。
細胞質分裂の英語名CytokinesisからサイトカイニンCytokininと命名しています。サイトカイニンは、オーキシンと協働して細胞分裂を促進することが知られます。
エチレン生成を抑制し、老化を抑えブロッコリー小花の老化を抑制し、品質を保持できます。ワタの収穫直前に葉を落とすことに使われます。
オーキシンとサイトカイニンによる拮抗的な頂芽優性の制御、側芽の成長を促進に働きます。多くの場合、オーキシンやサイトカイニンなどの植物ホルモンの濃度比を変えることによって植物個体を再生しています。
動物のホルモンにサイトカインというものが存在しますが語源はどちらもCytokinesisで同様ですが、全く別の物質です。
◇エチレンの、植物ホルモンとしての働きは1960年台以降で発見は100年前のガス灯の近くの街路樹の葉がガス灯の遠くにあった葉よりも早く落葉したことによるものです。
成長の異常促進による老化の急激な進行で花芽形成が促進する場合もあるのに対し、ジャガイモで発芽が抑制されるといった違いがあります。人工的に追熟を行う場合に利用し成熟ホルモン(老化ホルモン)ともいわれ実用化しています。
逆にエチレンを除くことによって貯蔵食品の劣化を遅らせることも行われます。鮮度保持剤としてエチレン吸収剤を包装した中に入れること、CA貯蔵(酸素に触れないようにして果物の呼吸を抑制し追熟を遅らせ鮮度を保たせる貯蔵法)があります。
エチレンガスが細胞壁の主成分であるセルロースを破壊するセルラーゼに働きかけ、細胞壁の組織破壊が進行することによります。
なお、エチレンは常温で気体であり、古典的な植物ホルモンの中では、周囲の個体にも影響を与えるといった点に特徴があります。
◇アブシシン酸は、1961年にLiuとCarnsがワタの葉柄由来の落葉促進物質をAbscission(葉などの離脱)にちなみアブシジン(Abscisin)と命名していました。
オーキシン発見のち、そのオーキシンを阻害する物質があることがわかっていたことから、研究が続けられ1963年に大熊和彦によって、ワタの未熟な果実から同様の物質を単離、1967年の第6回国際植物生長物質会議でアブシシン酸(アブシジン酸)としています。主に成長を阻害する方向に働きます。
例えば植物表面に存在する気孔を閉鎖し、乾燥耐性の獲得、ジベレリン阻害による種子の発芽抑制、悪い環境での発芽を抑制しています。アブシジン酸とエチレンによる協調的な離層形成しています。
ピルビン酸とグルタルアルデヒド3-リン酸(いわゆる非メバロン酸経路)からカロテノイド、キサントキシン、アブシシンアルデヒドを経由して合成するセスキテルペンに属する植物ホルモンのひとつで種子形成や休眠・発芽さらにはストレス応答において重要な役割を担っていると考えられます。
また乾燥などのストレスに対応し合成することからストレスホルモンとも呼ばれ植物が乾燥に耐える為に産生するホルモンとして存在します。
1970年台までの植物ホルモン研究は主に以上に記した5つのホルモンを中心に行われていました。
こうした5つのホルモン研究を中心とした研究の中で、更に新たなホルモンが次々と見つかっています。
◇ブラッシンは1979年に、アブラナで見つかっていながらごく微量であったために検出ができなかった植物成長物質のブラッシンBrassinという化学構造を決定しブラシノステロイドと命名しています。現在では、ステロイドの骨格を持つ植物ホルモンを総称した呼称となっています。
他のホルモンと特性が類似し、根や茎の伸長促進、細胞分裂促進、葉の拡大、老化促進、ストレス耐性の働きがあります。
◇ジャスモン酸は植物が様々なストレスを受けた際に放出するジャスモン酸jasmonic acidについても、植物ホルモン様物質として認められています。果実の熟化や老化促進、休眠打破などを誘導します。また傷害などのストレスに対応して合成しています。
この物質は昆虫などによる食害を受けた際、それをジャスモン酸を介して他の植物や同じ植物の別の場所に伝え、防御に働きます。
フロリゲンは1920年の実験で花の形成は日長に支配されるという報告があり、その後、1999年に京都大学の荒木崇らによって、シロイヌナズナという植物から見出しFT遺伝子というものを発見し、これは遺伝子でフロリゲンFlorigen(花成[かせい]ホルモン)の候補として有力なものでした。
その後2007年にフロリゲンはFT遺伝子の産物、つまりFTタンパク質がフロリゲンの正体なのではないかという結果を示しています。提唱から70年以上の時を超えて、初めてフロリゲンという植物ホルモン様物質の存在を確認しています。
◇ジャスモン酸メチルMethyl jasmonateは、ジャスミンの香りで揮発性であり、これが空気中を伝わって近隣の植物にシグナルを伝達します。植物ホルモン様物質で植物防御、種子発芽、根の伸長、開花、果実の熟化や老化促進、休眠打破などを誘導します。
システミンの誘導により、リノレン酸からジャスモン酸が生じます。
そんな中、近年、アミノ酸100種以下の比較的小さな分泌型ペプチドが細胞間の情報伝達に関与していることが明らかになっています。それらを総称して植物ペプチドホルモンPlant peptide hormone と呼び、植物ホルモン様物質として、植物ホルモンの一種とみなしています。
◇システミンSysteminは、害虫に対する化学防御を活性化する長距離シグナルとして機能する小ポリペプチドでペプチド性であると最初に確かめられています。
◇サリチル酸は、植物に病原菌が感染すると酵素(PAL、Phenylalanine ammonia lyase)が活性化し、フェニルアラニンからケイヒ酸を経てサリチル酸が合成され、抗菌性タンパク遺伝子の発現が活性化します。
◇フィトスルフォカインPhytosulfokine(ファイトスルフォカイン)は、最初アスパラガスとニンジンの培養細胞から調節因子として同定しています。
活性酸素は、植物自体にも悪影響を及ぼすので、過剰の活性酸素はすみやかに除去しなければなりません。そのため、抗酸化剤であるビタミンA、C、Eやカロテノイドによって、植物はこれを除去しています。
従って、抗酸化剤の含量が高いもの、すなわち高品質の作物品種、ほど病害虫に対して感受性が高く、被害を受け易いのです。病害虫の食害によって、ビタミン類やカロテノイドが40%も失われることの報告があります。
遺伝子組み換え食品とかもあり、人の手によって操作した食物も一長一短があるようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。