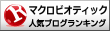・延胡索 えんごさく
ケシ科、湿った原野や山地、林の中に見られる多年草でケシ科の多年草数種(ジロボウエンゴサク・ヤマエンゴサク・エゾエンゴサクなど)の総称のこと。
茎は弱々しく 高さ10~20cm、葉は長さ1~3cmで、線形から広卵形まで変化がある。先端に青紫または紅紫色で長さ1.5~2.5cmの花を総状につける。小花柄(しょうかへい)のつけ根にある苞(ほう:はかま、芽や花弁の下につく葉)は先端が3~5裂する。
花期は4 ~5月で春の開花時に、地上部の全草を採取して軽く茹でて、おひたし、和え物、酢の物、薄くころもをつけて揚げ物にできる。 エゾエンゴサクの仲間は、毒草が多いケシ科の中で食べることができる。
東北以北の自生のエゾエンゴサクの花が枯れた6~7月頃に、地下の塊茎を水洗い蒸して日干にしたものを生薬で和延胡索(わのえんごさく)といい、漢名の延胡索(えんごさく)の生薬として用いられる。
アルカロイドのテトラヒドロパルマチンTetrahydropalmatine 、コリダリンCorydalineほかを含有し血行をよくし鎮痛、鎮痙(ちんけい)作用があり、胃粘膜を保護する。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。