
八木朋直 履歴

八木朋直が出資して架橋された、五姓田芳柳筆 「新潟萬代橋」図 明治19年
橋名を書いた「伯爵柳沢前光」、揮毫を委託した「八木朋直」二人の間を取り持った
「庄内屋しん」について、興味深いホームページが見つかりました。
1841 天保 12 米沢藩士カ猫文和弥の次男として誕生
1853 嘉永 6 12才 八木家(丈七(米慎))の養子となる。
1860 元治 元 19才 関流算法の免許を皆伝(師:米沢藩士 今井直方)
1865 文久 3 24才 上杉藩主の京都上洛に小荷駄役兼会計方として随行
1867 慶應 4 26才 戊辰戦争 軍事検地方兼会計元締役として参戦(会津、新潟)
1869 明治 2 28才 越後水原府に職をえる。(職務:財政整理)
1871 明治 4 30才 新潟県会計課長(越後の県を統合新潟県となる)
1872 明治 5 31才 国立銀行条例制定 学製(学校制度開始)
学製で数学は洋算が採用される(和算衰退)
1874 明治 7 33才 国立第四銀行開業
1876 明治 9 35才 第四銀行2代目の頭取就任
1886 明治 19 45才 萬代橋 架橋(共同経営:申請内山信太郎/出資八木朋直)
1896 明治 29 55才 新潟銀行 取締役会長
1897 明治 30 56才 新潟商業銀行 取締役
1899 明治 32 58才 新潟県農工銀行 監査役
1899 明治 32 58才 新潟市長4代目就任
1919 大正 8 78才 新潟市史編纂顧問
1929 昭和 4 89才 永眠
第四銀行の設立
・戊辰戦争後政治的社会的に混乱し品質の落ちた通貨製造、偽札、偽金が出回る。
・諸外国から通貨の安定を求められる。
・明治5年国立銀行条例
・明治7年第四銀行開業(明治6年12月認可)
・国立銀行四行はともに初年度から経営不安広がる(国立銀行は五行認可、開業四行)
・第四銀行も初年度赤字、経営不安広がる(株価100円が80円となる)
・明治政府は経営改善策を指示
・改善策の1つとして経営管理のできる実務者へ変更 八木朋直の就任

八木朋直が、職場で指揮する時使ったと伝えられている「軍扇」
なぜ米沢藩出身八木朋直が戊辰戦争終了後(水原府に職を得る)7年で第四銀行の頭取になりえたのか?
・江戸時代には必要としない数値管理できる実務者が明治時代移行の過程で嘱望され
関流算法皆伝の八木朋直の緻密な数値管理能力が生かされた。
・江戸からの移行明治という新時代には世の中の価値観が大きく変動した激動期で
熊本出身の新潟県令楠本正隆と米沢出身の八木朋直との出会いで新潟の過去にとらわ れない改革ができたのではないか。
米沢の地に根付いた上杉鷹山の『格式を捨て実利収める』という風土に育った。
米沢の節約関が原の戦い後会津120万石から米沢30万石に転封され世継騒動から15万 石に減らされる。
財政は藩存続の危機に陥るほど悪化するが、上杉鷹山を向かえ藩政改革による
財政再建が実施された。朋直はそんな風土の中で会計方という財務会計の仕事をし た。
八木朋直の上杉鷹山の墨蹟コレクション、鷹山の法要などにも出席し鷹山の考え方を
信奉していたと思われる。
鷹山の革新的な改革手法を身につけた朋直が新潟県令楠本正隆の明治の激動期の改革 の助けとなったとおもわれる。
なぜ緻密な数値管理のできる実務者がいなかったのか?
・算数は下級武士(御算用侍・算盤侍)の仕事とされ上級武士にその指導はなかった。
(算盤を仕事にするのは士農工商の身分制度のなか最も身分の低い商人の仕事とされ
武士本来の仕事ではないとされた。)
・新時代に入り緻密な係数管理のできる実務者が極端に不足した。
高度な和算の存在
・藩財政は大福帳の形式で入出費の記帳の単純な計算方式で高度な数学を必要と
しない。
・他方、江戸時代には暦が生活に根づきその正確さを要求された。
正確な暦には天文学は必要であり天体の動きには高度な数学を必要とした。
・日本独自に方程式や台数を考えだした関孝和や800年に2日のズレをなおす
改暦を行った渋川晴海がいた。
・八木朋直はこの関流算法の免許を皆伝されている。
*皆伝免許・朋直の書いた算学神壁、江戸期出版の算学神壁。
明治期の塵劫記(算数の入門書)など参照
世界に誇れる日本独自の和算はなぜ衰退したのか?

八木朋直の和算書
・嘉永6年黒船が来航すると外国勢力に対抗するための軍艦を購入し外国人の講師雇い 入れ教育を受ける。この際の講義は全て洋算でおこなわれる。
・明治6年学製(学校制度)がはじまる。
・士農工商という格差社会から国民という均一・等質の市民をつくることが教育目標と され、自身のレベルに合わせて各自各様に進める寺子屋方式の教育(和算)は洋算に 代わり和算は衰退し神社に掲げられた算額は解する人の減少とともに廃棄された。
晩年の朋直
・朋直の晩年の手記から明治9年ころに大量の喀血により医者から見離され
短命であると思った。
・財産を譲る実子がなく世のためになるものとして投資しよう考えた。

八木朋直の遺品箱に直筆の言葉が
最後に
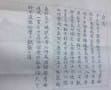
八木朋直の「自序」
今回の話は江戸から明治という変革期に士農工商という身分制度が崩壊し
政治的社会的に全ての価値観が変化していった時期に
八木朋直という和算を武器に大変動期を駆け抜けた男のお話でした。
晩年の八木朋直は自身の号に柳雪のほか橋架翁として萬代橋に愛着を持ち続けた。
講演者 本田より

八木朋直が出資して架橋された、五姓田芳柳筆 「新潟萬代橋」図 明治19年
橋名を書いた「伯爵柳沢前光」、揮毫を委託した「八木朋直」二人の間を取り持った
「庄内屋しん」について、興味深いホームページが見つかりました。
1841 天保 12 米沢藩士カ猫文和弥の次男として誕生
1853 嘉永 6 12才 八木家(丈七(米慎))の養子となる。
1860 元治 元 19才 関流算法の免許を皆伝(師:米沢藩士 今井直方)
1865 文久 3 24才 上杉藩主の京都上洛に小荷駄役兼会計方として随行
1867 慶應 4 26才 戊辰戦争 軍事検地方兼会計元締役として参戦(会津、新潟)
1869 明治 2 28才 越後水原府に職をえる。(職務:財政整理)
1871 明治 4 30才 新潟県会計課長(越後の県を統合新潟県となる)
1872 明治 5 31才 国立銀行条例制定 学製(学校制度開始)
学製で数学は洋算が採用される(和算衰退)
1874 明治 7 33才 国立第四銀行開業
1876 明治 9 35才 第四銀行2代目の頭取就任
1886 明治 19 45才 萬代橋 架橋(共同経営:申請内山信太郎/出資八木朋直)
1896 明治 29 55才 新潟銀行 取締役会長
1897 明治 30 56才 新潟商業銀行 取締役
1899 明治 32 58才 新潟県農工銀行 監査役
1899 明治 32 58才 新潟市長4代目就任
1919 大正 8 78才 新潟市史編纂顧問
1929 昭和 4 89才 永眠
第四銀行の設立
・戊辰戦争後政治的社会的に混乱し品質の落ちた通貨製造、偽札、偽金が出回る。
・諸外国から通貨の安定を求められる。
・明治5年国立銀行条例
・明治7年第四銀行開業(明治6年12月認可)
・国立銀行四行はともに初年度から経営不安広がる(国立銀行は五行認可、開業四行)
・第四銀行も初年度赤字、経営不安広がる(株価100円が80円となる)
・明治政府は経営改善策を指示
・改善策の1つとして経営管理のできる実務者へ変更 八木朋直の就任

八木朋直が、職場で指揮する時使ったと伝えられている「軍扇」
なぜ米沢藩出身八木朋直が戊辰戦争終了後(水原府に職を得る)7年で第四銀行の頭取になりえたのか?
・江戸時代には必要としない数値管理できる実務者が明治時代移行の過程で嘱望され
関流算法皆伝の八木朋直の緻密な数値管理能力が生かされた。
・江戸からの移行明治という新時代には世の中の価値観が大きく変動した激動期で
熊本出身の新潟県令楠本正隆と米沢出身の八木朋直との出会いで新潟の過去にとらわ れない改革ができたのではないか。
米沢の地に根付いた上杉鷹山の『格式を捨て実利収める』という風土に育った。
米沢の節約関が原の戦い後会津120万石から米沢30万石に転封され世継騒動から15万 石に減らされる。
財政は藩存続の危機に陥るほど悪化するが、上杉鷹山を向かえ藩政改革による
財政再建が実施された。朋直はそんな風土の中で会計方という財務会計の仕事をし た。
八木朋直の上杉鷹山の墨蹟コレクション、鷹山の法要などにも出席し鷹山の考え方を
信奉していたと思われる。
鷹山の革新的な改革手法を身につけた朋直が新潟県令楠本正隆の明治の激動期の改革 の助けとなったとおもわれる。
なぜ緻密な数値管理のできる実務者がいなかったのか?
・算数は下級武士(御算用侍・算盤侍)の仕事とされ上級武士にその指導はなかった。
(算盤を仕事にするのは士農工商の身分制度のなか最も身分の低い商人の仕事とされ
武士本来の仕事ではないとされた。)
・新時代に入り緻密な係数管理のできる実務者が極端に不足した。
高度な和算の存在
・藩財政は大福帳の形式で入出費の記帳の単純な計算方式で高度な数学を必要と
しない。
・他方、江戸時代には暦が生活に根づきその正確さを要求された。
正確な暦には天文学は必要であり天体の動きには高度な数学を必要とした。
・日本独自に方程式や台数を考えだした関孝和や800年に2日のズレをなおす
改暦を行った渋川晴海がいた。
・八木朋直はこの関流算法の免許を皆伝されている。
*皆伝免許・朋直の書いた算学神壁、江戸期出版の算学神壁。
明治期の塵劫記(算数の入門書)など参照
世界に誇れる日本独自の和算はなぜ衰退したのか?

八木朋直の和算書
・嘉永6年黒船が来航すると外国勢力に対抗するための軍艦を購入し外国人の講師雇い 入れ教育を受ける。この際の講義は全て洋算でおこなわれる。
・明治6年学製(学校制度)がはじまる。
・士農工商という格差社会から国民という均一・等質の市民をつくることが教育目標と され、自身のレベルに合わせて各自各様に進める寺子屋方式の教育(和算)は洋算に 代わり和算は衰退し神社に掲げられた算額は解する人の減少とともに廃棄された。
晩年の朋直
・朋直の晩年の手記から明治9年ころに大量の喀血により医者から見離され
短命であると思った。
・財産を譲る実子がなく世のためになるものとして投資しよう考えた。

八木朋直の遺品箱に直筆の言葉が
最後に
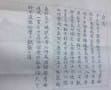
八木朋直の「自序」
今回の話は江戸から明治という変革期に士農工商という身分制度が崩壊し
政治的社会的に全ての価値観が変化していった時期に
八木朋直という和算を武器に大変動期を駆け抜けた男のお話でした。
晩年の八木朋直は自身の号に柳雪のほか橋架翁として萬代橋に愛着を持ち続けた。
講演者 本田より




















確かな予測(よみ)と深い思いをもって、
生き抜いた八木朋直。
その生き方に深く感動。
彼を生み、育てた、米沢。
いったいどんな町なのだろう。
講師に感謝!!
この度、本田さんのご講演を聞かせて頂き、明治黎明期における新潟地域力の向上に果たした功績は計り知れないと感じました。古来より新潟湊は越後の国津として日本海側の拠点港としての役割を果たして来ましたが、1586年(天正14年)には、上杉景勝の支配下に入っています。以来、時を経て、戊辰戦争では、新潟町でも、奥羽越列藩同盟軍と新政府軍が長岡城をめぐる攻防が繰り広げられましたが、同盟軍側の責任者は米沢藩家老「色部長門」でした。新政府側としては同盟軍側への軍事物資補給基地である新潟町を何としても落とす必要があり、激しく交戦した結果、新潟町は新政府軍に制圧され「色部長門」も死亡しました。(新潟高校前に追悼碑がある)
新潟町と米沢藩との関わりは歴史的な経過の中でも深い絆で結ばれていたのだと思いました。この様な背景からも、米沢藩出身でもある「八木朋直」が明治政府の下で、開港5港としての新潟町の地位向上のために奮闘したのであろうと思いました。
新潟市における「八木朋直」の知名度はどの程度のものであるのか私には分かりませんが、新潟検定のテキスト程度のものであるとしたならば寂しいと思います。湊町新潟を他県庁所在地都市(殆どが城下町)と比較して遜色の無い近代都市へとその礎を築いた「八木朋直」の「功績とその人となり」をもっと評価しても良いのではないかと思いました。
このコメントだけでも、読み応えアリ!です。
あ、なじらねっとの野内さんのブログに写真しっかり載ってますねーー。
楽しそうだなぁ。
そして、2/20にブラタモリのプロデューサーの講演があったのですね、
行きそびれてしまったー悔しい!
へたな講師に聞き上手ほめ上手の
聴講生ということでしょう。
講演終了後、米沢藩の改革に
関心を持った人が多いようですが、
本2冊紹介します。
『漆の実の実る国上下』藤沢修平
『上杉鷹山』童門冬二
日本中の武家の格式を指導する
吉良家(忠臣蔵の吉良家)の近しい親戚筋で
高い格式を要求された米沢藩。
格式を守って死すか、見栄や外聞を捨て
膨大な借財を返済するか。
今の日本の行く道が見える気がします。
3月13日ごろまで読み終えた人は
感想聞かせてください。
そんな誤解をしていて済みません。
今の御当主・邦憲さんも「謙信公家訓」を、今だに上杉一族が集まると和唱していると話していました。
世間では、鷹山以前の上杉家を無能扱いするけど、ちゃんと上杉博物館の学芸員さん達や、その他の関係者の人達が専門書を編選して、誤認の俗説を廃しています。
今後も大恩ある越後上杉家の為に、俗説を廃する事を誓う!
おかしな文章で。
これで最後にしますから、以下、どうかぜひ読んで下さい。
鷹山以前の誤った上杉家の認識を改めて欲しいのです。特に越後人なら。
《上杉家経営》
米沢30万石減封へ:執政・直江兼続の智政により、実質51万石に増やす。(城下拡張と平行して、城下を洪水から守る治水工事「直江石堤」、城下・城下町に用水・薪材を供給する堰の開削の指揮。荒地開墾(下級武士)、殖産興業を指示(越後から持ち込んだ織物「青苧」や桑・紅花・金山など殖産興業の指示)
兼続公は、「国を成すには人を成すを似てす」の通天存達和尚の教えを元に、移封後も仕官を希望する武士の召し放しをせず、共に国造りをした。
更に、後の鷹山の学問所の元になる「禅林文庫」を設立。懇意にしていた京都の僧侶・南化玄興和尚などから写筆したり譲られた貴重な本を多数使用(「宋版史記」は国宝指定)。
更に私財を投じ、日本初の銅版書「文選モンゼン」[直江版]を出版(市立米沢図書館所蔵)。大いに武士の学問に力を注いだ。
そして、滋賀や堺(大阪)から鉄砲職人を雇い入れ、白布温泉の隠し住まわせ、幕府に知られないように鉄砲製造を行った。(1000丁加増計2000丁、大砲20など)
そして指南書を書き、武芸も奨励し、武家の習いと防衛に務めた。
後の中興の祖と仰がれる藩主・鷹山も、過去の兼続公の施策を模倣したと言う。
尚、よく言われる上杉家自身での問題で、経済的に困窮したと出回る俗説は間違いである。
三代藩主・綱勝が世継ぎを残さず早世した為、幕府から録高を半分の15万石に減らされた為と、
当時、浪人が多数いて問題になっていた為(由井正雪の乱)の影響と、保科正之(綱勝の室の父)の指示があった為に、召し放し(リストラ)が出来なかったのが本当の理由。
どうか、これを機に、本当の理由を知って頂きたいと思います。
長文、失礼しました。
※参考文献…専門書「直江兼続」(高志書院より出版)や、(上杉家所蔵)『歴代古案』書状など。
他にも、[図説]『直江兼続 人と時代』(米沢市上杉博物館より刊行)に詳しい。(ネットに、米沢市の上杉家の各武将の案内もあり)