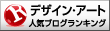箕面自由学園へ
昭和43年、私は箕面自由学園の校長の仕事を引き受けることになった。私の親しい人が学園の理事長であったため、再三の希望を断りきれなかったということもあるが、私に教育現場での仕事に対する郷愁のようなものがあったことと、箕面自由学園が幼稚園・小学校・中学校・高等学校を併せ持つ学園だったことに深く心をひかれたためであった。
箕面自由学園というのは大正15年4月、「箕面学園小学校」の名をもって私立小学校として発足した学校である。設立者は岸本汽船の社長岸本兼太郎氏、初代小学校長は神戸の諏訪山小学校の教頭から自由な理想教育を求めて私立小学校の校長となった小谷新太郎氏。朝日新聞杜から先年創刊された教育雑誌『のびのび』は、「新教育としての箕面自由学園」と題して創立当時の学園を紹介し、「小谷は知識注入主義をさけ、自発活動を重視、理科を自然科として一年からはじめた。共学、自学、自治の教育を追求した。『家なき幼稚園』の橋詰良一も協力した」と書いている。
橋詰氏は当時毎日新聞の部長を歴任し、「せみ郎」と号した文化人で、池田の呉服(くれは)神社の境内に「家なき幼稚園」(後に「自然幼稚園」と改称)を建て、季刊誌『愛と美』を出していて、学園の創立時に理事となって、学園の教育理念をつくり上げることについて、小谷校長の協力者だったようである。
後に第2代小学校長となった田村勝則氏は、回顧の文の中で当時の学園を想起しておられる。「型にはまった点とりとつめこみの教育から子どもを解放して、自然の子として、明るく、朗らかに成長させることを念願し、箕面の緑の丘に設立されたのがわが学園であった」「理科教育を重視して、子どもたちを自然に親しませ」「情操教育、全人教育を重んじ」「英語教育を重視して、国際人として、広く世界に舞台を求める態度を養うことにつとめた」「教育は人格と人格とのへだてなき交渉であることを思い、教師にその人を得て、学校が児童の幼き生命をはぐくむ苗床であり、これを培う壌土であるとの信念から、学校を温かく楽しき愛郷たらしめようとした」
当時の英語教師のマギル女史については、次のように書かれている。「女史は信仰心の深い、やさしい人で、子どもたちにとって英語の時間は一番楽しい時間だった。父母からも深く信頼され、学園の母とでもいいたいほどの人だった。悲惨ならい病患者を放置するに忍びず、その後草津に行き、らい病患者の友となり、後らい病に感染した」
学園の初期に在学され、のち一橋大学を出られた坪田龍夫氏は、私に下さった手紙の中で、学園在学当時を次のように回想しておられる。「その当時の学園は、恐らく関西で最もユニークな、個性尊重の自由主義的な教育で、ほのぼのとした温かい雰囲気の中で、生涯で最も楽しい思い出の小学校生活を送ることが出来ました。あの楽しい小学生活ほどの思い出は、その後の人生になかったように思われ、学園は心のふるさととして小生の心に生き続けております」
最初から学園は一人一人を伸ばす少数教育であったために、その経営は常に赤字で、専ら校主岸本氏個人の私財によって支えられたが、日本は太平洋戦争に突入して、岸本家も私学経営どころではなくなり、廃校を決意された。岸本家としては戦時中のやむを得ない処置だったと思う。
しかし父母たちは、この学園の教育を心から愛し、父母たちが経営者となって、他の場所に学園を存続させることを決議した。父母・教師・生徒は、しばらく中山寺などを借りて授業を行い、やがて22年10月、父母たちが力を合わせて現在の豊中市宮山町に校地を得て、そこに校舎を建て、一つ一つ校舎を建て増して行った。校名も箕面自由学園と改めた。そして中学をつくり、高校をつくり、最後に幼稚園をつくって、幼・小・中・高を持つ学校になったが、依然として私塾といってもよい少数教育だった。
私が幼稚園長・小学校長・中学校長・高等学校長を兼ねて、校長に就任した昭和43年の生徒数は、幼稚園104人、小学校141人、中学校50人、高校391人、計686人という小さな学校だった。
こういう小さな学校を経営し存続させて行くために、倉智氏、大野氏、槙野氏と続く理事長、財務理事の稲垣氏の苦心は非常なものだった。校長としての私にとっても、これは苦しい課題だった。
現在、在籍者数は約2倍の1300人となり、校舎も増築し、寄宿舎をつくり、大体育館も建設された。人間はどんなときも、苦しみつつも夢を抱いて、未来を望み、希望と勇気をもってがんばって行くよりほかはない。
小学校教育
昭和55年私は高齢になったので、学園の機構を改めて、私は学園長として全体をまとめる役となり、高校長・中学校長・幼稚園長はこれまでの主事を校長・園長として、それぞれの責任を負ってもらうことにしたが、小学校だけは、学園の都合で私が全責任を負わなければならないことになった。小学校は人間形成の上で非常に大事な時期なので、引き受けた以上は、私の教育人生の最後を小学生を対象としてがんばってみたいと決心した。
小学生は実にかわいい。私はこの学園にきて12年、幼稚園児・小学生・中学生・高校生のすべてに誕生日のお祝いの葉書を出し、お正月にも全部に賀状を出して、心の交流をはかっているが、小学生のよこす手紙や葉書は実にかわいい。いつか次のような手紙をくれた小学校の1年生があった。
こうちょうせんせい、おはがきありがとうございました。わたしはべんきょうがだいすきです。本をよむのも大すきです。1ばんとくいなのはさくぶんです。
このあいだプールにいったときのことをわたしはさくぶんにかきました。あのときはなきましたが、このごろはなかなくなりました。これからもがんばりますからみていてください。
わたしのなまえのすみれというのは、おとうさんもおかあさんも、しょくぶつがすきなので、すみれというなまえにしたそうです。すみれはすこしぐらい日のあたらないところでも、石がごろごろしているところでも、げんきよくはえていて、かわいい花をさかせて、みる人のこころをたのしませる花です。そうせきという人が「すみれほどな小さな人にうまれたし」と本のなかにかいているそうです。それでおとうさんとおかあさんが、わたしが、すみれの花みたいな人になってほしいとかんがえて、名まえをきめてくれました。わたしは大きくなってから、いい人になりたいとおもいます。せんせいもげんきでいつまでもいてください。
教育者として、80歳になってもなお明日への夢を抱いて生き得るのは幸せである。健康も悪くはない。学園は桜井駅の近くにあるが、私は毎朝運動のため乗り換え駅の石橋で電車を降りて、半時間歩いて登校する。就任以来ずっと続けているが、歩行のスピードは落ちていないようだから、まず健康なのであろう。
しかし、健康で働き得る残りの年月はどのくらいなのであろうか。
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より
昭和43年、私は箕面自由学園の校長の仕事を引き受けることになった。私の親しい人が学園の理事長であったため、再三の希望を断りきれなかったということもあるが、私に教育現場での仕事に対する郷愁のようなものがあったことと、箕面自由学園が幼稚園・小学校・中学校・高等学校を併せ持つ学園だったことに深く心をひかれたためであった。
箕面自由学園というのは大正15年4月、「箕面学園小学校」の名をもって私立小学校として発足した学校である。設立者は岸本汽船の社長岸本兼太郎氏、初代小学校長は神戸の諏訪山小学校の教頭から自由な理想教育を求めて私立小学校の校長となった小谷新太郎氏。朝日新聞杜から先年創刊された教育雑誌『のびのび』は、「新教育としての箕面自由学園」と題して創立当時の学園を紹介し、「小谷は知識注入主義をさけ、自発活動を重視、理科を自然科として一年からはじめた。共学、自学、自治の教育を追求した。『家なき幼稚園』の橋詰良一も協力した」と書いている。
橋詰氏は当時毎日新聞の部長を歴任し、「せみ郎」と号した文化人で、池田の呉服(くれは)神社の境内に「家なき幼稚園」(後に「自然幼稚園」と改称)を建て、季刊誌『愛と美』を出していて、学園の創立時に理事となって、学園の教育理念をつくり上げることについて、小谷校長の協力者だったようである。
後に第2代小学校長となった田村勝則氏は、回顧の文の中で当時の学園を想起しておられる。「型にはまった点とりとつめこみの教育から子どもを解放して、自然の子として、明るく、朗らかに成長させることを念願し、箕面の緑の丘に設立されたのがわが学園であった」「理科教育を重視して、子どもたちを自然に親しませ」「情操教育、全人教育を重んじ」「英語教育を重視して、国際人として、広く世界に舞台を求める態度を養うことにつとめた」「教育は人格と人格とのへだてなき交渉であることを思い、教師にその人を得て、学校が児童の幼き生命をはぐくむ苗床であり、これを培う壌土であるとの信念から、学校を温かく楽しき愛郷たらしめようとした」
当時の英語教師のマギル女史については、次のように書かれている。「女史は信仰心の深い、やさしい人で、子どもたちにとって英語の時間は一番楽しい時間だった。父母からも深く信頼され、学園の母とでもいいたいほどの人だった。悲惨ならい病患者を放置するに忍びず、その後草津に行き、らい病患者の友となり、後らい病に感染した」
学園の初期に在学され、のち一橋大学を出られた坪田龍夫氏は、私に下さった手紙の中で、学園在学当時を次のように回想しておられる。「その当時の学園は、恐らく関西で最もユニークな、個性尊重の自由主義的な教育で、ほのぼのとした温かい雰囲気の中で、生涯で最も楽しい思い出の小学校生活を送ることが出来ました。あの楽しい小学生活ほどの思い出は、その後の人生になかったように思われ、学園は心のふるさととして小生の心に生き続けております」
最初から学園は一人一人を伸ばす少数教育であったために、その経営は常に赤字で、専ら校主岸本氏個人の私財によって支えられたが、日本は太平洋戦争に突入して、岸本家も私学経営どころではなくなり、廃校を決意された。岸本家としては戦時中のやむを得ない処置だったと思う。
しかし父母たちは、この学園の教育を心から愛し、父母たちが経営者となって、他の場所に学園を存続させることを決議した。父母・教師・生徒は、しばらく中山寺などを借りて授業を行い、やがて22年10月、父母たちが力を合わせて現在の豊中市宮山町に校地を得て、そこに校舎を建て、一つ一つ校舎を建て増して行った。校名も箕面自由学園と改めた。そして中学をつくり、高校をつくり、最後に幼稚園をつくって、幼・小・中・高を持つ学校になったが、依然として私塾といってもよい少数教育だった。
私が幼稚園長・小学校長・中学校長・高等学校長を兼ねて、校長に就任した昭和43年の生徒数は、幼稚園104人、小学校141人、中学校50人、高校391人、計686人という小さな学校だった。
こういう小さな学校を経営し存続させて行くために、倉智氏、大野氏、槙野氏と続く理事長、財務理事の稲垣氏の苦心は非常なものだった。校長としての私にとっても、これは苦しい課題だった。
現在、在籍者数は約2倍の1300人となり、校舎も増築し、寄宿舎をつくり、大体育館も建設された。人間はどんなときも、苦しみつつも夢を抱いて、未来を望み、希望と勇気をもってがんばって行くよりほかはない。
小学校教育
昭和55年私は高齢になったので、学園の機構を改めて、私は学園長として全体をまとめる役となり、高校長・中学校長・幼稚園長はこれまでの主事を校長・園長として、それぞれの責任を負ってもらうことにしたが、小学校だけは、学園の都合で私が全責任を負わなければならないことになった。小学校は人間形成の上で非常に大事な時期なので、引き受けた以上は、私の教育人生の最後を小学生を対象としてがんばってみたいと決心した。
小学生は実にかわいい。私はこの学園にきて12年、幼稚園児・小学生・中学生・高校生のすべてに誕生日のお祝いの葉書を出し、お正月にも全部に賀状を出して、心の交流をはかっているが、小学生のよこす手紙や葉書は実にかわいい。いつか次のような手紙をくれた小学校の1年生があった。
こうちょうせんせい、おはがきありがとうございました。わたしはべんきょうがだいすきです。本をよむのも大すきです。1ばんとくいなのはさくぶんです。
このあいだプールにいったときのことをわたしはさくぶんにかきました。あのときはなきましたが、このごろはなかなくなりました。これからもがんばりますからみていてください。
わたしのなまえのすみれというのは、おとうさんもおかあさんも、しょくぶつがすきなので、すみれというなまえにしたそうです。すみれはすこしぐらい日のあたらないところでも、石がごろごろしているところでも、げんきよくはえていて、かわいい花をさかせて、みる人のこころをたのしませる花です。そうせきという人が「すみれほどな小さな人にうまれたし」と本のなかにかいているそうです。それでおとうさんとおかあさんが、わたしが、すみれの花みたいな人になってほしいとかんがえて、名まえをきめてくれました。わたしは大きくなってから、いい人になりたいとおもいます。せんせいもげんきでいつまでもいてください。
教育者として、80歳になってもなお明日への夢を抱いて生き得るのは幸せである。健康も悪くはない。学園は桜井駅の近くにあるが、私は毎朝運動のため乗り換え駅の石橋で電車を降りて、半時間歩いて登校する。就任以来ずっと続けているが、歩行のスピードは落ちていないようだから、まず健康なのであろう。
しかし、健康で働き得る残りの年月はどのくらいなのであろうか。
『人間の幸福と人間の教育』矢内 正一著(昭和59年9月30日創文社) より