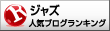私の中学時代の直接の恩師である甲斐淳吉先生が、矢内先生について書かれたものがありますので掲載させていただきます。美術教師の視点で、当時を伝えている文章です。
中学部図書館にも保管されている、中学部4回生の文集(平成4年刊)に「追想・矢内正一先生」として寄稿されたものです。
○ 矢内先生との出会い
昭和20年3月、就職の件で関西学院中学部(旧制)を訪ねることになった。公立校へ就職するつもりで、話をすすめていたが、気にいらず、思案していた頃、知りあいのT先生(中学部勤務)にすすめられてのことだった。
戦争末期のその頃は、勉強どころではなく、動員体制下であり、先生の数も応召や徴用の影響で、大変不足しており、どこの学校も困っていた。よい先生をというより、労働力がほしい時代だった。中学部でも、勤労動員で2年生以上は工場へいっており、1年生も間もなく動員された。本来の中学部校舎は既に予科練に接収されており、部長との面接は移転先の高商の校舎で行われた。
主に部長の畑歓三先生が心構えのようなことを話され、教頭の矢内先生からは履歴的なことの質問があり、10数分で面接は終ったように思う。退出するとき、矢内先生が、こういわれた。「私はどうも話しにくいとの評判なので、もし相談があれば、T先生を通じていってくださってもいいですよ」。初対面の矢内先生は、国民服にゲートル姿で、目こそ鋭かったが、非常にものやわらかで、話しにくい先生とは思わなかった。
古武士のような畑先生と、禅僧のような矢内先生、今までに出会ったことのないようなお2人の先生にお目にかかれ、不思議な感動を覚えた。お二方を通じ、関西学院にふれた思いがしたといってよい。
○矢内先生と文化祭
新制中学部は草創期(昭和22年-25年頃)を経て、昭和26年、第1回体育大会、翌々年の昭和28年には第1回の甲関戦(甲陽学院中学校との定期試合)が始まり、矢内先生の教育目標とされた、知、徳、体の三本柱は着々と成果をあげつつあった。
一方施設面でも別館が竣工し、理科、美術、音楽などの特別教室ができることにより、授業はもとより、文化部のクラブ活動もやりやすくなった。発表の場である文化祭は、昭和32年から企画されてはいたが小規模な学芸会程度のものだった。そのころ近隣各校でも文化祭が学校イベントとして盛んになり、それらの刺激もあって、中学部でも、出来れば体育大会なみの全校あげての行事にしたいものだと考え始めていた。
昭和36年、第5回文化祭から展示とステージをあわせた総合的な文化祭が生れることになった。30年も前の話で記憶もうすれているが、矢内先生が文化祭直後の感想としていわれた。「よくこれだけのことを生徒たちがやるなあ」と感嘆の言葉を何度か出された。生徒たちが自主的に活動してなしとげたことに対して先生はよほど感心されたのだと思う。
それと「ぼくにはわからん」と困ったときによくされる、あの頭に手をおかれる仕ぐさをされた。スーパーマンの矢内先生も、文化祭は未開拓の分野だったので、多分謙遜から出た言葉だったと思う。
先生は「ぼくは、オンチだ」ともよくいわれていたが、絵は造詣が深く、また生徒にも、いつもよい絵にふれさせたいと願っておられたようだ。各組の教室に名画の額を2枚ずつ掲げることを提案されたり、父兄の天羽義安氏(4回生、天羽均君の父上)をわずらわし、夏休みにパステル画の講習会を催した。この企画は夏休みの行事として10数年も続いたのは天羽先生のご奉仕と、矢内先生の熱意の賜物によるものだ。そのほか、あげていけばキリがないが、戦後のキズあともまだ生々しい日本に、うるおいをもたらしたマチス展を校外学習の形で観にいった懐かしい企画も、矢内先生から出たものと思う。
○ 矢内先生と年賀状
先生は、著書『人間の幸福と人間の教育』の中で「全校の生徒に対し、私が一人一人文通出来たことは、私と生徒とのつながりのもととなった。私は返事を出すのではなくて、私の方から先に、お正月と夏休みに一人一人の個性に合わせて激励のことばを書いて、全校の生徒に葉書を出した。」と記しておられることから、先生がこの賀状と、暑中見舞に力をそそいでおられたことがわかる。
先生は、いつのころからか、年賀状や暑中見舞状にイラストを加えられ、温かで、なごやかな雰囲気を上手に出しておられた。昭和34年から関西学院を退職される年の昭和40年まで、先生のアイディアで私が似顔絵をかいた時期があり、保存している方もあると思う。あの、おつむの曲線に苦労したのを懐かしく思い出す。
箕面自由学園へうつられてからは、ご自分で優しさと、雅趣に富んだ絵をかかれるようになった。ひと頃、墨絵を習っておられたのであのような、味わいのある絵ができたのではなかろうか。
○ 矢内先生を描く
昭和59年3月にお亡くなりになり、先生の肖像画制作のことが当然のことながらもちあがり、小林宏高中部長からその話の依頼があった。一年祭に間にあうようにとのことだったが、油絵の肖像画は初めてのことで、準備段階で手間どり、本格的にかき出したのは、年が明けてからのことだった。
制作中、体形のことや、服装のことでわからないことが生じると、奥様を訪ねたり、電話で教えていただいたりの苦労もあったが、期限いっぱいかかり、どうにか出来上がった。
肖像画は今、中学部の講堂に掲げられている。見る時によって、先生のお顔が、「厳しい目をしておられるときと、優しいお顔のときがある」と複数の先生から聞いた。作者としては、絵が既に一人歩きしていることになるので誠にありがたく思っている。まだ見ていない人は、一度、対面して、どんな顔をされるか確かめてほしい。

『矢内正一先生像』元関西学院中学部美術科教諭 甲斐淳吉作
中学部図書館にも保管されている、中学部4回生の文集(平成4年刊)に「追想・矢内正一先生」として寄稿されたものです。
○ 矢内先生との出会い
昭和20年3月、就職の件で関西学院中学部(旧制)を訪ねることになった。公立校へ就職するつもりで、話をすすめていたが、気にいらず、思案していた頃、知りあいのT先生(中学部勤務)にすすめられてのことだった。
戦争末期のその頃は、勉強どころではなく、動員体制下であり、先生の数も応召や徴用の影響で、大変不足しており、どこの学校も困っていた。よい先生をというより、労働力がほしい時代だった。中学部でも、勤労動員で2年生以上は工場へいっており、1年生も間もなく動員された。本来の中学部校舎は既に予科練に接収されており、部長との面接は移転先の高商の校舎で行われた。
主に部長の畑歓三先生が心構えのようなことを話され、教頭の矢内先生からは履歴的なことの質問があり、10数分で面接は終ったように思う。退出するとき、矢内先生が、こういわれた。「私はどうも話しにくいとの評判なので、もし相談があれば、T先生を通じていってくださってもいいですよ」。初対面の矢内先生は、国民服にゲートル姿で、目こそ鋭かったが、非常にものやわらかで、話しにくい先生とは思わなかった。
古武士のような畑先生と、禅僧のような矢内先生、今までに出会ったことのないようなお2人の先生にお目にかかれ、不思議な感動を覚えた。お二方を通じ、関西学院にふれた思いがしたといってよい。
○矢内先生と文化祭
新制中学部は草創期(昭和22年-25年頃)を経て、昭和26年、第1回体育大会、翌々年の昭和28年には第1回の甲関戦(甲陽学院中学校との定期試合)が始まり、矢内先生の教育目標とされた、知、徳、体の三本柱は着々と成果をあげつつあった。
一方施設面でも別館が竣工し、理科、美術、音楽などの特別教室ができることにより、授業はもとより、文化部のクラブ活動もやりやすくなった。発表の場である文化祭は、昭和32年から企画されてはいたが小規模な学芸会程度のものだった。そのころ近隣各校でも文化祭が学校イベントとして盛んになり、それらの刺激もあって、中学部でも、出来れば体育大会なみの全校あげての行事にしたいものだと考え始めていた。
昭和36年、第5回文化祭から展示とステージをあわせた総合的な文化祭が生れることになった。30年も前の話で記憶もうすれているが、矢内先生が文化祭直後の感想としていわれた。「よくこれだけのことを生徒たちがやるなあ」と感嘆の言葉を何度か出された。生徒たちが自主的に活動してなしとげたことに対して先生はよほど感心されたのだと思う。
それと「ぼくにはわからん」と困ったときによくされる、あの頭に手をおかれる仕ぐさをされた。スーパーマンの矢内先生も、文化祭は未開拓の分野だったので、多分謙遜から出た言葉だったと思う。
先生は「ぼくは、オンチだ」ともよくいわれていたが、絵は造詣が深く、また生徒にも、いつもよい絵にふれさせたいと願っておられたようだ。各組の教室に名画の額を2枚ずつ掲げることを提案されたり、父兄の天羽義安氏(4回生、天羽均君の父上)をわずらわし、夏休みにパステル画の講習会を催した。この企画は夏休みの行事として10数年も続いたのは天羽先生のご奉仕と、矢内先生の熱意の賜物によるものだ。そのほか、あげていけばキリがないが、戦後のキズあともまだ生々しい日本に、うるおいをもたらしたマチス展を校外学習の形で観にいった懐かしい企画も、矢内先生から出たものと思う。
○ 矢内先生と年賀状
先生は、著書『人間の幸福と人間の教育』の中で「全校の生徒に対し、私が一人一人文通出来たことは、私と生徒とのつながりのもととなった。私は返事を出すのではなくて、私の方から先に、お正月と夏休みに一人一人の個性に合わせて激励のことばを書いて、全校の生徒に葉書を出した。」と記しておられることから、先生がこの賀状と、暑中見舞に力をそそいでおられたことがわかる。
先生は、いつのころからか、年賀状や暑中見舞状にイラストを加えられ、温かで、なごやかな雰囲気を上手に出しておられた。昭和34年から関西学院を退職される年の昭和40年まで、先生のアイディアで私が似顔絵をかいた時期があり、保存している方もあると思う。あの、おつむの曲線に苦労したのを懐かしく思い出す。
箕面自由学園へうつられてからは、ご自分で優しさと、雅趣に富んだ絵をかかれるようになった。ひと頃、墨絵を習っておられたのであのような、味わいのある絵ができたのではなかろうか。
○ 矢内先生を描く
昭和59年3月にお亡くなりになり、先生の肖像画制作のことが当然のことながらもちあがり、小林宏高中部長からその話の依頼があった。一年祭に間にあうようにとのことだったが、油絵の肖像画は初めてのことで、準備段階で手間どり、本格的にかき出したのは、年が明けてからのことだった。
制作中、体形のことや、服装のことでわからないことが生じると、奥様を訪ねたり、電話で教えていただいたりの苦労もあったが、期限いっぱいかかり、どうにか出来上がった。
肖像画は今、中学部の講堂に掲げられている。見る時によって、先生のお顔が、「厳しい目をしておられるときと、優しいお顔のときがある」と複数の先生から聞いた。作者としては、絵が既に一人歩きしていることになるので誠にありがたく思っている。まだ見ていない人は、一度、対面して、どんな顔をされるか確かめてほしい。

『矢内正一先生像』元関西学院中学部美術科教諭 甲斐淳吉作