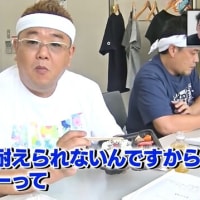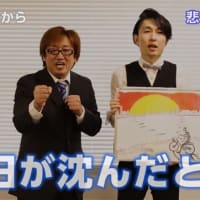2024年12月21日 土曜日は「冬至(とうじ)」。冬至は昼の時間が1年でもっとも短くなる日。
昼の時間が短いということは、日の出から日の入りの時間が短いということ。つまり、地球上を温める太陽が出場する時間が短いので、もちろん寒いことは寒い。冬至を過ぎれば少しずつ日が長くなっていきますが、日が長くなれば暖かくなるように思えるのですが、むしろ寒さはこれからが本番。
その理由は、「空気は暖めたり冷やしたりするのに時間がかかる」からです。
つまり、「熱しにくく、冷めにくい」ということ。逆に考えますと、酷暑の長い夏の空気がいつまでも地球表面を覆っていて、残暑が厳しいということを思えば納得できると考えます。
そのため、冬至はもっとも太陽の出場時間が短く、太陽高度も低く、太陽エネルギーが届きにくい日なのですが、いちばん寒い日は1月とか2月になってからやって来るのです。さらに日本は周りを海に囲まれていますよね。その海の水は空気よりもさらに暖まりにくく冷えにくいという、条件も重なっているからです。
さて、冬至の時期には古くから伝わる風習があります。
なんか、銭湯では「ゆず湯」のニュースが毎年のように報道されたりしますが、ゆず湯は江戸時代に銭湯が客寄せのために始め、冬至を「湯治」、ゆずを「融通が利く(体が丈夫になる)」という語呂合わせから始まったという説があります。また、ゆずは邪気が起こらないという考えもあったそうです。
とりあえず、バブのお風呂にでも入っておこうかと。

また、私が子どものころには「かぼちゃをあずきで煮込んだもの」を食べたこともありました。かぼちゃは夏の野菜ですが冬まで保存が可能。栄養価が高く、カロテンなどが豊富に含まれていて風邪予防にも役立つとのこと。ほかにも、運がつうじるように「ん」のつく食材を食べると縁起が良いとのこと。
とりあえず、カレーパンでも食べておこうかと。
さてさて、冬至の風習があるのは日本だけではありません。たとえば・・・、
英国
南部にある世界遺産「ストーンヘンジ」で冬至祭が行われます。ストーンヘンジは、巨大な石がつらなる古代遺跡で、夏至の時期には、ストーンヘンジの中心にある祭壇石と少し離れたヒールストーンという岩を結ぶ直線に朝日が昇り、冬至の時期は「ユール」といい、クリスマスシーズンに向けて真冬入りをお祝い
中国
中国では伝統的な行事で、冬節・交冬とも言う。二十四節気の中でも特に大切にされ、餃子を食べたり、白玉で作ったお団子のスイーツである「湯円(タンユェン)」を食べたりする。地域によっては「冬至は新年のごとし」ともいわれ、数日間祝うこともある
ブラジル
南半球ですから、日本が夏至のころです。冬至の時期を「フェスタジュニーナ」としてお祝いする。冬至祭だけでなく収穫祭や感謝祭としても祝われるため、全土で盛大なイベントが開かれる。男の子は麦わら帽子やひげ面姿、女の子はドレス姿など田舎暮らしをイメージした服装で踊り、トウモロコシを使った料理が定番
などなど。
これからが寒さ本番。
どうぞ、体調にご注意くださいませ。
昼の時間が短いということは、日の出から日の入りの時間が短いということ。つまり、地球上を温める太陽が出場する時間が短いので、もちろん寒いことは寒い。冬至を過ぎれば少しずつ日が長くなっていきますが、日が長くなれば暖かくなるように思えるのですが、むしろ寒さはこれからが本番。
その理由は、「空気は暖めたり冷やしたりするのに時間がかかる」からです。
つまり、「熱しにくく、冷めにくい」ということ。逆に考えますと、酷暑の長い夏の空気がいつまでも地球表面を覆っていて、残暑が厳しいということを思えば納得できると考えます。
そのため、冬至はもっとも太陽の出場時間が短く、太陽高度も低く、太陽エネルギーが届きにくい日なのですが、いちばん寒い日は1月とか2月になってからやって来るのです。さらに日本は周りを海に囲まれていますよね。その海の水は空気よりもさらに暖まりにくく冷えにくいという、条件も重なっているからです。
さて、冬至の時期には古くから伝わる風習があります。
なんか、銭湯では「ゆず湯」のニュースが毎年のように報道されたりしますが、ゆず湯は江戸時代に銭湯が客寄せのために始め、冬至を「湯治」、ゆずを「融通が利く(体が丈夫になる)」という語呂合わせから始まったという説があります。また、ゆずは邪気が起こらないという考えもあったそうです。
とりあえず、バブのお風呂にでも入っておこうかと。

また、私が子どものころには「かぼちゃをあずきで煮込んだもの」を食べたこともありました。かぼちゃは夏の野菜ですが冬まで保存が可能。栄養価が高く、カロテンなどが豊富に含まれていて風邪予防にも役立つとのこと。ほかにも、運がつうじるように「ん」のつく食材を食べると縁起が良いとのこと。
とりあえず、カレーパンでも食べておこうかと。
さてさて、冬至の風習があるのは日本だけではありません。たとえば・・・、
英国
南部にある世界遺産「ストーンヘンジ」で冬至祭が行われます。ストーンヘンジは、巨大な石がつらなる古代遺跡で、夏至の時期には、ストーンヘンジの中心にある祭壇石と少し離れたヒールストーンという岩を結ぶ直線に朝日が昇り、冬至の時期は「ユール」といい、クリスマスシーズンに向けて真冬入りをお祝い
中国
中国では伝統的な行事で、冬節・交冬とも言う。二十四節気の中でも特に大切にされ、餃子を食べたり、白玉で作ったお団子のスイーツである「湯円(タンユェン)」を食べたりする。地域によっては「冬至は新年のごとし」ともいわれ、数日間祝うこともある
ブラジル
南半球ですから、日本が夏至のころです。冬至の時期を「フェスタジュニーナ」としてお祝いする。冬至祭だけでなく収穫祭や感謝祭としても祝われるため、全土で盛大なイベントが開かれる。男の子は麦わら帽子やひげ面姿、女の子はドレス姿など田舎暮らしをイメージした服装で踊り、トウモロコシを使った料理が定番
などなど。
これからが寒さ本番。
どうぞ、体調にご注意くださいませ。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。