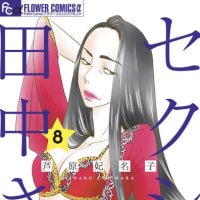『サピエンス全史 上 文明の構造と人類の幸福』(ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田 裕之 訳/河出書房新社)
オーディオブックで聞きました。イスラエルの歴史学者が語る人類史。著者はヘブライ大学歴史学部の終身雇用教授だそうです。
前回も書きましたが、人類は虚構を作れる・信じられる力によって想像上の概念で秩序(ヒエラルキー)を作って大規模な組織を回してきた、と言われるとすごく納得感がありました。例えば宗教、階級制度、会社、男女や人種の差別など。
もちろんそれはいい事ばかりではなく、むしろ一部の権力者たち(主に白人男性、宗教のトップ)の思い通りに世の中が作られてきたことを示しています。
つまり本書は、人類が辿ってきた傲慢な世界構築の行程を客観的に淡々と教えてくれるものでした。(すべてを鵜呑みにしないよう注意が必要と思う面もありましたけど)
個人的には女性がひどく差別されてきた歴史に目の前が暗くなりました。が、とくに耳をそばだてて聞いてしまったのは、生物学的に同性と性的関係を結ぶのは自然なことだが、想像上の社会的概念(ジェンター観)はそれを否定する、といった指摘を行うところ。第8章の「想像上のヒエラルキーと差別」の下記の部分(ほんの一部抜粋)です。※ギリシア人は単なる一例で、世界の大半の人々というニュアンスです。
現代のギリシア人の大半はまた、男らしさの不可欠な要素のひとつは女性だけに性的魅力を感じ、もっぱら異性とだけ性的関係を持つことだと考えてもいる。彼らはこれを、文化的偏見ではなく、生物学的現実だとみなしている。二人の異性間の関係は自然で、二人の同性間の関係は不自然だというのだ。
だが実際には、母なる自然は男性同士が性的に惹かれあっても気にしたりはしない。
この後、古代ギリシャを例に一部の文化では同性愛が認められていた/いることを解説していました。
この部分では、自分の興味関心、愛情の方向がどんなものに向こうとも、生き物としてはなんらおかしなことではない、と改めて肯定された気分でした。
引き続き下巻も聞きますよ。12時間弱かかるけど。
***