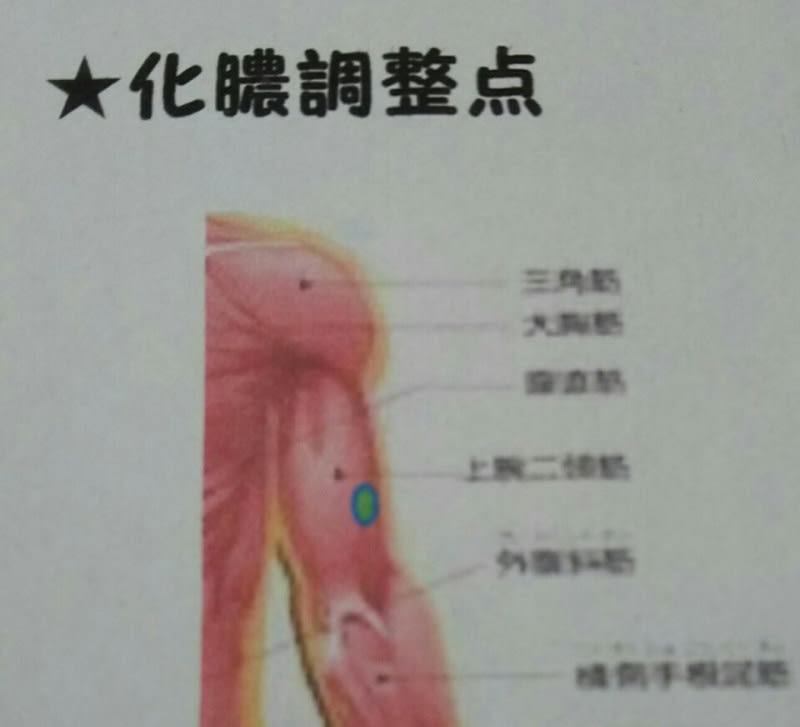痔というのは、
体の冷えから来る異常で
“体が乾いて、心臓が辛いんだよ”
というサインなのです
ですから痔になったときは、
薬に頼らず、心臓を守るために“痔”という症状が現れているのです
痔の薬を使って症状だけを抑えようとしないで
きちんと経過をさせていきましょう!
また体が乾くことで、便の出が悪くなったり、
食べ続けていると食べ物の入口(噴門/ふんもん)と
出口(幽門/ゆうもん)である肛門が切れたり、
荒れたりすると、切れ痔になります
体が乾きに注意しましょう!!
水分を小まめにとり、保水力を高めていきましょうね!
それには、輸(愉)氣(ゆき)を使う整体が有効です
家族の中で、
輸(愉)氣(ゆき)を使うことができる方がいらっしゃれば、ご自宅でケアしてもらうこともできます
◇◇◇
【やり方】
①右手で左足の小指の外側の指の中間(痛みが強い所)
部分を摘まむ
左手は、膝辺りに乗せて置く
片手で操法しないこと
必ず 支え手は体のどこかに、触れていること
↓
そうすると、“氣”の通りが良くなります
輸(愉)氣(ゆき)をしていると、
ジンジンした痛みが徐々に緩和してきます
一週間ほど毎日すると良いでしょう!!
②左の坐骨の下端に、ヌルっとした脂(あぶら)のよう
なものがついているので、それを捉えたらジっと
待つか、ゆっくりした動作で外側に弾く
*右側に“痔”のような痛みある人
⇊⇊
それは“痔”ではなく、
結核菌などを食べている“痔瘻(じろう)”です
整体では別物なので、
足の3趾4左趾間の冷えの急処と、左の骨盤閉めを
するといいでしょう!!
“痔を予防する”のであれば、
下半身の血行を良くし、適度な運動をする
腹八分目にすること
足湯(そくとう)を欠かさないことが大事です
また、肝心行氣をするのも良いでしょう
⇊
〈やり方〉ですが…
①あお向けになり、左手を肝臓(右下腹部)に、
手の平を当てます
手を当てるときは、優しく軽く当てましょう
②右手で心臓(左胸)に、手の平を当てます
③手を当てている部分に、行氣(輸氣)を入れながら、
ゆったりとした呼吸を行います
行氣と輸氣の違いですが、
行氣とは、自分で氣の巡りを良くすることで、
輸氣とは、自分以外の人にしてもらうことを指します
手を離すときは、ゆっくり外すと、
手を外した後も、手を当ててもらっている
感覚が残ります←これを残気(ざんき)といいます
手の平の温かさを感じながら行うと、
なお 良いでしょう
また、
高血圧の人が “痔” になることが多いです
体が乾くことで、血液が汚れる
新鮮な酸素を取り込めない
水分が足りないため、血が重くなる
↓
血が重くなると、血行不良を起こす
↓
それでも、
全身に血液を回す必要があるので、
心臓の圧を上げることで高い血圧を引き起こさなくてはならないので、これは必要不可欠な身体の作用となります
状態の良い血液ならば、
必要以上に圧力をかける必要がない
↑ ↑
これが分かっていないのに、病院で数値だけを診て
「高血圧だから、薬を飲みましょう」
と言われたから飲んでいる人が多いのでは?
それでは、
からだは良い方へ改善しないのです
身体の作用反応は意味があり、
薬で何かしらん弄(いじ)らなければならないような
不要なものはないのです
そこら辺が理解できると、より良い生活が営めるのではないでしょうか