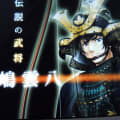岐阜県、美濃加茂市にある、美濃加茂
文化の森”美濃加茂市民ミュージアム”へ、
企画展”沙羅双樹の木の下で”~加茂の
涅槃図を中心に~を見に行きました。

このミュージアムは、戦国武将の書状が
数多く収蔵されていることで知られています。
以前、明智光秀の書状など見に行きました。
”惟任日向守”と書かれているのが、
光秀からの書状です。古文書読めないけれど
現代語訳も添えられていて、よくわかりました。
実は同じ美濃出身、信長に仕えた戦国武将、
もしかして、大嶋雲八の書状もないかな~?
…と思ったのですが、見当たらなかったです。
それはさておき、今回の涅槃図の展示では、
美濃加茂市と加茂郡のお寺に収蔵される
さまざまな涅槃図が公開されていました。

涅槃図というのは、お釈迦様が亡くなった時、
お釈迦様関係者はもちろん、多くの人々、
さまざまな動物が、死を嘆き悲しむ様子を
描いた絵画です。3月中旬の涅槃会の時に
お寺の本堂に掲げられる大きな軸物でした。
お釈迦様が中央に横たわっています。
それを取り囲むように、多くのお弟子さんや
菩薩さま、関係者一同が描かれています。
沙羅双樹や、満月の月…。上の方には、
お釈迦様のお母様、摩耶夫人が雲にのって
僧の導きで、急いでやって来る姿も…。
下の方には、動物の姿も描かれています。
涅槃図にはネコは描かれないといいますが、
案外、描かれているのですね~。
有名なところでは京都、東福寺の涅槃図…。
三毛猫らしきネコが丸くなっています。
その他の涅槃図でも、いくつか見つけました。
涅槃図を見たら、まず、ネコを捜してみます。
でも、それは置いておいて、これを機会に、
もっと涅槃図の本質にアプローチしたい…!

涅槃図を描くときに、製作上のお約束ごとが
あるのでしょうか、それとも涅槃図のお手本が
存在するのかしら…? どのお寺の涅槃図も
ぱっと見ると、同じような感じに思えました。
しかも、どれも相当古い時代のものなので、
退色、剥落していたり、輪郭がぼけています。
何が描いてあるのか、よくわからないものも…。
じっくり見ると、それぞれ違いがありました。
今回の展示では、その違いをわかり易く、
説明している文章が添えられていました。
学芸員さんが頑張っているようですね。
加茂地区のお寺の涅槃図が並んでいます。
あ~っ、川辺町の妙雲寺の涅槃図もある…!

妙雲寺は大嶋雲八の子孫であり、この地の
領主だった旗本大嶋家ゆかりのお寺です。
何度かゆかりのお寺めぐりで訪れました。
先代住職さんの時代には、”お会式”に
参加させていただいたことがあります。
”お会式”では、幼稚園のお飾りのような
桜の小枝の造花が配られていました。
日蓮さまの業績を讃え、”お会式”では
季節はずれの桜の小枝が配られます。
厄除けのお守りになると言われています。
さて、妙雲寺の涅槃図は室町時代初期の作。
お釈迦様が金色に輝くように描かれています。
人物の名前も添えられているのが特徴です。
妙雲寺にこのような文化財があったとは…!

あ~っ、富加の龍福寺の涅槃図もある…!
龍福寺も同じく雲八さんの子孫、旗本大嶋家
ゆかりのお寺の一つです。
ここも何度かゆかりのお寺めぐりで訪れました。
先代住職さんの時代に、お寺の歴史講座に
参加させていただいたことがあります。
その歴史講座のテーマは戦国時代、
加治田城の城主で、この龍福寺を建立した、
佐藤紀伊守でした。詳しい話を聞きました。
紀伊守、後に城主を退き、出家しています。

その佐藤紀伊守が、龍福寺を建立した時、
開祖だった和尚さんから、この涅槃図を
プレゼントされたそうです。
お釈迦様は赤い衣を着ています。
金泥で衣文線が描かれていました。
その他にも、龍門寺や大梅寺など
行ったことのあるお寺の涅槃図がいっぱい…。
知っているお寺があると親近感が湧きます。
こんな文化財が存在したのかと驚きました。

涅槃図の展示は一室のみでしたが、
中身がぎっしり詰まっている感じ…。
心に残る、素晴らしい展示でした。
ロビーも広々と解放感があります。
美濃加茂市民ミュージアムの帰りに、道の駅
”半布里の里とみか”に立ち寄りました。
久しぶりに行ってみると、レストラン&カフェは、
大幅にメニュー変更していました。

以前人気だった”ポーク味噌焼き重”が
姿を消していたのは残念でしたが、
デザートプレートが登場しています。
このデザートプレート、なかなかよかったです。