「見えたか?」
文観の座るのも待たずに後醍醐は訊いた。
「はい‥‥」
文観の鋭い眼光に自信のほどが表れている。
「それで、我の取るべき道とは?」
籠城を続けるのか、それとも還幸か。
「御還幸を致されるべしと‥‥」
口に出すまでもなく主上は既に心得ているとの確信がありながら、文観はそれでも厳かに奏上した。主上が求めているのは文観の意見ではない。主上の胸中にある思いを表に出す形式が必要となっており、言上げの装置としての文観の存在が重要なのである。
「ふむ。やはりそうか。それで、義貞めにはどうせよと?」
還幸となると問題は、義貞への対処となる。
「義貞には伏せて行うようにと‥‥」
義貞には内密に進めよと文観は言う。叡山の陣は広いが、天皇が動けば隠せるものではない。
「朕の輿を出せば、義貞にも知れようぞ」
逃げ落ちるのではないから、輿に乗って供奉を従え、堂々と京へ入らなければならない。そうなれば、いかに疎い義貞と雖も、やはり気づくだろう。
「それについても、良い手が‥‥」
文観は後醍醐の危惧を予想していたように、痩せた首を少しばかり前へ突き出した。
「ほう。良い手とは何じゃ?」
勿体ぶった文観の言い様には慣れているので、後醍醐は焦ることなく文観の次の言葉を促した。
「恒良(つねよし)親王を義貞につけて、越前の敦賀へ‥‥」
やはり敦賀か、と後醍醐は思ったが、それは口に出さなかった。
「ふむ。それだけで義貞が納得すると出たのか?」
皇子を大将につけて各地へ遣るのは常套手段となっている。皇子は人質であり、大将への信頼の証となる。天台へ入れた皇子は別としても、すでに義良(のりよし)親王を北畠親房父子に預けて陸奥へ送り、成良(なりよし)親王も一時は尊氏の弟直義(ただよし)が鎌倉へ連れて行っていた。
恒良を義貞に渡したとしても、それで義貞が後醍醐の還幸を認めるとは思えない。天皇のために戦うとの、義貞の面目が失われるのに違いはないのだから。
「そこで、この際、春宮(とうぐう)践祚の儀を‥‥」
文観の口元が僅かに歪んだ。
「ふーむ。その手を使うか」
後醍醐は鋭い眼差しを文観に向けたが、表情には微かな笑みが浮かんでいた。
これは、偽りの譲位をするという意味なのである。譲位をすれば、皇太子である春宮の恒良が天皇となる。そうすれば、義貞は天皇を奉じて北国へ向かう事になる。神器は常に偽物を用意してあるから、それを持たせれば義貞は信じるはずだ。随分と甘く見られた義貞であるが、負け戦ばかりで信用を失っていただけではなく、特に武士を下に見ようとする後醍醐の鬱屈した心情を、文観は心得ていたのだ。
「さらに、尊良(たかよし)親王も義貞につけます。春宮はまだお若いので、尊良殿に大事なお役目を任したく‥‥」
後醍醐には子を産ませた妃だけでも二十人おり、男女あわせて三十六人の子があった。恒良は義良・成良と共に寵妃廉子(れんし)の子であるが、その中の長子の恒良でさえ十三歳と、まだ一人前ではない。尊良は恒良の異腹の兄であり、本来なら一宮である尊良が皇太子となっているはずだが、後醍醐は廉子の子を世継ぎにと決めていた。尊良の母は歌人御子左為世(御子左家の二条為世)の娘為子で、簾子は阿野公廉(あのさねかど)の娘で洞院公賢(とういんきんかた)の養女である。
「尊良に役目とは、何事じゃ?」
「実は‥‥」
後醍醐と文観の密談は、叡山の夜が更けても長々と続いた。










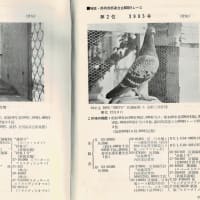

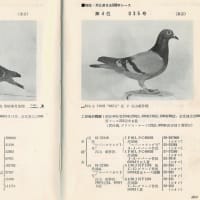







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます