これに対して幕府は翌年二月、今更変更できないと退けた。
天皇家が幕府の下にあるのは、天皇家が分裂して力が纏まらないからである。天皇家を一つにするためには、天皇家の財産を一つに集中しなければならない。しかし、幕府がそれを邪魔する‥‥。
このまま天皇の分立が続けば天皇家は幾つにも家系が細分され、両統が四統にも八統にもなる恐れがある。そうなれば小さな天皇家が幾つも出来てしまい、その間を皇位がたらい回しにされ、権威も何もかもが失われてしまい、そこらの公家でさえ天皇になる日が来てしまう。あるいは公家たちはそれを目論んで幕府に両統迭立を進言しているのかも知れない。幕府にしても、天皇家が小さく分立し、自然消滅するならばそれでいいのだ。
それを防ぐには、幕府を廃して、天皇自らが政権を握るしか手はない。後醍醐はそう考えた。
幕府の言いなりに皇位を両統で受け渡し、財産の分割縮小を放置して、天皇家を一公家並みに没落させてしまうのを、黙って見ている後醍醐ではなかった。
政治的な駆け引きは幕府に通じない。幕府にも、天皇家の事情に通じる公家どもが付いており、大覚寺統の後醍醐が動けば持明院統が反発して幕府に泣き付く。
後醍醐にしか出来ない事。それは、幕府を倒す事である。
幕府を倒すには、幕府に匹敵し、それを上回る武力が必要となる。
幸いにも、武士の中には幕府を嫌う者も多く、それらの武士は悪党と呼ばれて暴れていた。また、高利貸しとして銭儲けに走る僧兵や、乱暴狼藉を働く悪僧がおり、異形異類の者と呼ばれた賊もいた。彼らの政治的立場は一様ではなく、後醍醐天皇と一致する訳ではないが、幕府に反する点では共通する。
正規の武力を持ちえない後醍醐にとって、倒幕のための武力としては、そんな彼らを味方に引き寄せる他はない。後醍醐はこの不敵な目論見を推進した。
後醍醐の敵は幕府御家人であり、公式の武士である。それと共に、天皇家の権力を衰退させても幕府に庇護されて生き延びようとする公家貴族も、幕府と同じく後醍醐の敵である。また、そのような幕府や公家と結びついた僧侶も、やはり後醍醐の敵である。
つまり、後醍醐天皇が自らの権力を打ち立てようとする限り、既成の権力やイデオロギーと全面対決しなければならない状況にあった。それだけに、誰も後醍醐のような事をする者はいなかった。遅れてやって来た天皇であり、一家の惣領であった後醍醐だからこそ、全ての権威に反する事で天皇の権威を再興しようという、きわめてアナーキーな思想と行動をとれたのである。
後醍醐は、反幕府の武士たちに手を伸ばし、若い廷臣を登用し、僧界に息子を送り込み、密教の新たな教義を採用して、自らが法服姿で護摩を焚いて祈祷するといった、全方位攻撃を展開した。
後醍醐の父である後宇多法皇が死去した直後、後醍醐の倒幕計画が発覚し、六波羅の軍勢によって後醍醐方の武士が倒され、廷臣が拘置された。正中(一三二四)の変と言い、主上の御謀叛と呼ばれたものである。
この時に自刃して果てた武士は、無礼講と呼ばれる会合に、後醍醐の廷臣の誘いで参加していた。この無礼講が、後醍醐の倒幕計画の謀議の場であった。
花園院はこの無礼講を「結衆会合し乱遊す。或は衣冠を着せず、ほとんど裸形にして、飲茶の会ありと。これ、達士の風を学ぶか」と記している。参加者は武士も僧侶も衣冠を脱ぎ捨て、裸形の女たちに酌をとらせて、遊戯に耽るのである。まさに公天下を敵に廻した、闇の大王たらんとする後醍醐らしい振舞いである。










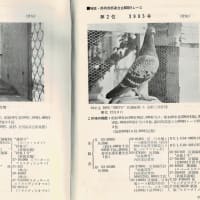
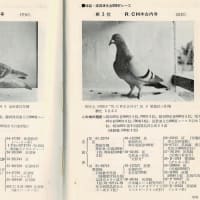
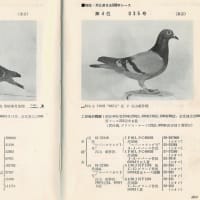
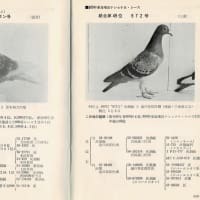
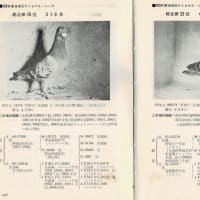
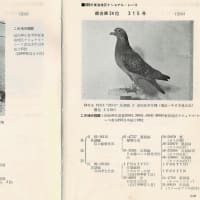
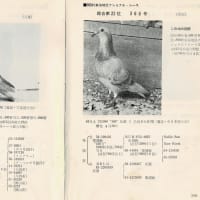
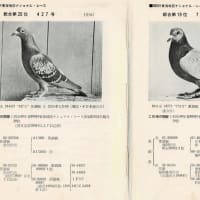
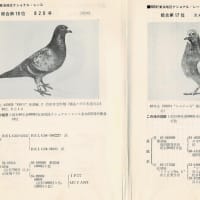
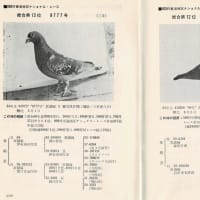
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます