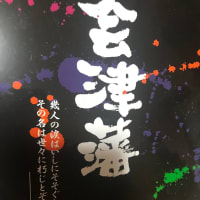かかる軍人ありきー伊藤圭一 著 さくら紀行より転載
昭和20年2月田辺大隊は銭塘江河口の
乍浦(チョンボ)に移駐した。
いよいよ米軍上陸の公算が濃くなり、
陣地構築を急ぐためである。
乍浦は海を控えているので、水産業が盛んだった。
台湾、下関あたりの漁船もくるし舟山列島を根拠地とする
魚師の水揚げ場でもある。城壁のある立派な街で、
倭寇に関連してその名を知られている。
田辺大隊の将兵は大隊長の方針とその効果を眼の当たりに見てきていたので、
中国人に接する態度が他部隊の兵隊とはまるで違っていた。
中国でいかに生きるべきかをよくわきまえていた。
ふつう警備交代があると、新しい部隊は住民となじみが薄いので、
とかく悶着を生じやすいが、そのような気配も全くなかった。
田辺大隊長は乍浦へ移駐すると同時に、徐と言う七十歳ほどの町長と会って、
街の経済状態を中心に懇談した。
その時、徐町長は「この街は今まで栄ていたのですが、
日本軍の駐留以来人口も半減しました」と嘆くように言った。
これは、駐留日本軍が商業を阻害した、と言うのではなく、
その頃援蒋物質の流入を抑えるために、軍は経済封鎖を行っていたのである。
従って、良港乍浦も全く寂れていたのである。
乍浦をいかに日本軍に協力させるか、
それによってこの地区での対米戦の帰趨が決まる。と、
考えた田辺大隊長は、ここでも独自の方針を行いたい旨を軍に要請した。
義烏における顕著な効果がわかっていただけに、
今では軍では田辺大隊に限りその施策を黙認している。
その第一の着手は、乍浦の開港宣言であった。
山地も海岸線も全て経済封鎖が行われている状況下に、乍浦のみは一切の制約を解いてしまったのである。乍浦の閉鎖を解いた翌日には、すでに船が入ってきたし
商人も流れ込んできた。中国商人の敏感さは驚くべきもので、数日のうちに乍浦は
往時の殷賑を取り戻し、活気が沸き立った。
そうなると中国警察が分署をおきたがって、交渉に来た。
利潤を吸い上げるうまみがあるからである。無論これは追い返した。
田辺大隊長は上海駐在時、中国警察の搾取の仕方をつぶさに見てきている。
中国警察に限らない、日本軍憲兵隊が軍隊をおきたいと言うのも拒んだし
特務機関の秘書の設置さえ断っている。
つまり規範の一切の責任は大隊長である田辺が負う、
と言う宣言のもとに、
絶対に不純な分子は入れなかったのである。
銀行は次々に支店を出し、乍浦の街は一軒の空き家もなくなった。
そうしたある日、大隊長の下へ高級主計がやってきて、
「水産物問屋の主人が買い入れの資金5百万元を返してくれと
言ってきているのですが、どう返事しますか」と相談した。
部隊の方針が順調に効果をあげている際にしても、五百万元と言うのは大金で、
部隊の保有金のほとんどにあたる。借り手は町の信用できる人物である。
高級主計は断ればせっかくうまくいっている町の人への、
心証を悪くするかもしれず、と言って引き受ければ不安である。
もし事故が生じたら軍法会議ものなのである。
借用期間は1週間と言う、申し出である。
「貸してやろう」と即座に大隊長は答えている。
「どうせ貸すなら無利子、無担保、無証文で貸してやれ。
万一の場合、責任は俺が取る」
主計は薄氷を踏む思いで金を貸した。
一週間目に金は滞りなく帰ってきた。
利子は受け取らなかった。
利子は無形のもので返されてきた。
日本軍部隊が、一商人に無利子無担保無証文で大金を貸した、と言う事実に対する、
中国人全般の畏敬と信頼感である。
この一事でガラリと、中国要人の日本軍への態度が変わっている。
ことに田辺大隊長に対する信用は絶対的なものとなった。
田辺大隊長は街を歩く時も、軍刀を捨てて、短い鞭一本を持って歩いた。
町で遊んでいる子供たちは、大隊長を見ると周りに群がってきて、
軍服にぶら下がったりする。
これは軍に好意を寄せる民心が子供にまで反映していることの、
何よりも証明だったのである。
戦争行為を停止し自ら武器を捨てれば、子供さえ飛びついてくるのである。
こういう事は一般の兵隊においても同じで、兵隊たちが町を歩くと
若い娘たちも明るい挨拶をしたし、
乍浦の町はのどかで平和な気分に満たされていた。
もちろん兵隊のための慰安所のようなものも町にはなかった。
上海から入手している情報で、刻々に敗勢に赴く日本の状態は読み取れたし、
大隊長としては慰安婦たちを敗戦の困苦に巻き込ませたくないと言う、
思いやりで帰国させたのであり、兵隊たちもそれを諒としたのである。
武力を全く行使しない、しかも極めて清潔の部隊が少なくとも、乍浦には
存在っていたのである。
兵隊たちが夜間、築城工事していると、住民が芋を蒸して持ってきてくれることが常例となっていた。命じたわけでも、頼んだわけでもなかった。
自らそこに湧き出てきた。互いの人情がそうさせたと、みるべきである。
そしてそれこそ、大隊長が赴任時に述べた、理想の実現であったと言える。
2021、5/29