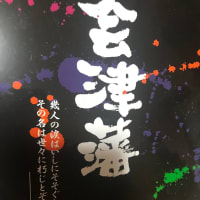さくら紀行 (9ー23) 記念すべき日、義烏の地にさくらを。
16日朝、桜植樹団一行は、
人民政府の先導車の後について陳先生のお母さんの故郷、
現在の大陳鎮(鎮は街の意味)へ向かった。
大陳町の町長に案内されて日中友好桜梅公園となる丘陵地を歩いて視察した。
狭い坂道を草を踏みながら登って行くと、
果樹園が右側に続いている。桃の木の一種だ。
立ち止まると、谷を挟んで左側に丘陵が広がっていた。
桜公園の青写真では、この谷に吊り橋がかけられている。
ここが二つの国の架け橋となる桃源郷、、、、いつの日か桜に包まれる丘、、、
歩きながら夢の中へ降りていく私の足元で、大陳の草が音を響かせてくれる。
大地の歌を、、、、。
汗を拭いながら丘を上ると大きな門構えのお寺に突き当たった。
お寺の門前には中国伝統の石像が立ち、中には極彩色の仏像があった。
鎮龍廟という大陳のお寺である。
私たちはお寺にお参りし、気持ちばかりの寄付を捧げて桜公園への夢を託した。
いつ集まってきたのか私たちの周りを、
街の人々や子供たちが笑顔で取り囲んで迎えてくれていた。
どこの国でも子供は好奇心の塊だ。
畠山さんの千羽鶴を御仏の上につるすと、ゾロゾロとちびっ子達が集まってきた。
目をクリクリさせて。
「この千羽鶴にお願いするとお願いしたことが叶うんですよ」と、
私たちは言いながらクリクリ目玉達の前で鶴を折った。
それが飛ぶように子供たちの手に渡り、
孫を抱いたおじいさんも来て、半分折りかけの鶴をにっこり持っていった。
ほんの少しの時間、こうして鶴の折り紙教室が御仏の前で開かれたのであった。
お寺の石段に腰を下ろして一緒に写真を撮ろうと呼びかける、
とみんな集まって仲良くカメラに収まった。
坂道を下って街の路地に入るとおばあさんが立っていた。
「ニーハオ」と声をかけると、
おばあさんは顔をくしゃくしゃにして笑いながら
私の手を両手できつくきつく握ってくれた。
この街は繊維工業が盛んで縫製工場が多く、人々の生活は豊かである。
私たち一行は大陳町で一番大きい縫製工場を見学した。
この工場は学校経営で、中学校の職業実習も行っている珍しい工場であった。
中国では政府の福祉資金が少ないので、
ここで得たお金は教師が福祉や学校改善、ボーナスに使うと言う。
1日の生産は7000着、従業員は300人、給料が良く
(一ヵ月440元以上、日本円で約8000円、ちなみに1人1ヵ月の生活費は6000円である)
若い女性はここへ勤めたがるが、腕の良いものしか入れないそうである。
素朴で優しい副町長さんに見送られて、大陳を後に再び義烏へ。
義烏市内にも戻ると、
私たちは桜の苗木を植えるためワクワクしながら公園へと急いだ。
広い公園の一角では耕された地が桜の到着を首を長くして待っていた。
日本からとうとう義烏の大地にやってきた桜の三年若木達、
みずみずしく背丈を切り揃えられた苗木達、
そこから新芽の出る日を祈って、平和を祈って、
私たちと義烏の人たちは苗木を植えた。
ソメイヨシノ、カンヒザクラ、、、、
東京小森氏はじめ中国に来られなかった有志の方々の桜の苗木に、
一つ一つ丁寧に名札を結んで感謝しながら苗木を抱いて、
それぞれの方々の思いをさくらに伝えた。
植え終わると大地に根付くように、
山口県の村田さんから託されたピンクの紙吹雪をみんなで一握りずつ持って、
一斉に桜の苗木の上に降らせ続けた。
桜吹雪の中でいつのひか再会できるように、、、、、
「桜の若木を大陳の丘陵に移して、大きくなり花をつけたら、
その下でまた酒宴を持ちましょう」
桜に心を託して、その後、前川先生の思い出の地、田辺部隊駐屯地後を訪ね、
見送りの方々との別れを惜しみながら私たち一行は車中の人となり、
義烏を後にした。
それにしても前川先生の記憶は鮮明すぎるほど鮮明であった。
街の中の大きな池のような湖とその側に聳える高い塔、
その横を入ったところがその場所であった。
駐屯地跡には住宅が建ち、広場では放し飼いの茶色い鶏が一羽餌をつついていた。
思い出の場所に絶たれ、胸に去来したものは何であったろう。
私等の知る由もない深淵に渦巻く押さえ方感情であったろうか、、、。
今私は、旅の終わりに黄山で詠まれた漢詩に
ほっと、心を、和ませている。
(季刊 ふるさと紀行 平成5年冬の特別寄稿)
2021 5/12