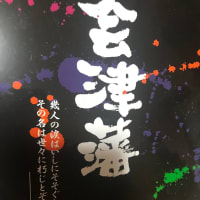二本松少年隊は白虎隊の悲劇の陰であまり知られてないのですが戊辰戦争の一番の激戦地であり福島では戊辰戦争といえば、二本松城周辺の戦いを言います。
資料は極端に少ないと言われています。
東北の戊辰戦争
1868年5月3日に仙台、米沢、二本松など25藩が奧羽列藩同盟、6日越後が加わり奥羽越列藩同盟に発展、倒幕派との激しい戦いを繰り広げた末7月29日に二本松城落城、その後会津戦争となり9月22日降伏し、翌日、会津城が開城。
二本松の戦いに於いて藩の兵力は仙台などの応援藩を含めてもわずかに約1000人それに対し薩摩長州土佐などの政府は約7000人徹底交戦の末、落城、落城敗戦は誰もが予想し得た事でしたが奥羽越列藩同盟の信義のために貫いた二本松藩の守信玉砕戦は、他藩には見られない壮絶な最期でした。
明治維新夜明け前に、 愛する郷土そして家族を守るため、
激戦の末に可憐な花を散らし、義に殉じた少年藩士を弔う参詣者の献花と香煙は
今なおその悲劇を伝えています。

1868年5月1日、西軍が白河城を占拠、二本松藩兵の大半が白河城攻防に従事している間に、棚倉城落城、守山藩降伏、平城落城、このような戦況の中、同盟の三春藩による西軍への寝返り、板垣退助の三春藩無血入城、噂された三春藩の背信でした。
二本松領に急迫した西軍に対し二本松城は空虚同然少年たち、そして一度隠居した老人までも出陣する原因ともなりました。
少年たちの出陣に対しそれぞれの家庭でのドラマが語り伝えられています。
徳田、13才、、母、秀は、出陣の門出に母の言うべきことではないが当主が不在なので…と戦陣での心得を諭した後に、徳田家の家名を汚すことのないよう、また亡くなった祖父や父の分まで忠勤を励むようにと、激励したと後に語ったといいます。
上崎、、16才、、一時は大喜びをしていたが時が経つにつれて物思いに沈むようになり、これを見た母はその訳を問い出したところ、「恥ずかしくない刀を持って戦いたい」との事でした。上崎家には実戦用の両刀がなかったのです。
母はすぐに実家に駆けつけて、相州ものを調達しました。7月27日の朝出陣時、母は祖母とともに見送り「行って来いよ」といつものように声をかけると「行ってこいよではないでしょう。今日は行けでいいのです」と答え、玄関を出てにっこり微笑みちょっと頭を下げると元気に駆け足気味に立ち去ったといいます。
母は「言の葉の、耳に残るや、今朝の秋」と詠んでいます。
久保富三郎、12才、、、母に何度も出陣を願ったものの歳が満たないために許されませんでした。それでもねだるように出陣を求めたため、母は困り果て、「幼いから間近に砲声でも聞いたら恐ろしくなって帰ってくるだろう」と考え下男と一緒に行くことを条件に許しました。富三郎は下男の手を引くようにして大壇口に向かって行ったと言います。
成田才次郎14才、、、父から敵を見たら、切ってはならぬ、突け、ただ一筋に突け、わかったか。分かったら行け、突くのだぞ」と、諭され出陣したといいます。
この突きは初代藩主、丹羽の二本松藩伝統の剣法です。

(二本松城(霞ヶ城として菊人形祭りが有名です)
二本松戊辰少年隊記によると急ごしらえの出陣服で出陣していますが、おそらく多くの家庭では母が徹夜で、父や姉の着物などを少年の体に合わせて縫い、何とか形のみを整えただけのものであり、少年たちの服装はまちまちでしたまた。
体が小さいため刀を佐々木小次郎のように
斜めに背負った少年や、
刀を抜くときに他の少年に抜いてもらったり、
あるいは2人が向き合い腰をおって互いに相手の刀を抜いたと、
生存した少年達が伝えています。
大壇口への出陣
7月26日、出陣許可が伝えられると、木村銃太郎門下の少年たちは北条谷の道場に集合、その時は16人の門下生だけだったと言われています。
28日朝、少年たちは箕輪門前の千人溜めに集合し、
ライフル砲1挺と各々の元込め小銃と、軍用金1両3分が支給され大壇口に向けて出陣しました。
まもなく引き上げの命令が下り、松坂門で休憩していたところ午後2時ごろに、再び出陣の命令が下り、喜び勇んで駆け足で
新丁の坂を下っため大砲を積んだ第八車に勢いがついて、
桑畑に突っ込んでしまった、と言うエピソードが伝えられています。
午後7時ごろに大壇口に着陣し、陣立てとして枠木を打ち込み横に丸太を渡しこれに畳2枚ずつ並列し、縄で括り付け終了したのが午後8時ごろでした。その日は警戒のままに過ぎました。
少年隊62人中、木村門下生16人を含む25人が、隊長、副隊長の指揮のもと、大壇口を守り、他の37人はそれぞれの部隊に配属され、7月29日の激戦を迎えたのです。
大壇口の激戦
7月29日の朝は霧が深かったと伝えられています。二本松兵と板垣退助隊との最初の接触があったのは午前6時半ごろで、
大壇口陣地では、はるか杉田方面から銃声が聞こえ、
しばらくして供中方面からも銃声が聞こえました。
8時ごろになり大壇口前方の尼子台に陣していた二本松隊に対して西軍の砲撃が開始されます。
その間に板垣退助隊は迂回して西法寺町の集落に入り、出たところで砲列を敷き、歩兵は散開し大壇口に向かって戦闘開始、
8時半ごろと言われています。
西軍は組み易しと見たのか隊列を組んでままに少年たちの眼下に姿を現しました。
「先生まだですか、」少年たちは打ちたくて気がはやります。「命令を待て、もっと敵を引きつけてからだ」
大砲には木村門下生の大砲手、岡田篤次郎と成田虎次の二人が付き、そのそばには銃太郎が毅然として立ち、他の少年たちは陣立てに身を潜め銃を構えて敵をにらみます。
息詰まるような時が刻々と過ぎ、銃太郎の命令が下り、篤次郎と虎次の精魂込めた直撃弾は、三発とも敵の頭上で爆発、
敵は慌てて散り、左右の山林に身を隠し、大砲と銃を雨あられと撃ってきました。
一方民家に潜んだ敵を砲撃したところ見事に命中し、民家51軒を貫いたといいます。この砲撃の確実さには西軍も驚いたほどで、一弾一弾よく目標に命中したと、後に西軍の隊長が語っています。
しかし多勢に無勢、新式銃を使い、統制ある巧みな、近代戦法の西軍体制を整え徐々に少年たちを責め立ててきます。。、
「先生、午之助がやられました」遠くで叫ぶ声がしました。
少年隊最初の戦死者である。
少年たちは始めて、戦争と言う実体験を、間近に見せつけられたのでした。仲間の命を奪われた少年たちは、弔い戦と奮起し激しく向かい撃ちました。
こうした中、ついに隊長が敵弾で左腕を打ち抜かれ、重傷を負い、もはやこれまでと退却を決断し、自ら集合の太鼓を打ち鳴らします。敵は目前に迫り危険な状況になった時、追い打ちをかけるように敵弾に腰を撃ち抜かれ、その場に倒れました。
「この重傷では、到底お城には帰れぬ、我が首を取れ」と副隊長に願います。
少年たちは銃太郎を励まし一緒に退却するよう懇願しましたが「押し問答する時ではない早く切れ」と促し、副隊長は心を決め銃太郎の首を切り落としました。
その瞬間少年たちは一斉に号泣したといいます。
そして少年たちは副隊長の指示に従い泣きながらも銃太郎の屍を急いで埋め、首を下げ持ち、引き上げることになりました。
隊長・副隊長の指揮のもと、わずか25人の少年で交戦した大壇口の戦いは幕を閉じました。午前10時ごろでした。
敵将、野津七次の回顧談
(後の元帥陸軍大将の頭)
兵数不詳の敵兵は、砲列を布いて、我が軍を激撃するのであった。わが軍は早速これに応戦したが、敵は地所を利用して、
おまけに射撃がすこぶる正確で一時わが軍は、全く前進を阻害された。わが軍は正面攻撃では奏功せざることを覚り、軍を迂回させて敵の両面を脅威し、辛うじて撃退することを得たが、
おそらく戊辰戦争中、第一の激戦であったろう。
〜打つ人も 打たれる人も 哀れなり
共にみくにの 民と思えば〜
戊辰戦争の悲壮さをうたった野津の詠歌です。
また、大壇口には、野津に勧められて1930年(昭和5年)
当地を訪れた陸軍中将の木越安綱の詠んだ歌碑が建立されています。
〜色かへぬ 松間の桜 散りぬとも
香りは千代に 残りけるかな〜
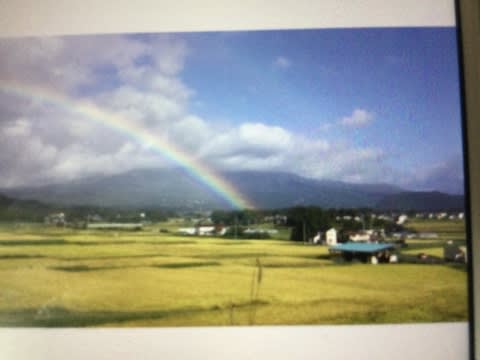
二本松少年隊の哀歌にうたわれる安達太良山
少年隊士62人のうち壮絶な戦死を遂げた少年は、
14人を数えます。
・13才、、、大壇口で敵弾により顔面を負傷、その後郭内まで
引き上げ、夕暮れごろに西軍に切り掛かり、二ノ丁で戦死し
ました。
・14才 成田、、重症の身で城に向かう途中西軍と出会い、一瞬の油断を見て、敵将の平井を突き殺した後、その場で絶命、出陣に際し父の教えをけなげにも守った末の戦士でした。
・17才、、、師の朝可とともに重傷を負いながら師をを背負い退去の途中、大手門前で師の絶命を知り屍を手で掘り埋めたといいます。その後久保丁坂の中ほどで土佐兵と遭遇したが精魂つき果てたためか介錯を頼み、その場で絶命。
師を埋める時素手で掘ったため生爪が剥がれていたといいます。
武谷剛介の回顧談
藩のため戦争に出て戦う事は武士の子として当然のことであって、特に語るべきことではない。恐ろしいとは思わなかった。出陣の前夜などは今の子供の修学旅行の前夜のようなはしゃぎようだった。
資料参照
2021 10/8