昭和44年2月27日、大分県九重(ここのえ)町の八丁原(はっちょうばる)。標高1100メートルのこの地は日中の最高気温さえ氷点下10度を下回った。そんな吐息も凍るほどの九重(くじゅう)連山に九州電力や関係会社の社員らの「万歳」がこだました。
地下1087メートルまで掘り進んだ直径20センチのパイプから大量の蒸気が噴き出したからだ。この蒸気ならば発電タービンを回すことができる。地熱発電所建設に向け、現地の九電調査所に配属されていた松本正氏(69)は当時の様子を克明に憶えている。
「轟音とともにすさまじい勢いで蒸気が噴き出しました。辺りは寒いのにものすごい熱気です。誰も彼もが『出たぞ!』と叫んでいました。ああっ、これまでの苦労が報われた。心からそう思いました…」
だが、喜びもつかの間。数分後、蒸気とともにバリバリと激しい音をたてながら人の頭ほどの岩石が次々にパイプから噴き出した。あわてて避難する作業員たち。その音は2キロ離れた調査所事務所でも聞こえた。
しばらくするとパイプが詰まり岩石の噴出は止まったが、同時に蒸気も噴き出なくなった。「やり直しだ…」。松本氏らは重い足取りで掘削現場に向かった。
大岳地熱発電所
地球内部に蓄えられたエネルギーを使う地熱発電の歴史は大正時代に遡る。
第1次世界大戦中の大正7(1918)年、海軍が日本中の地熱調査に着手し、大分・別府温泉に井戸を試掘。この井戸を使って7年後には出力1・12キロワットの発電が行われた。
だが、当時の技術で蒸気が噴出する場所を掘り当てるのは並大抵のことではなかった。地熱発電の開発はほどなく断絶した。
地熱開発が再開したのは戦後だった。昭和23年、戦後復興に必要な電源開発の一環として、商工省(現経済産業省)工業技術院に地熱開発審議会が設置され、日本各地で地質調査を開始した。火山や温泉が多い九州は、当初から有望な地とみられていた。
26年に発足した九州電力が、地質調査を引き継ぎ、38年に大分市の西約40キロ、大分県九重町大岳地区で本格的な井戸を掘ったところ、地下350~500メートル地点で蒸気を掘り当てた。
42年、電力会社が運営するわが国初の「大岳地熱発電所」が運転を開始した。このとき、日本地熱調査会の会長だった松永安左ェ門はこう会報に記した。
「良質、低廉、豊富な地熱エネルギーをもってすれば、わが国経済力の発展は期してまつべきものがあるであろう。わが国に優秀な(蒸気)生産井1000本の開発、これは私の現実の夢である」
とはいえ、実験の色合いが強かった大岳発電所は出力1万2500キロワットに過ぎず敷地も狭い。実用発電所を作るには別の場所を探す必要があった。そこで九電が目を付けたのが、大岳の南2キロの八丁原だった。
掘れども掘れども…
昭和41年、八丁原での試掘作業が始まった。
「大岳より少し深く掘れば蒸気は噴き出すだろう」
多くの技師はこう考えたが、目算は崩れた。500、600、700メートル-。どれだけ深く掘っても地中の温度は上昇しない。蒸気が詰まった層がないということだった。
当時の掘削能力は1日10メートル程度。深度800メートルに達したところで、理科の実験で使うような温度計をひもに結び、パイプ内に降ろして計測したが、地中温度は上がらない。
「本当にここで掘り続けて大丈夫か?」
多くの技師たちが疑心暗鬼となったが、地熱発電実用化に熱心だった本社火力部の吉田勝亮氏(後の常務)はこう厳命した。
「とにかく掘れるところまで掘れ!」
深度1千メートル超。掘削機の限界が近づいたところで、ようやく蒸気が噴き出した。蒸気と一緒に噴き出す岩石はセメントを流し込むことで抑えることができることも分かった。
九電は出力5万キロワットの「八丁原地熱発電所」の建設を決定。43年から計6本の井戸を掘り、うち5本から発電に使える蒸気が出た。後に八丁原地熱発電所所長も務めた松本氏は当時をこう振り返る。
「奥深い山の中。道路は砂利道で大雨の度に砂利が流れ出てました。冬は寒さも厳しく、胸まで積もった雪をかき分けつつ事務所から掘削現場まで歩くこともありました」
「オール九州」で夢実現
だが、ここからも八丁原計画は苦難の連続だった。
近隣の温泉旅館から「掘削で温泉が枯れたらどうしてくれるんだ」と抗議が殺到。九電は地下から噴き出し発電に使わなかった温水を、地元に無料供給することで合意を取り付けたが、この温水にヒ素が含まれていることが分かった。
九電は八丁原計画をいったん中断せざるを得なかった。結局、わき出る温水を全て地中に還元する方式に切り替え、地元には真水を沸かして供給することでヒ素問題を解決した。
ようやく八丁原に蒸気タービンと発電機を設置したが、今度は蒸気が足りない。中断中に井戸の最深部が崩れてしまったのだ。52年6月に発電所は稼働し始めたが、計画出力5万キロワットの半分に満たない2万3千キロワットしか発電できなかった。
この出力ではコストに見合わない。焦った九電は53年、総合研究所が担ってきた調査・掘削を、大勢の技師が居る火力部に移した。
火力部地熱課の初代課長、木下保美氏(80)は、「地熱発電の鬼」と化した吉田氏にこう耳打ちされた。
「多少の金のことは目をつぶる。とにかく早く5万キロワットにしてくれ…」
木下氏は、地質、火山、探査-など地熱に関するあらゆる本をむさぼるように読み、発電所に応用した。
もちろん九電の独り舞台ではない。試掘調査は九州大が請負い、蒸気と温水の分離や、発電効率を高める技術は三菱重工業長崎造船所が担った。
長崎造船所で地熱発電を主導した相川賢太郎氏も地熱の魅力に取り憑かれた一人。建設現場に頻繁に泊まり込み、タービンが不調と聞けば、長崎からタクシーを飛ばして駆けつけた。そんな技術者魂を買われてか、相川氏はその後、長崎造船所長を経て三菱重工業社長にまで昇り詰める。
こうして「オール九州」で蒸気井戸を増やした結果、昭和55年4月、当初計画を上回る出力5万5千キロワットの八丁原1号機が運転を開始。平成2年には同じ出力の2号機も完成した。わが国最大の地熱発電所であることは今も変わりない。
木下氏はこう語った。
「八丁原では何度も『もう無理だ』という難関にぶつかったけど、そのころの九電社内は『地熱をやるぞ』という気持ちがみなぎっていましてね。経営陣から若手技師まで『ここでやめたらもう地熱に未来はない』と考え、踏ん張ったことが現在の地熱技術に繋がっています。原発も同じです。一度、やめてしまえば技術は失われる。後から必要になっても取り戻すことは大変難しい」
◇
第4部では、電気普及の黎明期から九州電力の軌跡を追った。日本初のアーチ式ダム、米国製の最新鋭火力発電所、初の純国産原発-。長崎の爆心地で送電再開に命をかけた技師もいた。どの時代を切り取っても、そこには使命感あふれるプロの姿があった。平成23年の東京電力福島第1原発事故を受け、激しいバッシングに遭い、九電社員はすっかり萎縮してしまったかにみえる。今こそ社内に脈々と受け継がれたはずのフロンティア精神を取り戻すべきではないのか。=この連載は石橋文登、小路克明、田中一世、大森貴弘が担当しました。














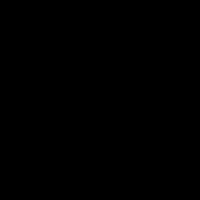
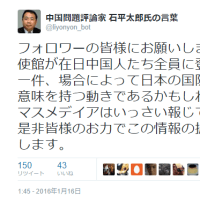

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます