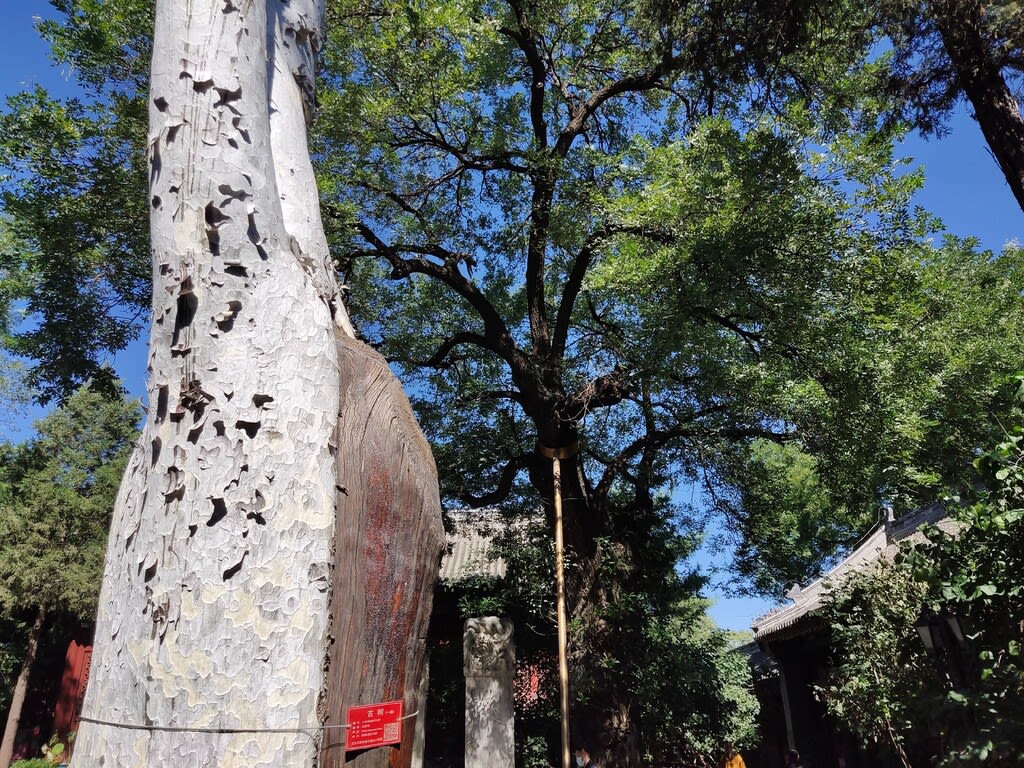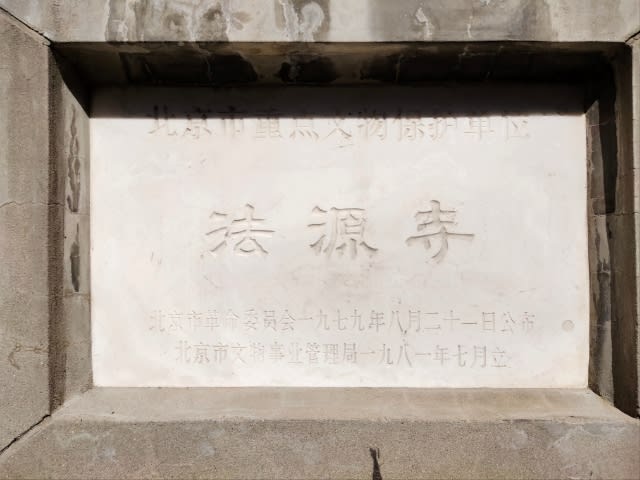流山に行ってみました。
流山にはかつて、糧秣廠とよばれた陸軍の施設がありました。軍馬の飼料となる干し草を圧搾梱包して保管し、国内外の各部隊や宮内庁、警視庁などに供給する役目を担いました。

ここにあったのは糧秣廠の本拠地ではなく、倉庫(後に出張所に昇格)でした。
今はイトーヨーカドーやビバホーム、流山南高校がある場所です。

流山は江戸川の水運と流鉄線という鉄路に恵まれ、飼料の原料となるわらや干し草の産地にも近かったので、この地が選ばれたようです。
ここから江戸川の堤防まで200メートルほど、流鉄線の線路には隣接しています。
施設の痕跡を探るべく、周囲を歩いて一周してみましたが、痕跡らしきものはどこにも残っていません。
残っているのは当時から施設の一角にあった千草稲荷という小さな祠だけでした。

この神社は大正14年(1925年)に錦糸町から施設が移転してきた直後に分祀してきたものだそうです。
戦勝を願って働く工員たちの心の拠り所として信仰を集めたのでしょう。

面積は20坪ほどでしょうか。県道側からは見落としそうになるほど小さい神社です。
この台座には、陸軍糧秣本廠流山倉庫職員一同、大正15年7月1日とあります。

建立時に作られたものだと思われます。
この灯篭には昭和11年6月1日とあります。

この時点ではまだ出張所ではなく倉庫です。
こちらの手水鉢の裏側には、陸軍糧秣本廠流山出張所所員一同、昭和17年8月と刻まれています。


つまり、この頃から出張所に昇格したと。組織としての機能を持ったということだと思われます。
神社の裏側(県道側)にはこんな掲示板が掲げられ、市民にひっそりと歴史を伝えています。

元所長の瀧上浦治郎さんが執筆したようです。
以下、起こしてみました。
元陸軍糧秣本廠流山出張所跡碑
元陸軍糧秣本廠流山出張所跡碑について
当所は元陸軍馬糧倉庫として、東京本所錦糸堀の旧津軽藩屋敷跡にあったが周辺の人家が増加して火災の危険を生じたため流山に移り、大正十四年七月一日開庁、敷地三五二六〇坪建物七五九七坪(倉庫二〇棟、事務所、工場等一五棟)であった。業務は軍馬用大麦、燕麦、高粱、牧草は本廠の指示により、また干草、ワラは関東地方各都県より買入れて貯蔵し、干草は圧搾工場にて四〇瓩梱包に精撰加工し、近衛第一師団下各部隊並びに宮内省、警視庁に補給した。また所管下の習志野、駒沢支庫がこれを補足した。なお江戸川岸に架空輸送機があって舟運の荷役に用いられ、ガラガラと称され名物であった。
流山がこの基地に選定された主因は、干草、ワラの主産地が千葉、茨城県下でその収集、補給に水陸両運の便が得られたためである。かくて流山は特徴ある有名な町となった。
やがて終戦となり、進駐軍に英和文リストを提出し接収された。その後構内及び職員共に運輸省東京鉄道局所管となり、特殊物資(進駐軍返還の各軍用品)を受け入れて整理、出納する鉄道用品庫流山支庫として6カ年余つづいたが、国鉄改革のため、昭和二十七年三月五日閉止され大蔵省を経て野田醤油並びに東邦酒類両会社と流山町に払下げられ、現在の状態となった。
回顧すれば、大戦中は敵機の攻撃目標となり、爆弾も投下され、且つ東京糧秣本廠が空襲のため全焼するや、その業務の一部が当所に加重されるなど重大任務の遂行と防空対策とで職員は殆ど不眠不休の苦労を重ねた。さらに終戦直後は軍廃止のため全員失職の運命に遭い、物資の欠乏、生活の困窮は実に甚しく、またともすれば流言飛語に迷わされがちな不安の中にあって、複雑な引継ぎと残務処理を一同一糸乱れず誠実に無事に完遂した。その労苦多としたい。
右の実情に鑑み、ここに本碑を建立して、史跡の標識とし、後代の参考に供する次第である。
昭和五十五年八月十五日
元陸軍糧秣本廠流山出張所長
記念碑建設委員長 瀧上浦治郎