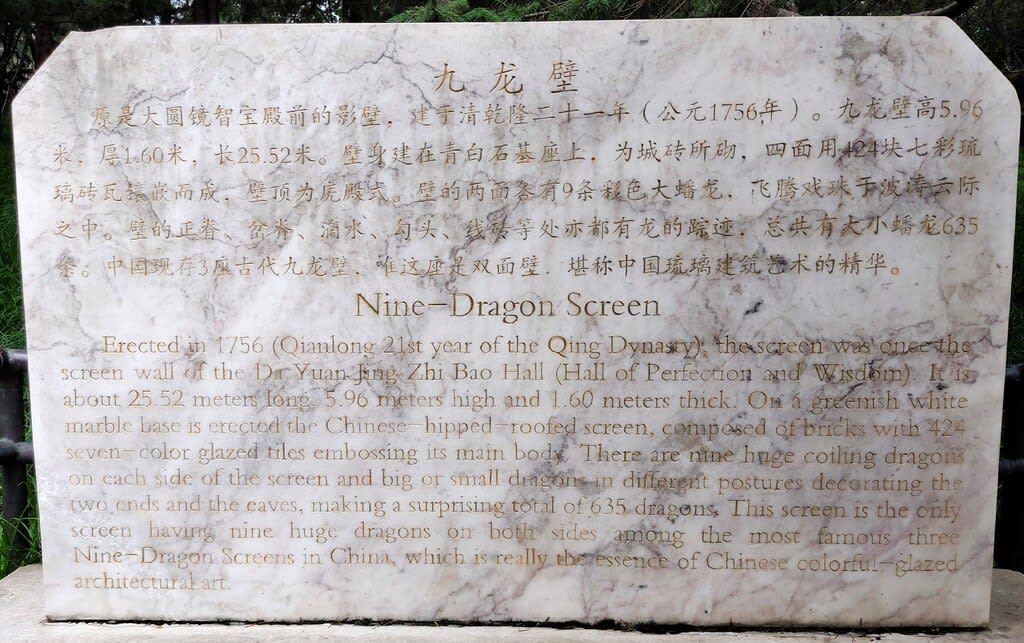芥川龍之介は北京に滞在したことがあります。
1921年(大正10年)、当時29歳の芥川は大阪毎日新聞の特派員として中国各地を取材して回りました。
北京を訪れたのはこの旅の後半で、6月から7月にかけての約1か月間でした。
芥川は北京での訪問記を「北京日記抄」として残しています。発表したのは旅の4年後となる1925年です。
このほか、さまざまな文献から芥川の北京での足跡や訪問当時の心境が明らかになっています。

芥川は中国の長旅で心身を病み、嫌気がさしていたようですが、北京の印象はことのほかよかったようです。
今回は、この「北京日記抄」に記されている辜鴻銘(1857—1928、学者・翻訳家)を訪問した時の足跡をたどってみました。
まずはその部分の原文を記してみます。
この原稿は、国立国会図書館デジタルコレクションで芥川の手書き原稿を閲覧することができます(ココ)。
コマ番号8ページから始まります。なんとも便利でありがたいことです。
二 辜鴻銘先生
辜鴻銘先生を訪う。ボイに案内されて通りしは素壁に石刷の掛物をぶら下げ、床にアンペラを敷ける庁堂なり。ちょっと南京虫はいそうなれど、蕭散愛すべき庁堂と言うべし。
待つこと一分ならざるに眼光烱々たる老人あり。闥を排して入り来り、英語にて「よく来た、まあ坐れ」と言う。勿論辜鴻銘先生なり。胡麻塩の辮髪、白の大掛児、顔は鼻の寸法短かければ、何処か大いなる蝙蝠に似たり。先生の僕と談ずるや、テエブルの上に数枚の藁半紙を置き、手は鉛筆を動かしてさっさと漢字を書きながら、口はのべつ幕なしに英語をしゃべる。僕の如く耳の怪しきものにはまことに便利なる会話法なり。
先生、南は福建に生れ、西はスコットランドのエディンバラに学び、東は日本の婦人を娶り、北は北京に住するを以て東西南北の人と号す。英語は勿論、ドイツ語もフランス語も出来るよし。されどヤング・チャイニィイズと異り、西洋の文明を買い冠らず。基督教、共和政体、機械万能などを罵る次手に、僕の支那服を着たるを見て、「洋服を着ないのは感心だ。只憾むらくは辮髪がない」と言う。先生と談ずること三十分、忽ち八九歳の少女あり。羞かしそうに庁堂へ入り来る。蓋し先生のお嬢さんなり。(夫人は既に鬼籍に入る。)先生、お嬢さんの肩に手をかけ、支那語にて何とか囁けば、お嬢さんは小さい口を開き、「いろはにほへとちりぬるをわか……」云々と言う。夫人の生前教えたるなるべし。先生は満足そうに微笑していれど、僕はいささかセンティメンタルになり、お嬢さんの顔を眺むるのみ。
お嬢さんの去りたる後、先生、又僕の為に段を論じ、呉を論じ、併せて又トルストイを論ず。(トルストイは先生へ手紙をよこしたよし)論じ来り、論じ去って、先生の意気大いに昂るや、眼は愈炬の如く、顔はますます蝙蝠に似たり。僕の上海を去らんとするに当り、ジョオンズ、僕の手を握って曰いわく、「紫禁城は見ざるも可なり、辜鴻銘を見るを忘るること勿れ。」と。ジョオンズの言、僕を欺かざるなり。僕、亦また先生の論ずる所に感じ、何ぞ先生の時事に慨して時事に関せんとせざるかを問う。先生、何か早口に答うれど、生憎あいにく僕に聞きとること能わず。「もう一度どうか」を繰り返せば、先生、さも忌々しそうに藁半紙の上に大書して曰、「老、老、老、老、老、……」と。
一時間の後、先生の邸を辞し、歩して東単牌楼のホテルに向えば、微風、並木の合歓花を吹き、斜陽、僕の支那服を照す。しかもなお蝙蝠に似たる先生の顔、僕の眼前を去らざるが如し。僕は大通りへ出ずるに当り、先生の門を回看して、――先生、幸に咎むること勿れ、先生の老を歎ずるよりも先に、未だ年少有為なる僕自身の幸福を讃美したり。
以上です。いかがでしょうか。
辜鴻銘の住まいがあったのは今の東城区柏樹胡同です。


当時の邸宅はすでに取り壊されていますが、場所は柏樹胡同26号という情報と30号(旧王府井旅館)という情報があります。
両者は30メートルぐらい離れていますが、どちらでしょうか。あるいは、両方そうなのでしょうか。

ここが26号です。


この建物が30号です。今は「人民小酒文化館」というレストランになっています。
芥川はこの辺りで辜鴻銘と段祺瑞やトルストイについて論じました。
当時29歳の芥川に対して、辜鴻銘は64歳になろうかという年齢です。
芥川は辜鴻銘との面会を終えた後、ここから歩いてホテルまで戻りました。
僕もその道をたどってみることにします。

日記では斜陽に照らされたことが記されているので、時間は日没前の18時台といったところでしょうか。
夏至の頃ですから日は長かったはずです。
柏樹胡同を東側に向かって歩きます。幅は7メートルほどの道です。
さて、紀行文によると、芥川は道中で合歓(ネムノキ)の花を愛でたようですが、その木は今もあるでしょうか。
丁寧に見て回りましたが、ネムノキらしい木は見当たりませんでした。この辺りは槐(エンジュ)が多いようです。

この槐の老木は樹齢100年は越えていそうです。おそらく芥川が訪ねたときからあったのではないでしょうか。

ひょっとしたら、芥川は北京市内の別の場所で見たネムノキの記憶をここに重ね合わせて表現した、という可能性もあるかもしれません。
なにしろ紀行文を発表したのは帰国から4年後のことです。取材メモを見ながらの執筆だったはずです。
北京では今もネムノキをよく見かけます。6月ごろに咲く白と紫の花はとても可憐で美しいものです。

この老建築も古そうです。リノベーションしていますが、元々は当時からあったものでしょう。

柏樹胡同を300メートルほど歩くと、東単北大街に出ました。

芥川が紀行文で「大通り」と説明しているのはこの突き当りの通りです。
芥川はここで西側の胡同を振り返っています。

これが振り返った景色です。芥川と同じ目線で見た景色です。
紀行文では「先生の門を囘看し」とありますが、ここから辜鴻銘邸までは相当距離があります。
一直線ですが、本当に門が見えたのかは疑問です。
あるいは景色の中に溶け込む門を心で見た、という意味なのかもしれません。
芥川はこの東単大街を右折し、南側にある「東単牌楼のホテル」に向かいます。

東単牌楼とは、芥川は地名として用いていますが、その名のとおり東単にあった牌楼でした。
牌楼とは、ちょっと乱暴なたとえですが、いかつい鳥居みたいなものと思えばよいと思います。
場所は長安街と東単大街の交わる場所です。当時北京最大の繁華街のひとつだった東単大街の南側の入口に構えられていたランドマークでした。

牌楼は交通の妨げになったため、1923年に取り壊されました。芥川の訪問の2年後のことです。
芥川が宿泊していたホテルは扶桑館という名前だったことが分かっています。これも建物は残っていません。

10分ほど歩くと、扶桑館があったと思われる場所に着きました。


古地図で照合すると、ホテルはこの植込みのある場所に建っていたようです。

東単牌楼が建っていたのは、この歩道橋のあたりだと思われます。
歩道橋に登ってみます。

芥川は向こう側からこちら側に歩いてきました。中央奥の植込みが扶桑館のあった場所です。
この通りを中華服を着た29歳の芥川が歩いたと。
扶桑館の話は次回に続きます。
1921年(大正10年)、当時29歳の芥川は大阪毎日新聞の特派員として中国各地を取材して回りました。
北京を訪れたのはこの旅の後半で、6月から7月にかけての約1か月間でした。
芥川は北京での訪問記を「北京日記抄」として残しています。発表したのは旅の4年後となる1925年です。
このほか、さまざまな文献から芥川の北京での足跡や訪問当時の心境が明らかになっています。

芥川は中国の長旅で心身を病み、嫌気がさしていたようですが、北京の印象はことのほかよかったようです。
今回は、この「北京日記抄」に記されている辜鴻銘(1857—1928、学者・翻訳家)を訪問した時の足跡をたどってみました。
まずはその部分の原文を記してみます。
この原稿は、国立国会図書館デジタルコレクションで芥川の手書き原稿を閲覧することができます(ココ)。
コマ番号8ページから始まります。なんとも便利でありがたいことです。
二 辜鴻銘先生
辜鴻銘先生を訪う。ボイに案内されて通りしは素壁に石刷の掛物をぶら下げ、床にアンペラを敷ける庁堂なり。ちょっと南京虫はいそうなれど、蕭散愛すべき庁堂と言うべし。
待つこと一分ならざるに眼光烱々たる老人あり。闥を排して入り来り、英語にて「よく来た、まあ坐れ」と言う。勿論辜鴻銘先生なり。胡麻塩の辮髪、白の大掛児、顔は鼻の寸法短かければ、何処か大いなる蝙蝠に似たり。先生の僕と談ずるや、テエブルの上に数枚の藁半紙を置き、手は鉛筆を動かしてさっさと漢字を書きながら、口はのべつ幕なしに英語をしゃべる。僕の如く耳の怪しきものにはまことに便利なる会話法なり。
先生、南は福建に生れ、西はスコットランドのエディンバラに学び、東は日本の婦人を娶り、北は北京に住するを以て東西南北の人と号す。英語は勿論、ドイツ語もフランス語も出来るよし。されどヤング・チャイニィイズと異り、西洋の文明を買い冠らず。基督教、共和政体、機械万能などを罵る次手に、僕の支那服を着たるを見て、「洋服を着ないのは感心だ。只憾むらくは辮髪がない」と言う。先生と談ずること三十分、忽ち八九歳の少女あり。羞かしそうに庁堂へ入り来る。蓋し先生のお嬢さんなり。(夫人は既に鬼籍に入る。)先生、お嬢さんの肩に手をかけ、支那語にて何とか囁けば、お嬢さんは小さい口を開き、「いろはにほへとちりぬるをわか……」云々と言う。夫人の生前教えたるなるべし。先生は満足そうに微笑していれど、僕はいささかセンティメンタルになり、お嬢さんの顔を眺むるのみ。
お嬢さんの去りたる後、先生、又僕の為に段を論じ、呉を論じ、併せて又トルストイを論ず。(トルストイは先生へ手紙をよこしたよし)論じ来り、論じ去って、先生の意気大いに昂るや、眼は愈炬の如く、顔はますます蝙蝠に似たり。僕の上海を去らんとするに当り、ジョオンズ、僕の手を握って曰いわく、「紫禁城は見ざるも可なり、辜鴻銘を見るを忘るること勿れ。」と。ジョオンズの言、僕を欺かざるなり。僕、亦また先生の論ずる所に感じ、何ぞ先生の時事に慨して時事に関せんとせざるかを問う。先生、何か早口に答うれど、生憎あいにく僕に聞きとること能わず。「もう一度どうか」を繰り返せば、先生、さも忌々しそうに藁半紙の上に大書して曰、「老、老、老、老、老、……」と。
一時間の後、先生の邸を辞し、歩して東単牌楼のホテルに向えば、微風、並木の合歓花を吹き、斜陽、僕の支那服を照す。しかもなお蝙蝠に似たる先生の顔、僕の眼前を去らざるが如し。僕は大通りへ出ずるに当り、先生の門を回看して、――先生、幸に咎むること勿れ、先生の老を歎ずるよりも先に、未だ年少有為なる僕自身の幸福を讃美したり。
以上です。いかがでしょうか。
辜鴻銘の住まいがあったのは今の東城区柏樹胡同です。


当時の邸宅はすでに取り壊されていますが、場所は柏樹胡同26号という情報と30号(旧王府井旅館)という情報があります。
両者は30メートルぐらい離れていますが、どちらでしょうか。あるいは、両方そうなのでしょうか。

ここが26号です。


この建物が30号です。今は「人民小酒文化館」というレストランになっています。
芥川はこの辺りで辜鴻銘と段祺瑞やトルストイについて論じました。
当時29歳の芥川に対して、辜鴻銘は64歳になろうかという年齢です。
芥川は辜鴻銘との面会を終えた後、ここから歩いてホテルまで戻りました。
僕もその道をたどってみることにします。

日記では斜陽に照らされたことが記されているので、時間は日没前の18時台といったところでしょうか。
夏至の頃ですから日は長かったはずです。
柏樹胡同を東側に向かって歩きます。幅は7メートルほどの道です。
さて、紀行文によると、芥川は道中で合歓(ネムノキ)の花を愛でたようですが、その木は今もあるでしょうか。
丁寧に見て回りましたが、ネムノキらしい木は見当たりませんでした。この辺りは槐(エンジュ)が多いようです。

この槐の老木は樹齢100年は越えていそうです。おそらく芥川が訪ねたときからあったのではないでしょうか。

ひょっとしたら、芥川は北京市内の別の場所で見たネムノキの記憶をここに重ね合わせて表現した、という可能性もあるかもしれません。
なにしろ紀行文を発表したのは帰国から4年後のことです。取材メモを見ながらの執筆だったはずです。
北京では今もネムノキをよく見かけます。6月ごろに咲く白と紫の花はとても可憐で美しいものです。

この老建築も古そうです。リノベーションしていますが、元々は当時からあったものでしょう。

柏樹胡同を300メートルほど歩くと、東単北大街に出ました。

芥川が紀行文で「大通り」と説明しているのはこの突き当りの通りです。
芥川はここで西側の胡同を振り返っています。

これが振り返った景色です。芥川と同じ目線で見た景色です。
紀行文では「先生の門を囘看し」とありますが、ここから辜鴻銘邸までは相当距離があります。
一直線ですが、本当に門が見えたのかは疑問です。
あるいは景色の中に溶け込む門を心で見た、という意味なのかもしれません。
芥川はこの東単大街を右折し、南側にある「東単牌楼のホテル」に向かいます。

東単牌楼とは、芥川は地名として用いていますが、その名のとおり東単にあった牌楼でした。
牌楼とは、ちょっと乱暴なたとえですが、いかつい鳥居みたいなものと思えばよいと思います。
場所は長安街と東単大街の交わる場所です。当時北京最大の繁華街のひとつだった東単大街の南側の入口に構えられていたランドマークでした。

牌楼は交通の妨げになったため、1923年に取り壊されました。芥川の訪問の2年後のことです。
芥川が宿泊していたホテルは扶桑館という名前だったことが分かっています。これも建物は残っていません。

10分ほど歩くと、扶桑館があったと思われる場所に着きました。


古地図で照合すると、ホテルはこの植込みのある場所に建っていたようです。

東単牌楼が建っていたのは、この歩道橋のあたりだと思われます。
歩道橋に登ってみます。

芥川は向こう側からこちら側に歩いてきました。中央奥の植込みが扶桑館のあった場所です。
この通りを中華服を着た29歳の芥川が歩いたと。
扶桑館の話は次回に続きます。