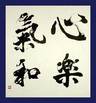見方についての話題です。武道ではそれを「目付け」といいます。宮本武蔵の表現が有名で、かつ分かりやすいので、「兵法三十五箇条の六番目」を引用します。
一 目付の事
目を付けると云う所、昔は色々在ることなれ共、今伝わる処の目付は、大体顔に付けるなり。目のおさめ様は、常の目よりもすこし細き様にして、うらやかに見る也。目の玉を不動、敵合近く共、いか程も、遠く見る目也。其の目にて見れば、敵の技は申す及ば不、左右両脇迄も身ゆる也。観見二つの見様、観の目つよく、見の目よはく見るべし。若し又敵に知らすると云ふ目在り。意は目に付け、心は物に付け不也。能々吟味有るべし。
文京道場の稽古仲間の黒猩猩さんのブログにも、彼の意見が紹介されています。ここ。参考になるのでお読みください。
さて、私が今日、どう感じたかを話します。これは武術的目付の話ですが、今日物事を観照する時、同じ見方をすべきではないか、いやそうすると違った見方が出来て面白いのではないかと思います。たとえばここに表示したのは、私の写心館から転載したものです。朝顔か昼顔の種です。武蔵のいう「見の目」すなわち「肉眼による動体視力」で見ると、単なる枯れ草の写真でしかありません。一方の武蔵のいう「観の目」すなわち「心眼による感知・予知力」で観ると、今まさに熟した種の生命力が発露し、新しい生命への継承が始まった場面の写真です。
さらに武蔵は「観の目つよく、見の目よはく見るべし」といいます。物質的現状よりも、内的な意図を強調しています。この辺が重要かと思います。物心両面の5:5ではないのです。心眼強くとは、どのような割合でしょう。そこが気になります。4:6でしょうか?
私は2:8の割合で、心眼強くといっているのではないかと思います。
貴方は、どう思われますか?
関連記事
一 目付の事
目を付けると云う所、昔は色々在ることなれ共、今伝わる処の目付は、大体顔に付けるなり。目のおさめ様は、常の目よりもすこし細き様にして、うらやかに見る也。目の玉を不動、敵合近く共、いか程も、遠く見る目也。其の目にて見れば、敵の技は申す及ば不、左右両脇迄も身ゆる也。観見二つの見様、観の目つよく、見の目よはく見るべし。若し又敵に知らすると云ふ目在り。意は目に付け、心は物に付け不也。能々吟味有るべし。
文京道場の稽古仲間の黒猩猩さんのブログにも、彼の意見が紹介されています。ここ。参考になるのでお読みください。
さて、私が今日、どう感じたかを話します。これは武術的目付の話ですが、今日物事を観照する時、同じ見方をすべきではないか、いやそうすると違った見方が出来て面白いのではないかと思います。たとえばここに表示したのは、私の写心館から転載したものです。朝顔か昼顔の種です。武蔵のいう「見の目」すなわち「肉眼による動体視力」で見ると、単なる枯れ草の写真でしかありません。一方の武蔵のいう「観の目」すなわち「心眼による感知・予知力」で観ると、今まさに熟した種の生命力が発露し、新しい生命への継承が始まった場面の写真です。
さらに武蔵は「観の目つよく、見の目よはく見るべし」といいます。物質的現状よりも、内的な意図を強調しています。この辺が重要かと思います。物心両面の5:5ではないのです。心眼強くとは、どのような割合でしょう。そこが気になります。4:6でしょうか?
私は2:8の割合で、心眼強くといっているのではないかと思います。
貴方は、どう思われますか?
関連記事