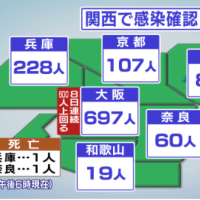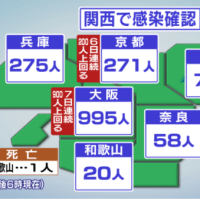自他不二は画餅にあらずや彼我唱う天上天下唯我独尊
((現代仮名遣いで) じたふには がへいにあらずや ひがとなう てんじょうてんげ ゆいがどくそん)
【補註】
「自他不二」≒ ひとの身になること(自分と他人は一体であること ≒ 「お互い様」(=互譲)の精神)
「天上天下唯我独尊」≒ 自分が最も大切だということ
以下は、わたしの浅薄かつ図式的な仏教理解です。
宗教=ひとが生きるうえでの指針
(故 福島慶道老師が講和の中で述べておられた『宗教とはライフスタイルの問題だ』ということを、わたしはこのような意味に理解しています。多分に哲学的問題)
宗教の出発点:自分が最も大切だということ(=エゴ)
人間:社会的存在としてしか生きてゆけない
→ 社会:各々の「唯我独尊」(=エゴ)が衝突し合う関係
→ 社会存立のために必要な至上命題 =「自他不二」
「唯我独尊」と「自他不二」との調整原理 =「慈悲」(≒ '思いやり')
(白状すると、「自他不二」と「慈悲」を概念的に区別することはできないでいます)
(蛇足:「唯我独尊」と「自他不二」と「慈悲」との関係は、キリスト教に由来する「個人の尊厳」原理の敷衍された「自由」と「平等」(しかるに、両者は究極的には矛盾します)、両者の調整原理としての「博愛」とのそれに酷似)
(蛇々足:「慈悲」、「博愛」ともに、”自己犠牲”を本質とするという点で共通すると思います)
仏教では、現実のこの世に存在する諸事象、すなわち、自他、男女、老若、物心(色心)、生死、善悪、苦楽、美醜などの区別を、それぞれ相対立する二元論として捉え、各対立概念を、「空」(≒ 「無」)(=現実の事象には実体がないこと)の下では、不二・一体なのだと説かれています。しかし、少なくとも男女の別に限っては、一体でないことを認めたうえで、論を進めているようです(この項については「岩波 仏教辞典『不二』」参照)。
(蛇足:「男と女のあいだには ふかくて暗い 河がある 誰も渡れぬ 河なれど エンヤコラ今夜も 舟を出す」という、かつてのヒット曲は、極めて正鵠を得たものとして忘れられません。バハールの涙 | 映画 | 無料動画GYAO!を見たときも、"産む性"である女性が、産まれた存在である"犯す性"としての男たちを殺すという、理解を超えた絶対的矛盾にいたく戸惑いました)
さらにわたしは、自他の間に厳然として存在する能力の差を認めざるを得ないと考えています。
要するに、わたしの考える宗教の出発点としては、「唯我独尊」の他に、少なくとも「男女」の別、「能力」差をも措定しなければならず(まだ他にもあるかも知れません)、後二者を踏まえたうえでの「唯我独尊」だと、牽強付会的理解であることを白状しなければなりません。
それはともかく、わたしが、「自他不二」が現実に果たして実践可能かという疑問を抱いたのは、死の床にあった妻と母に対したときです。
妻はホスピスで最期を迎えました。妻はホスピスの何たるかを理解してはいませんでした。せめて安らかな最期を、との願いから、わたしはホスピスに妻を預けました。抗ガン治療は、かえってからだの負担になるとの理由で、中止され、主として鎮痛剤のみの投与がなされていました。死ぬ十日前の頃、妻が、急速な衰えに不安を覚えたのか、「ウチに帰れるやろか?」と心細げに問いかけてきました。咄嗟に返すべきことばが見つけられず、わたしは、「ここで養生すれば帰れる」と答えるのが精いっぱいでした。一枚の写真があります。カマキリのようにやせ細った妻が、ベッドに仰向けた姿勢で、窓外の空にぼんやり見入っている様子です。絶望とも、諦念とも受け取れる表情。その心情をうかがうことは全くできませんでした。尋ねることさえできませんでした。わたしは、今も、妻を騙したという罪悪感から、自由ではありません。果たして、死後の妻の表情は、般若のように険しいものでした。わたしに対する、ありったけの怨みを残しているように思われました。
母は、郷里の老人ホームで、介護スタッフの協力のもと、百歳の長寿を全うして逝きました。直前の母は、老衰の極みとも言えるような、褥瘡に苦しめられていました。母は、はじめのうちは、痒さを訴えることができたので、母の指示に従ってかゆみ止めの薬を塗ることができました。しかし、直に痒い部分を指し示すべく腕を上げてはそれを力なく落とすだけになりました。母の表情だけを頼りに痒そうな部位に薬を塗ることしかできませんでした。最も血が濃く、この世で最も理解し得るはずの母の痒みの部位さえ察してやれないことの悔しさ。「自他不二」とはいうものの、息子であるわたしが、百歳の老い衰えた母と一体になることは到底なれません。もし、そうなれたとしても、死に瀕した身で、何ほどのことができたでしょうか。
下顎呼吸が始まり、手足さえ動かせなくなった母に、禅者のはしくれとして、「生死不二」とか「生死一如」と説いたところで、母に「安心」をもたらすことができようとは到底思えませんでした。代わりにわたしが夢中で母にかき口説いたことは、「ありがとう、さようなら」と「ほら、とうちゃんがそこにいるよ、弟もいるよ、また会えてよかったね」などという、禅者らしからぬことばだけでした。今際の母が覚えているかも知れない、死とこの世を去ることへの不安と恐怖を少しでも和らげることができるのではないか、また聴覚だけは最後まで残るという噂をあてにした呼びかけでした。
後に、奥野慈子著「『お迎え』されて人は逝く 終末期医療と看取りのいま」(ポプラ新書)という本を読みました。著者は「緩和ケア医」。「お迎え」とは、逝く間際に、あの世から、先に死んだ親しい人が迎えに来てくれる、という、終末期の意識障害の一つの現れ。「お迎え」現象を話す本人は、とても穏やかそうな表情をみせるということです。たとえ、死ぬ間際のせん妄であれ、「お迎え」されて逝くことは、幸福な死の在り様ではないかと思いました。
禅者として「生死不二(一如)」を極めるよりも、死んでいった親しい人々との再会という幻想に包まれて死旅立つほうが、はるかに手っ取り早く、かつ実用的な途ではないかと、心揺れる、きょうこの頃です。