
その2の続き
【結 び】
軍律審判と通常司法は違う。軍律審判は【行政行為】と【軍事行動】であるし、日本軍を裁いた極東国際軍事裁判(通称東京裁判)においても、日本軍の行為に於ける【蛮行】を裁く【法の根拠】などが無く、それを【法】曲げて【無かった罪を作り出し】ことで、国際法として【刑法】の【戦争犯罪】が成り立っていたことが無く、その様な罪科無きもので裁いた【判決】は【無効】であると判断する。
軍事裁判であるのなら、なおさら講和成立後は、アムネスティ条項で日本軍の【戦犯】は無効と成すべきである。それに関係することでもあるが、靖国参拝など政教分離の議論は別として、天皇陛下および日本国民の代表としての内閣総理大臣は、国家として国家のために殉じられた人々に対する敬意を示す行為も再会すべきである。
【法の支配】というのなら、【国際法】の視点からの認識による現代に日本の史観の変更と、この【人権無視】も甚だしい【サンフランシスコ条約】についてのせめて米国・英国・フランスについては、【非人道な条約】に関する改定を求めるべきであると考える。
【参照論文・文献】
(*1)冨士信夫氏著 『「南京大虐殺」はこうして作られた─東京裁判の欺瞞』 展転社 1995年5月
P.22 2行目
〈この作戦は支那の首都南京の掌握とともに終了した。この古代都市の住民が強盗、拷問、強姦、殺戮の目に遭わされたこと、虐行、乱的軍人の盲群の手に持たされた放火物、銃剣および機関銃は、匈奴「アチラ」以来比類なき戦慄すべき物語を綴ったことおよび支那軍人が把に括られ、無差別に乱殺されたことを我々は証示する〉と述べ、その後引き続き中国における日本軍の行動等について述べて冒頭陳述を終わったが、
(*2)笠原十久司著『南京事件論争史 日本人は史実をどう認識してきたか』平凡社新書403
一九三七年から開始された日中戦争の初期、当時の中国の首都南京を占領した日本軍が、中国軍の兵士・軍夫ならびに一般市民・難民に対しておこなった戦時国際法や国際人道法に反した不法、残虐行為の総体である。
(*3)ハーグ陸戦条約 wikihttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。
交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。
日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
(*4)ヴェストファーレン条約 Wikiよりhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E6%9D%A1%E7%B4%84
(ヴェストファーレンじょうやく、羅: Pax Westphalica、独: Westfälischer Friede、英: Peace of Westphalia)は、1648年に締結された三十年戦争の講和条約で、ミュンスター講和条約とオスナブリュック講和条約の総称である。ラテン語読みでウェストファリア条約とも呼ばれる。近代における国際法発展の端緒となり、近代国際法の元祖ともいうべき条約である。
この条約によって、ヨーロッパにおいて30年間続いたカトリックとプロテスタントによる宗教戦争は終止符が打たれ、条約締結国は相互の領土を尊重し内政への干渉を控えることを約し、新たなヨーロッパの秩序が形成されるに至った。この秩序を「ヴェストファーレン体制」ともいう。
(*5)①倉山満著『国際法で読み解く世界史の真実』 PHP新書 2016年11月15日
P202 11行目 第四章 国際法を使いこなした明治日本、破壊したウィルソン=>4 人類を劣化させ、国際法を破壊したウッドロー・ウィルソン=>旧外交否定と民族自決が開いた地獄
(*5)②倉山満著 『ウェストファリア体制 天才グロティウスに学ぶ「人殺し」と平和の法』 PHP新書 2019年11月16日
P.229 6行目 第四章「ウェストファリア体制」の現実=>ウッドロー・ウィルソンが人類を不幸にした
第十四条、国際連盟設立。国際連盟は「仮面を着けた大国主義」と言われます。
以上すべて、それまでの国際秩序を全否定し、世界をウィルソンの思うように作りかえようとしたのです。
ウッドロー・ウィルソンの十四ヵ条宣言で、「ウェストファリア体制」は風前の灯火になってしまいました。
(*6)多谷千香子著『戦争犯罪と法』(2006年12月5日)岩波書店
P.2 「第2節 第一次世界大戦後のドイツ戦犯の裁判」
・ヴェルサイユ条約 平和条約予備交渉
1919年1月25日 ドイツ及びその同盟国の戦争犯罪について連合国としての対応を協議する「戦犯の責任及び処罰に関する委員会:通称15人委員会」(Commission on the Responsibility of the Authors of War and on Enforcement of Penalties)で国際法違反の罪を犯したものを次の四つにタイプに想定した。①捕虜を虐待した者、②戦争の指揮官、③戦争の法規及び慣習違反を命令した者又は見逃した者、④その他、国際法廷で裁くことが適当な者であり、戦犯を連合国が裁く為の国際法廷を作る事、文明国に共通する法の一般原則を適用する事、量刑は連合国及びドイツの慣習によって決める事。
刑罰(Penalties) 227条〜230条
227条 ドイツ皇帝を裁く米・英・仏・伊・日の裁判官からなる特別法廷を創設する。オランダに皇帝の引き渡しを要求する。
228条 ドイツは、戦争の法規及び慣習に違反した戦犯を、連合国が軍事法廷で裁く権利を認め、戦犯を引き渡す。
229条 連合国の一国の国民に対して戦争犯罪を犯した戦犯は、当該国の軍事法廷で裁かれる。いずれの場合も、被告人は、弁護人をつける権利を有する。
230条 ドイツは、捜査・裁判に必要なすべての証拠・資料・情報を提供する。
(*7)藤田久一著『戦争犯罪とは何か』 岩波新書 1995年3月20日
P.61 7行目 Ⅱあらたな戦争犯罪の観の模索=>4.カイゼルの刑事責任をめぐる議論
〔オランダ政府は〕戦争の起源にはまったく関知しなかったし、……最後まで中立を維持した。それゆえ……同政府は諸国の高度の国際政治行為にくわわる国際的義務を認めえない。もし将来、国際連盟によって、戦争の場合に、犯罪とされた行為で、かつ、犯された行為より以前の規定によって制裁を科せられる行為を裁くために、権限ある国際管轄権が設定されるならば、オランダはこの新制度にくわわることになろう。……〔オランダ王国の憲法もまた〕つねにこの国を国際紛争の敗者のための避難地として古くからの尊敬すべき伝統も、オランダ政府がこの法律およびこの伝統の利益を前皇帝から奪うことによって諸国の願望にこたえることを許さない。
一九二〇年二月一五日新覚書がオランダとドイツに送られた。これは、やや穏やかな表現ながら、引き渡し要求が聞き入れられなかったことを遺憾とし、あらためて引き渡しを求める理由を述べた。これに対してオランダ政府は三月六日改めて覚書を送って反論した。同盟および連合国側とオランダとのこのような覚書によるやりとりがくりかえされたが、結局事態は変化せず、引き渡しが行われないまま推移したのである。
ドイツの異議申し立て
また、ドイツ政府はヴェルサイユ平和条約のこれらの刑罰規定にくりかえし異義を申し立てていた。すでに一九一九年五月七日のドイツ外相ブロックドルフ・ランツァウ伯の演説は、戦勝国が戦敗国に「敗者として賠償を支払わせ、罪人として刑罰を加えよう」としていることに抗議していた。さらに、いくつかの覚書で、中立国による戦争責任の調査を求めた。そして二九日の覚書に付けられた陳情書で、二二七条に規定してある特別裁判所は国際法上何の法的根拠もなく、例外的裁判所というべきものであって、遡及的効力を有する例外的法律を適用しようとするものであるとして、異義を申し立てた。
結局ドイツ政府は、平和条約を受諾するに際して、二二七〜二三〇条に署名しえないと留保したのである。
(*8)倉山満著『国際法で読み解く世界史の真実』 PHP新書 2016年11月15日
P.27 9行目 第1章 国際法で読む国別「傾向と対策」=>戦争そのものに善悪の区別はない
国際法は、無意味な殺傷、不必要な残虐行為をやめさせようとの発想に立ちます。
そこで登場した考え方が、「戦争とは、国家と国家による決闘である」との考え方です。決闘は単なる喧嘩ではないので、ルールがあります。グロチウスの意図は、その」ルールを整備しようというところにあります。
そもそも「決闘」とは、「どちらの主張が認められるかは、ルールに基づき正々堂々と戦って決着をつける」というものです。決着は「善悪」でつけるのではありません。善悪を言い出したら、決闘で負けた者が「それでも自分が正義だ」などと言い出して収拾がつかなくなります。
(*9)清水正義著『第一次世界大戦後の前ドイツ皇帝訴追間題』」『白鴎法学』第十九号
例えば、オーストラリア首相ヒューズは「彼[前皇帝]には世界を戦争に突っ込ませる完全な権利があるのです。今、我々は勝利をした。だから彼を殺す完全な権利がありますが、それは彼が世界を戦争に突っ込ませたからではなくて我々が勝ったからです。法律違反で彼を訴追するなんて、首相、それはできませんよ」と率直に語り、ロイド・ジョージを牽制すると、軍需相チャーチルも呼応して、「前皇帝を絞首刑にするという道を意気揚々と開始するのは易しいし、大衆の一般的関心をその中に取り入れることもできる。けれど、時が過ぎてやがて大変な袋小路に陥ってしまうことになるでしょう。世界中の法律家たちがこの起訴状はとても支えきれるものではないことに気がつき始めるでしょう」と非常に消極的な姿勢に終始した。
(*10)陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 Wikiより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。
第2条:第1条に掲げた規則及び本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。
第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年の条約に代わるべきものとする。ただし、1899年の条約は本条約に記名しながら批准をしない諸国間の関係においては依然効力を有する。
第5条:本条約はなるべく速やかに批准しなければならない。(詳細略)
第6条:記名国でない諸国は本条約に加盟できる。(詳細略)
第7条:(批准国における効力発生条文につき 略)
第8条:締結国が本条約を破棄するときはオランダ政府にその旨書面で通告しなければならない。オランダ政府は、直ちに通告書の認證謄本をそのほかの諸国に送付し、かつその通告書を受理した日を通知すること。
破棄はその通告書がオランダ政府に到達した時点から一年後、通告した国に対してのみ効力を生じる。
第9条:オランダ外務省が帳簿を管理する。(詳細略)
(*11)英国砲艦のレディバード及び同型艦のビーに砲撃を加え被害を与えた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89_(%E7%A0%B2%E8%89%A6)
「パネイ」号事件に関する米大使宛書翰写送付の件 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C01001546500
各種情報資料・支那事変彙報 「パナイ」号事件損害額明細(米国ドルにて計上) https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000761421
(*12)倉山満著『国際法で読み解く世界史の真実』 PHP新書 2016年11月15日
P.102 第2章 武器使用マニュアルとしての「用語集」=>刑事裁判と民事裁判にたとえればわかる
(*13)石田清史著『近代日本に於る参審の伝統─ 裁判員制度を契機として─』 苫小牧駒澤大学紀要 第14号 2005年11月
P.62 h.軍律会議
軍法会議の性格を明らかにするため、軍律会議(又は軍律法廷。以下軍律会議と呼ぶ)に付言する。この言葉は耳慣れないが、東京裁判もまた軍律会議であった。極東国際軍事裁判と称して軍法会議と呼ばないのはこの為である。軍事裁判=軍法会議とする誤解が蔓延しているが、軍律会議も又軍事裁判である。軍律会議は戦時に特設される臨時の機関で、統帥大権に基き、自軍の利益のために設けられる。よって犯人のマグナカルタ(当方註:罪刑法定主義のこと)的機能は乏しい。軍律と軍律会議は名こそ違え、内外に存在する。近代日本に於る嚆矢は日清戦争の際「占領地人民処分令」に基き設置した軍事法院であった。日露戦争時も陸軍第四軍に審判委員会が設けられた。支那事変に際しては陸軍が軍律会議、海軍が軍罰処分会議を置いた。米軍にもMilitary Commission軍事委員会、英軍にもMilitary Court under Martial Lawが存する。
軍法会議が主として自国民に対する裁判であるのに対し、軍律会議は逆に外国人を裁く。敵国軍人や敵性住民も戦時国際法を遵守する限り国際法の保護を受けるが、戦争法規を犯して敵対行為を働く者は単なる戦時重罪犯、戦時刑法犯であるから国際法の保護を受けない。敵国軍人や占領地域住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る。これが軍律であり、軍律会議である。国際慣習法上認められて来たものであるが、1907年のハーグ陸戦法規第3款が「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」として第42条以下を以て占領地に於る軍律、軍律会議を認めたと解されている。国内法的には大日本帝国憲法第11条の「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定される統帥大権に根拠を求めた。軍律や軍律会議は作戦用兵上の必要に基き、軍が自ら定立するからである。つまり軍事行動であり、戦争行為なのである。軍刑法や軍法会議法などに対する下位法であるから当然、上位法に劣後し、法律の制約を受ける。
(*14)佐藤和男監修『世界が裁く東京裁判』 明成社 改訂版 2005年8月
P.271 1行目 【附録Ⅱ】日本は東京裁判史観により拘束されない=>二 講和条約とアムネスティ条項
さて、ここで、アムネスティ条項(amnesty clause)の説明に移ります。前述のごとく戦争を終了させるものは講和ですが、第一次世界大戦以前の時代にあっては、交戦諸国は講和に際して、平和条約の中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」を設けるのが通例でした。これがアムネスティ条項と呼ばれる者ですが、アムネスティとは「国際法上の大赦」を意味します。
国際法では伝統的に戦争それ事態は合法制度とされ、戦争の手段・方法を規律する交戦法規に違反した者だけが戦争犯罪人として、戦時敵に捕らえられた場合に裁判にかけられて処罰されました。戦争を計画・遂行した指導者を犯罪に(いわゆるA級戦犯)とする国際法の規則は、厳密には今日でも存在していないと観がエッレ艇増す。(第二次世界大戦後、国際連合憲章の発効とともに、自衛戦争とは反対の侵攻戦争[俗訳・侵略戦争]は、明らかに違法行為とされましたが、重大な違法行為としての犯罪とは正式にはまだされておらず、このことは国際連合国際法委員会においても認められています。)
アムネスティ条項の説明の実例として、アメリカの国際法学者C・G・フェンウィック博士が自著『国際法』(一九三四年)の中で述べているものを要約しますと、同条項は「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つものとされます。しかも、講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、このような責任免除は講和(戦争終結)に伴う法的効果の一つであることが確認され、アムネスティ(大赦)が国際慣習法上の規則となっていることがわかります(五八二頁)。
https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=3344585&id=43123435
(*15)横浜弁護士会BC級戦犯横浜裁判調査研究特別委員会著『法廷の星条旗─BC級戦犯横浜裁判の記録』 日本評論社 2004年7月
(*16)ポツダム宣言 wikiより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%A0%E5%AE%A3%E8%A8%80
ポツダム宣言(ポツダムせんげん、英: Potsdam Declaration)は、1945年(昭和20年)7月26日にイギリス首相、アメリカ合衆国大統領、中華民国主席の名において大日本帝国(日本)に対して発された、全13か条から成る宣言である。正式には日本への降伏要求の最終宣言(Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって、「米英支三国共同宣言」ともいう。
他の枢軸国が降伏した後も交戦を続けていた日本は、1945年8月14日にこの宣言を受諾し、1945年9月2日に調印・即時発効(降伏文書)に至って第二次世界大戦(太平洋戦争)は終結した。
ソビエト連邦は後から加わり追認した。
(*17)東京大学名誉教授 大沼 保昭(国際法)『講演会「東京裁判 ──国際政治と国際法の立場から──」 東京裁判──歴史と法と政治の狭間で──』
P.23 下段3行目
ただし、侵略戦争が違法であることと、その戦争指導者が個人的に刑事責任を問われることは別問題です。違法と犯罪は異なる概念であって、ニュルンベルク裁判、東京裁判の実体法で初めて指導者責任観が戦争違法観と結びついたのです。ですから、侵略戦争の犯罪という訴因で日本の指導者を裁いたことは国際法上合法と言い難い。このことは確認しておきたいと思います。
(*18)多谷千香子著『戦争犯罪と法』 岩波書店 2006年12月5日
P.64
しかし、ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰すべき旨の規定はない。
損害賠償義務については、ハーグ陸戦法規3条が、「ハーグ陸法規の規定に違反した交戦国は、事件に応じて、損害賠償の義務を負う。交戦国は、軍隊の構成員によって犯されたすべての行為に責任を負う」と規定している。
それなら、どのようにして、これらの違反が個人の犯罪として処罰されるようになったのだろうか、それは、以下のとおりである。
ハーグ陸戦法規で禁止される行為は、1907年に同条約ができて初めて国際的に禁止行為として認知されたものではなく、それ以前から国際慣行として守られてきた戦争のルール及び国際人道法に違反する行為であった。つまり、条約は、ルールの新設ではなく、慣行の確認にすぎなかったが、条約が締結されて処罰するようになった。この時点では他国の裁判所や国際的な刑事裁判所が、世界管轄のもとに戦犯を処罰することはなかったが、ニュルンベルク裁判では、「文明国では、ハーグ陸戦法規は、(筆者注:個人の犯罪として処罰することが)1939年から(筆者注:第二次世界大戦開戦当時から)国際慣習法として確立している。ニュルンベルク条例は、この国際慣習法を確認したものにすぎない」とされ、国際的な刑事裁判所であるニュルンベルク裁判所で戦犯を処罰するために適用された。
ニュルンベルク裁判所での「ハーグ陸戦法規は、1939年から国際慣習法として確立している」という解釈には、異論もないわけではない。しかし、伝統的な戦争犯罪を国際的に処罰しようという動きは、第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約の当時から存在し、ニュルンベルク条約が初めてではない。したがって、それからはるかに時代の下った第二次世界大戦当時には、そのような考え方は多くの国に広く受け入れられ、国際慣習法として確立しており、異論はとるにたらないという議論には説得力がある。
仮に、この異論が正論だとしても、ニュルンベルク条例の内容は、早くも1950年に国際法委員会(ILO)によってニュルンベルク原則として定式化され、国連総会で採択されて多くの国に受け入れられている。したがって、少なくともそれ以降は、国際慣習法として確立していることはまちがいなかろう。
(*19)加藤一郎『ニュルンベルク国際軍事法廷憲章批判』(『教育学部紀要』文教大学教育学部 第36集 2002年)
さらに、もとをたどると、ニュルンベルク裁判の法的根拠であるロンドン協定には、アメリカ検事ジャクソン、フランス予備裁判官ファルコ、ソ連検事ニキチェンコが署名している。このことは、ニュルンベルク裁判が、立法者、検察官、裁判官を兼ねることを禁じた「司法権力の分割」という根本原則からまったく逸脱していたことを意味している。
ロバート・ジャクソン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3_(%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%B6)
(*20)清水正義『第一次世界大戦後の前ドイツ皇帝訴追間題』」『白鴎法学』第十九号
例えば、オーストラリア首相ヒューズは「彼[前皇帝]には世界を戦争に突っ込ませる完全な権利があるのです。今、我々は勝利をした。だから彼を殺す完全な権利がありますが、それは彼が世界を戦争に突っ込ませたからではなくて我々が勝ったからです。法律違反で彼を訴追するなんて、首相、それはできませんよ」と率直に語り、ロイド・ジョージを牽制すると、軍需相チャーチルも呼応して、「前皇帝を絞首刑にするという道を意気揚々と開始するのは易しいし、大衆の一般的関心をその中に取り入れることもできる。けれど、時が過ぎてやがて大変な袋小路に陥ってしまうことになるでしょう。世界中の法律家たちがこの起訴状はとても支えきれるものではないことに気がつき始めるでしょう」と非常に消極的な姿勢に終始した。
(*21)多谷千香子著『戦争犯罪と法』 岩波書店 2006年12月5日
P.55 2行目
(3)アメリカのICCの対策法
(i)「ハーグ襲撃法」
アメリカは、ICC発行に備えて、American Servicemembers Protection Act od 2002 を、2002年1月23日に制定した。これは「ハーグ襲撃法」とあだ名され、「アメリカは、ハーグの拘置所からアメリカ人を奪還するため、直接的な武力行使に訴えるつもりなのか」とオランダの人々を驚かせた。
アメリカは、そのようなことを考えているわけではないと説明しており、同法の内容は、以下のとおりである。
①アメリカがICCと協力するのを禁止する。協力とは、例えば、連邦裁判所をはじめとする合衆国及び州の政府機関が、ICCの協力要請に応じて、捜査・引き渡し・秘密情報の提供・調査回答などをすることである。ただし、後に、ICCがアメリカの敵国についての事件を扱っているときには、協力することが出来るように改正された。
②アメリカ軍人などがICCに身柄を拘束されているときには、その身柄を自由にするため、すべての必要かつ適切な手段を行使する権限(筆者注:ハーグ襲撃法とあだ名される所以であるが、明文では「すべて必要かつ適切な手段 all means necesasary and appropriate」になっていて、軍事的手段とは書かれていない)を大統領に付与する。
③NATO諸国、その他の同盟国、及びアメリカ国民をICCに引き渡さない旨の98条合意(後述)を締結した国を除いて、ICC締結国には軍事援助しない。
(ⅱ)98条合意=アメリカ人不引渡しの合意
アメリカは、SC決議1422 及びハーグ襲撃法に念をおすように、ICC締結国となった各国に大使を派遣し、いやしくもアメリカ人をICCに引き渡すことがないよう、合意をとりつけようとしている。
なお、ICC Statute 98条は、免責特権を有する外交使節の引き渡しを禁じる国際法上の義務に背くこと、又はその他の条約上の義務に背くことを被要請国に強いることになるときは、ICCは引き渡し要請をしない旨、規定している。同条は、軍人の地位協定、外交使節についての合意、犯罪人引き渡し条約に言及したもので、これらの目的にのみ使うことができ、一般的にある国の国民(例えば、アメリカ人)をICCに引き渡すことを禁じるためには使えない。したがって、98条合意は、Icc Statute 98条に沿うものではないが、形式的文言を借りているため、そのように呼ばれる。
98条合意は、アメリカも98条合意相手国に対して同様の義務を負う双務的な場合もあるが、片務的合意もある。98条合意の締結方法は、98条合意を結ばなければ、軍事援助及び経済援助をストップするという強引なものである。
なお、98条合意の要点は、以下の通りである。
①アメリカの現役又は軍人・役人、アメリカに雇われた人(外国人をふくむ)、アメリカ人を、ICCに引き渡すことを禁じる。
②引き渡さなかった場合、アメリカ国内での捜査・訴追は、必ずしも義務ではない。
(*22)南シナ海判決
南シナ海判決(みなみシナかいはんけつ)では、1982年の国連海洋法条約附属書VIIに基づく南シナ海問題に関するフィリピン共和国と中華人民共和国の仲裁裁判(英語: Matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China)、通称、南シナ海仲裁裁判 (-ちゅうさいさいばん、英: South China Sea Arbitration)の判決(裁定)について説明する。
この事件は、中華人民共和国が、海域や島々の領有権を有すると主張してきた、いわゆる九段線[2]に囲まれた南シナ海の地域について、フィリピンが国連海洋法条約の違反や法的な根拠がない権益の確認を常設仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁裁判である。
櫻井よしこ著 『仲裁裁判所判決を「紙くず」 無法中国への最大の反撃』 月刊Hanada 2016年9月号 オピニオンサイトiRONNA https://ironna.jp/article/4466
引用
《
彼らは、当初から仲裁裁判による解決を拒絶しており、当然のことながら、この判決にも激しく反発している。中国外務省は十二日、「法的拘束力のない判決を受け入れることはない」 「中国の権利を著しく侵害した」とする声明を発表、中国政府も「南シナ海における活動は二千年以上の歴史がある」と主張した。
[中略]
〈中国には、領土問題について歴史的に欧米主導の国際法体系から「被害を受けた」という潜在意識がある。中国は近代史の中で領土や権利を失ってきたが、いずれの場合にも条約があり、「合法的」とされてきた。既存の国際法が形成される過程で、中国の意見はほとんど反映されなかった〉
[中略]
だが、中国は国連海洋法条約(UNCLOS)を批准した。批准したからにはそのルールを守らなければならないというのが、私たちの原理原則である。批准によるメリットを受けながら、一方で自国に不利な部分のみ無視する勝手は許されない。中国はそうした西側陣営の基本的価値に真っ向から挑戦しているのである。
》
(*23)クリミア危機・ウクライナ東部紛争 wikiよりhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%A2%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E6%9D%B1%E9%83%A8%E7%B4%9B%E4%BA%89
クリミア危機・ウクライナ東部紛争[2]は、2014年2月下旬に発生したウクライナ騒乱以後、クリミア半島(クリミア自治共和国)とウクライナ本土の東部2州(ドネツィク州とルハーンシク州)で起こっているウクライナ政府軍と、親ロシア派武装勢力や反ウクライナ政府組織、ロシア連邦政府・軍との紛争(軍事衝突や対立)である。
ウクライナ系メディアでは、ロシアの正規軍の関与が広く見られることからロシアによる侵略、ロシアによる占領、またはウクライナ・ロシアの戦争と呼んでいる。ポロシェンコ大統領もしばしば現状説明として「ロシアとの戦争」という用語を用いる。ただしウクライナ、ロシアともに宣戦布告は行っていない。一方、ロシア系メディアでは、この紛争初期にはロシアの春と表現する場合もあったが、以降は「ロシア軍は関与していない」との立場から、今次紛争をウクライナ国民同士の対立であるウクライナ内戦であると表現している。他方で、欧米諸国からは、派兵や兵器・燃料の供給をはじめ、ロシアの直接的関与は明白だとして、対露制裁を科すなどの措置を取っており、「内戦」という用語は用いず、代わりに紛争、占領、侵略、軍事侵攻等の用語を使用する。
クリミア自治共和国では、衝突初期の2014年2月下旬-3月にかけて行われたロシアによる軍事干渉と、国際的な非難を浴びながら行われた住民投票の結果、同年3月17日にロシアへの編入を求める決議を採択したと宣言。ロシア軍の支配下に置かれ、さらにロシアへの編入が宣言された。その後、ウクライナ本土の東部2州(ドネツィク州、ルハーンシク州)での抗議運動が、武装した分離主義勢力による反乱へと広がった結果、ウクライナ政権が軍事的反攻に乗り出すことになった。
参考文献・論文
【論 文】
清水正義『第一次世界大戦後の前ドイツ皇帝訴追間題』
廣峰正子『民事責任における抑止と制裁(2・完)─フランスにおける民事罰概念の生成と展開をてがかりに』
山田卓平『国際法における緊急状態理論の歴史的展開』
松宮孝明『罪刑法定の原則と刑法の解釈』
小梁吉章『19世紀国際私法理論にいう「文明国」基準』
ミッチェル=バイヤーズ『慣習・権力そして法制定権力─国際関係と慣習国際法』
山内進『明治国家における「文明」と国際法』
竹内雅俊『国際法学における『文明の基準』論の移入』
桧山幸男『明治憲法下における戦時規定について』
小林好信『戦時下の刑法学についての覚書』
清水隆雄『テロリズムの定義─国際犯罪化への試み』
伊藤哲朗『国際刑事裁判所の設立とその意義』
福王守『『法の一般原則』概念の変遷に関する一考察国内私法の類推から国内公法の類推へ』
フィリップ・オステン『東京裁判に於ける犯罪構成要件の再訪』
内海愛子『東京裁判と捕虜問題』
神山晃令『国際労働機関(ILO)との協力終止関係史料』
石田清史『近代日本に於る参審の伝統』
本田稔『ナチスの法律家とその過去の克服』
永井均『日本のおける東京裁判研究の動向』
福井康人『国際刑事法の発展の歴史』
加藤一郎『ニュルンベルク国際軍事法廷憲章批判』
小池政行『国際人道法とは何か』
舘川知子『戦争犯罪について』
中立悠紀『東京裁判観_新聞・論者』
長島友美『東京裁判と国家主権の関わりについて』
斎藤洋『現代国際法社会における東京裁判の意義』
島田征夫『東京裁判と罪刑法定主義』
日暮吉延『東京裁判と国際政治』
大谷保昭『東京裁判と国際法』
アスキュー・デイヴィッド『占領下南京研究序説─道徳言説の脱却を目指して』
孟国祥『南京大虐殺事件に関する審判』
西 平等『Ⅶ 市民社会の敵・国際社会の犯罪者─テロリストの法的地位に関する法思想史的考察』
北村稔氏論文『東京裁判にみる誣告と事後法」
中原精一『国際法と国内法の関係』
【文献】
立作太郎『戦時国際法論』1944年
信夫淳平『戦時国際法講義 第2巻』
信夫淳平『国際法』
信夫淳平『国際政治論叢』第2巻
拓務大臣官房文書課編『外地に行はるる法律調』
木原正樹『「国際犯罪」としての侵略:国家責任法および国際刑法の法典化の歴史的および理論的検討』
【パンフレット】
佐藤和男『国際法の観点から考える東京裁判』
WW1_同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約及附属議定書
極東国際軍事裁判(東京裁判)の欺瞞性についての法的検証
国際刑事裁判所に関するローマ規定
国際法の学び方
Rule-of-Law-A-guide-for-politicians-Japanese『法の支配 政治家のためのガイド』
【講演映像】
寺谷広司「国際社会における悪と法」ー東京大学 公開講座「悪」2015 https://youtu.be/jEIglkyIQM4











![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)
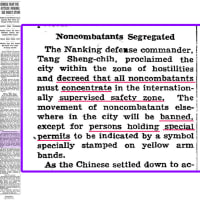

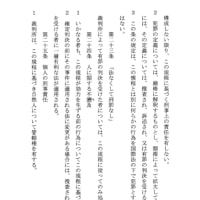

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます