
その1からの続き
- 戦争での殺傷を、平時の【殺人】などの【非道行為】と一線を画す必要があるのは言うまでもない。
- 平時に於ける【サイコパス・ソシオパス】などが行うような、【拷問・快楽殺害】とは違うことも明らかである。
- 【法令違反】=【犯罪】かどうかである。
- 【戦争法規違反】とは【国家間】の【違約】であって、【刑法】でいう軍隊構成員の【個人】の【犯罪】でも無く又【国家】の【犯罪】でも無い。
- 【戦時国際法】には、【旧軍人】を【裁く】という【刑法】は存在しない。
- 【占領政策】の【軍律審判】は、【軍事行動・行政執行】であって【刑法】による【処罰】では無い。
ハーグの陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約/1911年)には【第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。(当方補記:当事者としてあるが:当事者は国家のことである。)(*10)】とあるように、例え【違反】としても【犯罪】でも無く、飽く迄も【賠償】の対象である。
支那事変の12月12日の揚子江を漢口へ遡上する避難船団に同行していた米国砲艦パネイ号と英国砲艦のレディーバード号への攻撃に関する中立国の軍艦への攻撃という【陸戦法規違反】が発生したが、その解決は【賠償】だった(*11)。そして【該当】の日本国兵士は、米国及び英国に引き渡されて【戦争犯罪人】として何等かの【刑罰】を受けることはなかった。【陸戦法規慣例規則】を【違反した又は違反の疑惑のある敵側構成員】を【軍律審判】などの手続きを経ずして【殺傷】した者を【犯罪】として裁く国外・国内法での【法】および【罪刑】は存在しない。
当時は、【陸戦法規慣例規則】は、【行為規範】であって【裁判規範】ではなかった(*12)。そして【違反】=【犯罪】では無いと言う事である。
【国際法】には【戦時重罪人】という軍隊構成員による交戦法規違反、文民による武力敵対行為、スパイ、戦時叛逆、剰盗などがあり、原則として戦闘行為中に於ける敵側の行為に対して、戦争犯罪人、戦争重罪人などというものが国際慣例上概念として存在し、敵対国軍に鹵獲された場合には敵対国(敵国占領地)の【軍律審判】などで裁かれ処罰・処刑されている。【軍律審判】と【通常裁判】の司法を混同されることが往々にしてあるが、【軍律】とは占領軍の司令官が制定した占領地の住民に対する【一時的な規則】であり、軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則で自治体で制定する条例と同様であり、【刑法】ではなく【軍事行動】又は【行政執行】である。又、【戦闘期間中の講和締結前までの占領期間中に鹵獲された敵兵や非戦闘員】に【一時的】に適用される行為で、【軍律審判】による処置は、戦争法規を犯して敵対行為を働く者は軍律に於ける軍律違反による軍罰が科せられる【国際法の保護】を受けない敵国軍人や占領地域住民の違法な敵対行為が対象となり、軍律で定めた【刑罰法規】で処断し得た。これが軍律審判であり、又は軍律会議である。【国際慣習法上認められて】来たものであり、占領や安全確保、作戦用兵上の必要に基き、軍が自ら定めることが出来る【軍事行動・戦争行為】である(*13)。軍律が【法】としての一面はあるとしても、【軍事行動・戦争行為】という【一時的なもの】であることは留意する必要があり、本来ならば講和締結と同時に【アムネスティ条項】により生きていた場合は、恩赦となり刑罰対象者ではなくなる(*14)。当然の事ながら、【犯罪者】という【前科者】でも全く無い。
戦後、BC級戦犯を裁いた横浜裁判(*15)においても、【戦争犯罪人】として【無差別爆撃】を行った【陸戦法規違反】として、日本国内で鹵獲された撃墜された爆撃機の米国人空軍兵士が、【軍律裁判を行う】又は【軍律審判せず】に処刑されているが、横浜裁判では【手続き】や【捕虜の権利の有無】や【捕虜の権利としての弁護人の選任】などがなかったことについてが【合法・違法】かが争点であったが、占領期での【行為】でもない過去の日本軍の【行為】をその後の米国が軍事委員会自体が運営・裁判出来るかどうかと言うことがそもそも国際法として慣習法として成立していたものでも認められているものでは無かった。
1945年8月14日にポツダム宣言(*16)を受諾し、【武装解除した】日本軍全体の降伏後の戦闘終結以後に【裁判受け入れ】て、占領政策中での【武装解除して】帰順を示している旧日本軍人・軍属・一般人を【陸戦法規違反】を【戦争犯罪人】として構成員の【個人】を裁くことが国際慣例として当時成立していなかった。少し脱線するが、そもそも、戦勝国側は侵略戦争は違法だと糾弾して開いた裁判だが、国際法学者の(故)大沼保昭東京大学名誉教授も、《侵略戦争の犯罪という訴因で日本の指導者を裁いたことは国際法上合法と言い難い。このことは確認しておきたいと思います。》と講演会の中で述べている。(*17)
この事の意味することは、1937年の上海事変及び南京攻略戦に於いて、日本軍の【陸戦法規】への【違反】が【犯罪】とは言いがたく、ニュルンベルグ法廷憲章で例え決まったとしても、【罪刑法定主義】という【文明社会】の【前提条件】からは、【文明の裁き】と言うものでは無く、【単なる戦勝国側の報復】という中世以前のまさにアッチラの如く【蛮行】を犯したことと同様である。
また、南京攻略戦の【蛮行】として引き合いに出される【捕虜の処遇】についても、田岡良一著『新版 国際法Ⅲ』347-348頁において、ハーグ附属文書23条d項(助命拒否の禁止)について、ウェストレーク(John Westlake:英国の国際法学者)を引用して《この規定が実行不可能な場合として一般に承認されているのは、戦闘の継続中に起こる場合である。このとき投降者を収容するために軍を停め、敵軍を切断して突撃することを中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、時として危うくされるであろう。のみならず戦闘の継続中には、捕虜をして再び敵軍に復帰せしめないようんに拘束することが実行不可能な場合が多い。》とし、助命拒否が承認される場合があることを認めている。これは明確な規定がない為、柔軟性のあるもので、オッペンハイムも「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は緊急必要の場合において(in c-se of imper-tive necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害されて、軍自身の安全が危うくされる場合にはおいてである。」
戦時於ける戦闘状態によっての曖昧な規定であり、それをもって【犯罪】と認定することは不可能である。
米国の軍事委員会は(Military Commission、Military Tribunal)、軍律審判と論理的に同じとするならば、アムネスティ条項により講和後は【戦犯】に対する大赦であり、【戦犯】などは、1952年のサンフランシスコ条約以降は存在しなくなるはずだったが、実際にはそうは成らなかった。
南京城陥落後の占領の過程での、敗残兵摘出とその処刑行為が、この軍律審判を経ずに処刑されたことに対して、国際法違反を主張しているのは、この軍律審判を経ないまま処刑したことが手続き緩和が許容されるものではなく国際法上違法であるという主張が為されるケースがあるが、【陸戦法規】は【刑法】ではなく、【合意・相互法】であって、当時日本国は捕虜条約を批准して居らず【条約】に拘束されていたわけではない。又、横浜のBC級戦犯裁判の様に、戦闘機の搭乗兵士が意図的に【便衣】となって逃走したと言う事でも無く、【捕虜】と成り得る前提条件としての【徽章(軍服・軍装)】の着用があり、南京での城内での【便衣と成って逃走・潜伏する敗残兵】の摘発とその後の処遇についてと【違う】ものと考える。
WW1以後、WW2までに国際連盟加盟国や米国と1917年にロシア革命で出来たソビエト連邦という共産国家も含めた国際社会で、第1次世界大戦後、国際連盟の機関として1921年に常設国際司法裁判所(PCIJ)がオランダのハーグに設置されて国際刑事の議論が成されたかというと、少しはあったようだが【テロ】への規制などであって【陸戦法規違反】や【戦争指揮官の犯罪】が【戦争犯罪】として裁く【定義や条約項目】の検討は成されなかったし、当時【陸戦法規違反】が【罰】を持つ【犯罪】への昇華は、【政治】に依るもので、何か議論を踏まえて決定された事項ではない単なる【報復処置】への【項目】であると言う事が判る。ニュルンベルグ裁判で《ニュルンベルグ裁判では、「文明国では、ハーグ陸戦法規は、(筆者注:個人の犯罪として処罰することが)1938年から(筆者注:第二次世界大戦開戦当時から)国際慣習法として確立してる。ニュルンベルク条例は、この国際慣習法を確認したものにすぎない」(*18)》という連合国という戦勝国連合側は主張した。しかし、これは【罪刑法定主義】の【司法概念】を継承するならば、【法の遡及】を無視した【犯罪規定】に関しては矛盾する行為である。又南京攻略戦は、1937年の事で、厳密に言えば【国際慣習法として確立していない】となり、それを【南京暴虐事件】として【訴因55】で敗戦後の占領下で軍人でもなかった松井石根大将・広田弘毅外務大臣が有罪判決を受けたのは将に【自分達】の【主張】を全く【無視】して【有罪】にしていると言うことになる。
極東国際軍事裁判でも、【文明国】という言葉が一つのキーワードになって居り、南京暴虐事件の裁判に於いても、検察が【アッチラの如く】と称したように、【日本軍】を【野蛮国家】と位置づけようとしたことは前述した通りでだが、当時の【戦争】への認識は、本来【決闘】という兵力を用いた【外交交渉】でこれを【無差別戦争観】と言い【正戦論】のことで、正当な戦いである。そして【規則】への【違反=犯罪】という考えは存在していない。当時の他国による【国際法違反】に対する【自力救済】の為の武力に訴えることは禁止もされていなかったことはその他の国家の状況を見るとあきらかである。これは日本の北方四島・拉致被害、ウクライナのクリミア半島、南沙諸島の状況を見れば、現代に於も【自力救済】がなければ、何等領土国民を回復・守り得ないことの証左である。
【戦争違法観】という話が出て来たのは、1928年(昭和3年)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本といった当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名し、その後、ソビエト連邦など63か国が署名した。フランスのパリで締結されたためにパリ条約(協定)(Pact of Paris)あるいはパリ不戦条約(通称:ケロッグ・ブリアン条約)である。飽く迄【前提(対手国の軍事・政治徴発)】の無い相手国への突然の軍事侵攻に関して問題にしているだけで。【戦闘行為という軍事力の行使】を【違法=犯罪】とした訳ではない。その上この不戦条約に於いても何が【自衛】で何が【侵略】かということは【明確に定義】はなされず、ケロッグは米国上院議会で、【経済制裁】を受ければ、それに対する武力の行使は【自衛】と判断出来るという見解を示している。又、イギリスは自国領内ではなく、海外領域にある自国権益に対する侵害も【徴発行為】となり【自衛】の為に【武力行使】を容認し得るものしている。この不戦条約ができて以降も【国際慣例】又は【国際慣習法】として、【戦争違法観】が国際社会で認知されていたかというと、米国のみが前のめりで、1932年の日本国への満洲の対応を【不戦条約違反】と「スティムソン・ドクトリン」で主張したが、これが国際法に於ける【国際慣習法】して成立したのではなく単に国際連盟の参加国でも無い米国1国の見解であって、米国はラテンアメリカに干渉をし続けた事で、ラテン・アメリカ不戦条約もパリ不戦条約同様の言葉だけだったと理解できる。又、ドイツがポーランドに侵攻したことは【侵略】と定義して非難された【開戦事由】にもなったが、当時同時にポーランドに【侵略】した【ソビエト連邦】が行った【罪】は【戦前も戦後】も問われたことがなく、【戦犯】として【個人】が【責任】を問われ、国際的な軍事法廷で裁かれたことはなく1991年12月に国家崩壊した。WW2まで【戦争違法観】が国際社会での国際慣例ではなかったということは、極東国際軍事法廷での前半の満洲事変から支那事変までの日本軍の行為そのものが単なる外交的【兵力を用いた交渉】であって、何か【文明国】から外れた【野蛮な行為】というわけではないと言うことが理解できる。
その上、極東国際軍事法廷憲章は、ニュルンベルグの【国際軍事裁判所憲章】から流用されたものであり、それ自体が、【立法者、検察官、裁判官分離の原則】を無視した事は、ニュルンベルグ裁判で検察官として告訴した米国の検察官ロバート・ジャクソンがこの憲章作成に関わっていたということは明らかになって居り、【司法】を無視したなものであることが判っている(*19)。日本国はポツダム宣言の10項により【裁判】を受け入れたが、それが【軍律審判】と考えて【罪刑法定主義の論理】から離れた【裁判】とは想定してなかったようで、【賠償】であって【個人を対象】とした【刑罰】とは考えておらず、対応が敗戦処理、人員、資金、資源の制約もあり戦勝国側よりも後手に回ったことは、【敗戦国家】の状況なら止む得ない状況と考えるのは普通の推察であろう。東京裁判でも、開始早々清瀬弁護士による裁判への動議について述べられていることを見ても日本側は、【文明国家の前提】【国際法】を理解し行動していたことになる。詳しくは冨士信夫氏著『私の見た東京裁判 上』をご覧戴きたい。有名な歴史著述家の秦郁彦氏がその著作『南京事件「虐殺」の構造』で、検察側の証拠が圧倒的だったという論拠を児島襄著『東京裁判』から引用した伊藤清弁護人の証言を使っているが、当時の環境・状況・時間を理解せずに、【平時】に於ける同レベルでの法廷争議と同一視するという余りにも軽率な考察をしている。
運用面で見ても、戦勝国という【連合国側出身の裁判官】などが多数を占め、中立性という面でも【裁判の公平性】も無く、何より【国際法】の専門家の学者は遅れてきたインドのパール判事のみで、人選にも国際法からではなく、【審理】もそれぞれの【主権国家内の法概念】が持ちこまれた【実験的】な裁判となった。それと重要な事は【通常裁判】ならば【伝聞証拠禁止の原則】や【偽証罪】が当然用いられるはずだが、その点も無視されているという【軍律審判】という面が都合よく使われている。横浜で行われたBC級を裁く裁判では、1946年の立法府再編法(Legislative Reorganization Act)によって設置された米国大統領直轄の組織である【軍事委員会 Military Commission】により裁判の運営が成された。これも又【軍律審判】と同様のもので、【審議】の運営そのものは、米国の【軍法】によって行われた【軍事行政】であり、通常の【司法】での【裁判】ではない。
東京裁判では、意外な事だが、オーストラリアのウェブ裁判長が【罪刑法定主義】の【法の遡及】に言及し他国の判事等に提議したが、イギリスの判事が多数派工作を行って議論を都合の良い方に捻子曲げた事実は余り知られてないようで、そもそも【戦争犯罪】を裁く事を主張したのが、1945年2月に行われた【違法】な戦勝国側の領土獲得を約束した密室のヤルタでの会談でイギリス首相のチャーチルが言い出した事を受けてのことである。チャーチルは軍需相だったWW1後の際、元ドイツ皇帝を裁くことに関して、「前皇帝を絞首刑にするという道を意気揚々と開始するのは易しいし、大衆の一般的関心をその中に取り入れることもできる。けれど、時が過ぎてやがて大変な袋小路に陥ってしまうことになるでしょう。世界中の法律家たちがこの起訴状はとても支えきれるものではないことに気がつき始めるでしょう」と語っているにも拘わらず、WW2後の際は変節している(*20)。
サンフランシスコで、日本は各国と講和条約を結び批准した。その際の第11条の【極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。】として事実上永久に【名誉を回復する為】の【上訴上告】を否定されるという【非人道的な条約】を結ばざるを得なかった。当然ながらポツダム宣言受諾の戦闘終結後80年近くになるという状況で人権に対する眼が厳しい現代に、この【人権を著しく害した不公正な条約】は今も解消されていない。東京裁判やマニラ裁判では再審が出来ず、横浜裁判ではBC級戦犯裁判は出来た。再審の機会も与えずに処刑したことの人権無視は許されるのか。【文明】をかかげて【正義】をかかげて、裁判を行った連合国側に何の正統性や正義があるとういう根拠はどこにも無いし、現在の法曹関係者・法律関係者に対してもこの【人権無視】に対して声を上げない、逆に【助長する】などの行為を行うことに対して、【法の公平・正義】に疑問を抱かざるをえない。このような事では【法の支配】とは一体どういうものかすら判らなくなる。
むしろ、このことは【文明国】を称する連合国側が、国際ならびに各種権国家内の【司法】の前提である、【罪刑法定主義】という【文明国】の前提から外れた【野蛮国】であると言う事を証明した事に外ならない。
戦後はこの【憲章】からの【戦争違法観】という【司法概念】が生き続け、後に【国際刑事裁判所=ICC(International Criminal Court)】での国際刑事裁判所ローマ規程へつながるが、現在2019年時点で、アメリカ、ロシア、中華人民共和国などの国際連合の常任理事国の内の主要国は非加盟国である。日本は批准・署名している。ICCの規定には、戦争犯罪が明文化されているが、米国のようにICCに自国の兵士、外交官、一般人を引き渡しを拒む関係国との98条合意=アメリカ人不引渡しの合意条約(*21)や、近年での【南シナ海問題】に関するフィリピン共和国が中華人民共和国に対する常設仲裁裁判所に提訴した問題の判決(*22)は、フィリピン側の主張がほぼ通り、中華人民共和国の主張は、退けられた判決であったが、その後中華人民共和国はどうしたかと言えば、現在も違法・不法に周辺一帯を【占拠】した状態である。これも上位権力機構のない主権国家の並立機関では、【パクタ・スント・セルヴァンダ、pacta sunt servanda】が原則かつ前提である証左である。【合意】や【司法判決】を守らせる為には、【強制力】としての【軍事力】の存在が欠かせない。現在ではダントツトップの軍事力を誇る米国やそれに追随して他国を圧倒する軍事力を持つ中華人民共和国に、【合意】や【司法判決】を守らせるなどとと言うことは出来ない。そして現在もウクライナの東部及びクリミア紛争のようにロシア国の違法占拠(*23)、北朝鮮による日本国民の拉致被害、日本領土の千島列島・北方四島への違法占拠。韓国の日本国領土である竹島への違法占拠などがある。
日本の司法関係者は、東京裁判での司法について【意義】だけを【主張】され、何か素晴らしい進歩があったかように喜んで居られる方が大多数のようだが、実際問題として、その後の【司法】と【法の支配】等というものは、国際社会の利害関係に於いて【形骸化】【無視】【無効果】になっているのが現状である。
国際社会で【法の支配】が行きわたるには、上位権力が無い状態では、絵に描いた餅で、国家の持つ軍事力次第となる、その他の国際社会が何等【問題解決を先延ばし】又は【解決しない】とするだけで、何等【解決出来る手段】を提示出来ていない。そして【国際法】などの【法の支配】を言及する【法律家】の方々は、【解決】に向けて何等出来ること【皆無】【無力】と言っても過言ではない。
その3に続く











![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)
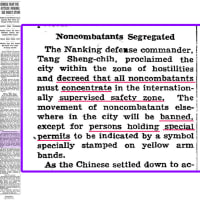

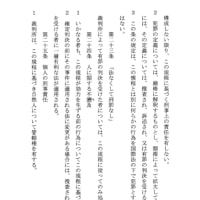

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます