10月6日川崎市麻生市民館にて管楽器によるオーケストラで演奏会を開催致しました。無事開催できましたのもご来場いただきました皆さま並びに関係各位おかげでございます。厚く御礼申し上げます。
今回の演奏会では、ドビュッシーの小組曲、ラフマニノフのヴォカリーズ、そしてメインプログラムとして、ブルックナーの交響曲第4番『ロマンティック』を演奏致しました。
一週間前の最後の全体練習が台風のためキャンセルとなるというアクシデントがあり、本来、最後にいろいろ確認すべきことができなかったこともあり、みんないつも以上に不安と緊張があったと思います。
私個人的には、それに加えて、リハーサル前にホールでの音の感覚に馴染もうとしていました。少しでも不安を払拭すべく、少ない時間の中、いつも以上に焦りを感じながら、時間ぎりぎりまで自分自身の課題やセクションでの合わせを繰り返し練習していました。
そしてリハーサルが始まりました。単に演奏のきまりごとを確認するだけでなく、本番前にも関わらず大山先生の指揮も熱を帯び、また、エキストラの方を含め演奏者一同必死についていきました。最後の全体練習ができなかった分を取り戻すそうと頑張り、「なんとかこれでいける」という確信のようなものがみんなの心に芽生えたのではないでしょうか。
私は、リハーサルが終わってから本番前のわずかな時間も、少しでも楽器に触れていたい気持ちを抑えられず、気持ちを集中させ最後のおさらいをしていました。出演者の皆さんも各自集中力を高めていたと思います。
いよいよ本番開始のブザーが鳴り、舞台へ。
大山先生のタクトが動き、曲が流れ始めます。
最初の曲はドビュッシーの小組曲です。ドビュッシーはフランスの人です。フランス音楽は概してドイツ音楽とは違った感性が求められます。練習では、指揮者の大山先生からそれらについて学びました。曲によって、波のように流れる感じや、ダンスのような軽快なリズムなど雰囲気も異なります。私自身はリズムの感じ方や流れるような曲想に注意して演奏を心がけました。何より最初の曲ということで、音の出だしから練習通りに演奏できるように心を配りながら取り組みました。
この曲の美しいフレーズから来る様々な印象がお客様まで届いていれば幸いです。
続いてヴォカリーズです。この曲は木管楽器中心の演奏で、金管楽器の私は舞台袖で聞いていました。個人的な印象では、どことなくせつなげでありながらしっとりとした美しさを持っているように思います。皆が気持ちをひとつにして演奏できたように思います。
続いて、15分の休憩です。出演者の皆さんは舞台袖などで思い思いに過ごしていましたが、私はこの休憩の間、次の曲の全体像のイメージを思い浮かべながら、一方で自身の技術的な課題を心の中で確認していました。
いよいよ、第2部のロマンティックが始まります。
静かな弦楽器パートのささやきの後にホルンのフレーズが現れ弦や木管が受け継いで盛り上がった後に金管の力強いフォルテシモが現れます。そうなるとブルックナーの圧倒的な世界観に打ちのめされます。そこからは一気に曲の中に入り込んでしまいました。
各楽章の曲想についてはこれまでの練習日記にいろいろと書いてありますが、楽章ごとにいろいろな風景が見えることと、曲全体を通して宇宙を感じさせるような壮大な世界観、そして何より曲名の通りの「ロマンティック」な印象は来て頂いた皆さまの心の中にお届けできたのではないでしょうか。
ロマンティックは比較的長い曲でスケールの大きな曲であるにも関わらず、実際吹いてみると、あっという間に終わってしまいます。終楽章の終わりに近づいてくると、曲が盛り上がって興奮してくるにもかかわらず、終わって欲しくない、もっと吹いていたい、といった気持ちになります。演奏会が終わってしまったら、長い間練習してきたロマンティックも一区切かと思うと寂しさも込み上げてきます。まだまだブルックナーの深さを探ってみたい、そんな気持ちになります。
正直に告白すると、今回のロマンティックがこれまでの演奏した曲の中で一番不安と緊張にかられた曲でした。でも、本番の時は一番演奏を楽しめたと思います。自分が吹いている、いないに関わらず、この曲の壮大さを味わいつつ、一方で、不安な気持ちを楽しむような冷静さを曲の終わりまで持ち続けることができました。くじけそうになる気持ちを追い払うような、臆しない気持ちが必要なんだなぁ、と改めて気付かされました。むろん普段の練習と勉強が重要なのは言うまでありませんが。普段練習不足の私としては、これからは一回一回の練習に集中して取り組んでいきたいと改めて思いました。
まだまだ勉強中の団体ですが、今回も皆が心を一つにして、他にはないグレイスシンフォニーオーケストラならではの演奏ができたのではないかと思います。
ご来場頂いた皆さまの心の中に、作曲者の、そして演奏者の気持ちが少しでも伝われば望外の幸せです。
常に進化し続ける団体というのが我がグレイスシンフォニーオーケストラのモットーです。まずは今回の録音を聞いて反省するところからスタートすることでしょう。そこから勉強です。次回演奏会ではさらに向上した私たちをお見せできるのではないかと思います。
次回演奏会も是非お越し下さいませ。
テューバK
今回の演奏会では、ドビュッシーの小組曲、ラフマニノフのヴォカリーズ、そしてメインプログラムとして、ブルックナーの交響曲第4番『ロマンティック』を演奏致しました。
一週間前の最後の全体練習が台風のためキャンセルとなるというアクシデントがあり、本来、最後にいろいろ確認すべきことができなかったこともあり、みんないつも以上に不安と緊張があったと思います。
私個人的には、それに加えて、リハーサル前にホールでの音の感覚に馴染もうとしていました。少しでも不安を払拭すべく、少ない時間の中、いつも以上に焦りを感じながら、時間ぎりぎりまで自分自身の課題やセクションでの合わせを繰り返し練習していました。
そしてリハーサルが始まりました。単に演奏のきまりごとを確認するだけでなく、本番前にも関わらず大山先生の指揮も熱を帯び、また、エキストラの方を含め演奏者一同必死についていきました。最後の全体練習ができなかった分を取り戻すそうと頑張り、「なんとかこれでいける」という確信のようなものがみんなの心に芽生えたのではないでしょうか。
私は、リハーサルが終わってから本番前のわずかな時間も、少しでも楽器に触れていたい気持ちを抑えられず、気持ちを集中させ最後のおさらいをしていました。出演者の皆さんも各自集中力を高めていたと思います。
いよいよ本番開始のブザーが鳴り、舞台へ。
大山先生のタクトが動き、曲が流れ始めます。
最初の曲はドビュッシーの小組曲です。ドビュッシーはフランスの人です。フランス音楽は概してドイツ音楽とは違った感性が求められます。練習では、指揮者の大山先生からそれらについて学びました。曲によって、波のように流れる感じや、ダンスのような軽快なリズムなど雰囲気も異なります。私自身はリズムの感じ方や流れるような曲想に注意して演奏を心がけました。何より最初の曲ということで、音の出だしから練習通りに演奏できるように心を配りながら取り組みました。
この曲の美しいフレーズから来る様々な印象がお客様まで届いていれば幸いです。
続いてヴォカリーズです。この曲は木管楽器中心の演奏で、金管楽器の私は舞台袖で聞いていました。個人的な印象では、どことなくせつなげでありながらしっとりとした美しさを持っているように思います。皆が気持ちをひとつにして演奏できたように思います。
続いて、15分の休憩です。出演者の皆さんは舞台袖などで思い思いに過ごしていましたが、私はこの休憩の間、次の曲の全体像のイメージを思い浮かべながら、一方で自身の技術的な課題を心の中で確認していました。
いよいよ、第2部のロマンティックが始まります。
静かな弦楽器パートのささやきの後にホルンのフレーズが現れ弦や木管が受け継いで盛り上がった後に金管の力強いフォルテシモが現れます。そうなるとブルックナーの圧倒的な世界観に打ちのめされます。そこからは一気に曲の中に入り込んでしまいました。
各楽章の曲想についてはこれまでの練習日記にいろいろと書いてありますが、楽章ごとにいろいろな風景が見えることと、曲全体を通して宇宙を感じさせるような壮大な世界観、そして何より曲名の通りの「ロマンティック」な印象は来て頂いた皆さまの心の中にお届けできたのではないでしょうか。
ロマンティックは比較的長い曲でスケールの大きな曲であるにも関わらず、実際吹いてみると、あっという間に終わってしまいます。終楽章の終わりに近づいてくると、曲が盛り上がって興奮してくるにもかかわらず、終わって欲しくない、もっと吹いていたい、といった気持ちになります。演奏会が終わってしまったら、長い間練習してきたロマンティックも一区切かと思うと寂しさも込み上げてきます。まだまだブルックナーの深さを探ってみたい、そんな気持ちになります。
正直に告白すると、今回のロマンティックがこれまでの演奏した曲の中で一番不安と緊張にかられた曲でした。でも、本番の時は一番演奏を楽しめたと思います。自分が吹いている、いないに関わらず、この曲の壮大さを味わいつつ、一方で、不安な気持ちを楽しむような冷静さを曲の終わりまで持ち続けることができました。くじけそうになる気持ちを追い払うような、臆しない気持ちが必要なんだなぁ、と改めて気付かされました。むろん普段の練習と勉強が重要なのは言うまでありませんが。普段練習不足の私としては、これからは一回一回の練習に集中して取り組んでいきたいと改めて思いました。
まだまだ勉強中の団体ですが、今回も皆が心を一つにして、他にはないグレイスシンフォニーオーケストラならではの演奏ができたのではないかと思います。
ご来場頂いた皆さまの心の中に、作曲者の、そして演奏者の気持ちが少しでも伝われば望外の幸せです。
常に進化し続ける団体というのが我がグレイスシンフォニーオーケストラのモットーです。まずは今回の録音を聞いて反省するところからスタートすることでしょう。そこから勉強です。次回演奏会ではさらに向上した私たちをお見せできるのではないかと思います。
次回演奏会も是非お越し下さいませ。
テューバK












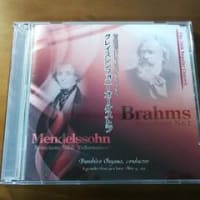
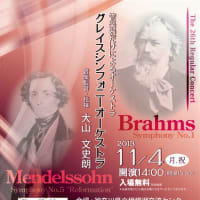




台風に見舞われたりして、マイナス要因はありましたけれども、全員で乗り切ることが出来たと思っています。
人生初のブルックナーでしたので、自分の集中力を高めるというところが難しかったですが、今後の自分の演奏にも活かせると思いますし、毎週の音楽監督の指導をよく聴いて前に進みたいと思っております!
Kさんの、ff は、すごく良い音でした!
台風に阻まれ、最後の練習は中止になったりと色々ありましたが、全員が全力で臨んだ演奏会だったと思います。
個人的には、積み重ねることの大切さを改めて感じた演奏会でもありました。
早いもので演奏会より1週間経ちましたが、テューバKさんの演奏会後記を何度も読み返し、
個人的な面でも振り返り、この気持ちをモチベーションとしてスタートしています。
一回一回の練習を大切に!着実に進んでいこうと思います。