2011.3.15東京台東区、
『ヨウ素131+ヨウ素132』1,170,000,000μBq/m3が降り注いでいた!
CTBTデータにある最大値である3月16日と比較しても、桁が1・2つ違う、
まさに桁違いの量の放射能が東京に降り注いでいた
http://onihutari.blog60.fc2.com/blog-entry-47.html より(引用開始)
■ 小出裕章氏が計測した3月15日東京の大気中放射能濃度
小出裕章氏(京都大学原子炉実験所助教)が東京台東区で、
これまでに最も放射能濃度が高かったと思われる3月15日に大気中放射能濃度を計測していた。
それによると台東区の大気中放射能は以下のようになっていた。
テルル132:570 Bq/m3(570,000,000 μBq/m3)
ヨウ素131:720 Bq/m3(720,000,000 μBq/m3)
ヨウ素132:450 Bq/m3(450,000,000 μBq/m3)
セシウム134:110 Bq/m3(110,000,000 μBq/m3)
セシウム137:130 Bq/m3(130,000,000 μBq/m3)
群馬県高崎市にあるCTBT観測所のデータにはこの3月15日の分が欠落している。
計測ポイントが違うので一概に比較はできないが、
CTBTデータにある最大値である3月16日と比較しても、桁が1・2つ違う、
まさに桁違いの量の放射能が東京に降り注いでいたというわけだ。
3月19日以降の分しか公表されていない文科省の降下量データが
全体の降下量をいかに過小評価しているか、
ここからも推し測れるだろう。
原発利権政府は「パニックを防ぐ」などといった
バカげた口実でWSPEEDIを隠蔽することで、
このすさまじい量の放射能で多くの人が被曝することを黙ってみていたというわけだ。
(引用終了)
政府統計で隠されている事実:
キセノン133・テルル132・ランタン140など日本で検出、
千葉で地表に1.4Ci/km2のセシウム137:依然公表されないWSPEEDI
http://onihutari.blog60.fc2.com/blog-entry-47.html より(引用開始)
■ 千葉でセシウム137の地表蓄積が53000Bq/m2(チェルノブイリ第三汚染地域クラス)、キセノン133・セシウム136・テルル129/132なども検出
千葉県にある財団法人・日本分析センターがおこなった大気中濃度の測定によると、3月14日から22日までの間、キセノン133が通常値0.001Bq/m3の130万倍にあたる1300Bq/m3に急増していたことが分かった。その後キセノン133は減少しているが、4月中旬時点でも通常の600倍近い水準となっている。またその他にも大気中からクリプトン85・ヨウ素132・テルル129・テルル132などが検出された。観測地点は千葉市にある同センター敷地内である。なおプルトニウムやウランは同センターでも観測自体が行われていないとのこと。
また同センターがおこなった放射性物質の土への蓄積量の測定によると、4月14日の時点で、小石混じりの土の表面にはヨウ素131が約48000Bq/m2、セシウム134・137が各53000Bq/m2、セシウム136が1000Bq/m2以上検出された。また腐葉土の表面にはヨウ素131が16000Bq/m2、セシウム134・137が各26000Bq/m2蓄積していた(正確な数値は日本分析センターに問い合わせた)。また地中5センチの土からも放射能汚染が見つかった(5センチより深くは計測していないとのこと)。文科省が公開している千葉県のセシウム137の降下量の累積(3月19日から4月24日まで)は約5000MBq/km2つまり5000Bq/m2なので、その10倍以上のセシウム137が地表に蓄積されているという値は驚きである。ちなみに53000Bq/m2または53000MBq/km2または1.4Ci/km2という値は、10数年後にガンや白血病が発生しているチェルノブイリの第三汚染地帯のレベル(1Ci/km2以上5Ci/km2以下、つまり37000-185000MBq/km2)に相当する。これは土の地表の値でありコンクリート表面はそれより低い蓄積量だと推測されるが、いずれにしても文科省公開の降下量の累積値では千葉県よりも東京・茨城・山形・そしておそらく福島・宮城の方がセシウム137降下量が多いので、千葉で1Ci/km2を超える数値が出たということはかなり深刻な事態である。※Bq/m2=MBq/km2
(引用終了)
http://ameblo.jp/x-csv/entry-11174503215.html からの情報
志賀原発の運転差し止め命じる 金沢地裁判決
石川県志賀町の北陸電力志賀原発2号機(改良型沸騰水型炉=ABWR、出力135万8000キロワット)をめぐり、16都府県の132人が、同社(本店・富山市)を相手取り、運転差し止めを求めた民事訴訟の判決が24日、金沢地裁であった。
井戸謙一裁判長は「電力会社の想定を超えた地震動によって原発事故が起こり、住民が被曝(ひばく)をする具体的可能性がある」として巨大地震による事故発生の危険性を認め、住民側の請求通り北陸電力に対して志賀原発2号機の運転を差し止める判決を言い渡した。2号機は今月15日に国内55基目の商業用原発として営業運転を始めたばかりだった。北陸電力は控訴する。
営業運転中の原子炉の運転差し止めや原子炉設置許可の取り消しを求めた訴訟で、原告の訴えが認められたのは初めて。判決の内容を即座に実行できる仮執行宣言はついておらず、判決が確定しない限り、実際に運転が止まることはない。
井戸裁判長は判決で、志賀原発2号機の敷地で起きる地震の危険性と耐震設計について検討。耐震設計が妥当といえるためには、運転中に大規模な活動をしうる震源の地震断層をもれなく把握していることと、直下地震の想定が十分であることが必要だと述べた。
その上で、国の地震調査委員会が原発近くの邑知潟(おうちがた)断層帯について「全体が一区間として活動すればマグニチュード7.6程度の地震が起きる可能性がある」と指摘したことを挙げ、「電力会社が想定したマグニチュード6.5を超える地震動が原子炉の敷地で発生する具体的な可能性があるというべきだ」と述べた。
巨大地震が発生した際の被害については「許容限度を超える放射性物質が放出され、周辺住民の生命、身体、健康に与える影響は極めて深刻である」として、最悪の場合、最も遠方である約700キロ先の熊本県に住む原告であっても許容限度をはるかに超える被曝の恐れがあると指摘。住民の健康が侵される具体的な危険は受忍限度を超えると結論づけた。
さらに判決は、国の定めた耐震設計審査指針についても、前提となる計算方法が古くなり実際の観測結果と食い違う例があることなどを挙げ、「合理性に疑問を抱かざるを得ない」と述べた。
ABWRの危険性については「原告の立証が不十分である」などとして認めなかった。
原告側は、東北電力女川(おながわ)原発(宮城県女川町、石巻市)で、昨年8月の宮城県沖地震が設計の範囲内の規模だったのに、敷地内の一部で限界を超す揺れを記録した──などと指摘。
「20年以上前の耐震設計審査指針は時代遅れで、地震を過小評価している。2号機を含む日本の原発は現実の地震に耐えられない」と主張した。
これに対し北電側は、邑知潟断層帯には活動度の低い断層もあり、一連のものとして評価する必要はなく、仮に調査委の評価通りの地震が起きたとしても、原発の揺れは限界を下回る▽女川原発の1~3号機は設計通り自動停止しており、環境への放射能の影響はない。設備の健全性も損なわれていない──などと反論。宮城県沖地震の発生が志賀原発の耐震安全性に影響を与えるものではないとしていた。(朝日新聞 2006/03/24)











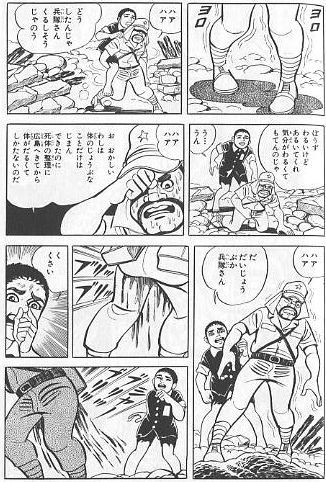
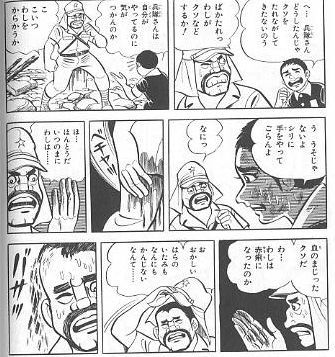



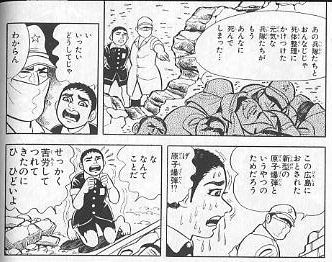

 neko-aii @neko_aii
neko-aii @neko_aii 松任谷正隆 @mm1119
松任谷正隆 @mm1119 大野 美香 @utaumika
大野 美香 @utaumika