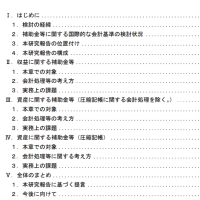エフオーアイ粉飾事件に関連して、株主が引受証券会社らに損害賠償を求めていた裁判の高裁判決で、証券会社に対する請求が棄却された(1審では約3100万円の賠償金が認められていた)ことを取り上げた解説記事。弁護士が書いています。
この裁判では、会計士(監査法人)による監査と証券会社による審査との関係が、ポイントのひとつだったようです。
裁判所は、監査結果の信頼性に疑義を生じさせるような事情があった場合、引受証券会社は「一般の元引受証券会社を基準として通常要求される注意を用いて監査結果に関する信頼性についての疑義が払拭されたと合理的に判断できるか否かを確認するために必要な追加調査を実施すれば足りる」との見解を取ったとのことです。エフオーアイのケースでは、引受証券会社(解説では「Y」)は、財務数値の異常には気付いており、また、匿名投書もあったので、追加調査を行ったそうです。
「追加調査について見ると、Yは、
1.会計監査人から監査方法について具体的な報告を受け、
2.会計監査人が取引先全体に対して、直接、売上債権の実在性を照会し、各帳票類及び預金通帳の原本等を用いた取引の実在性を実証的に確認していると認識した、
3.会計監査人の説明から、会計監査人が直接預金通帳の原本を確認したと認識した、
4.Y自身も、第1投書を受領する前に取引先国内メーカー・海外各1社を実査して販売実績を確認していた、
5.自主規制法人が第1投書を踏まえて売上債権の存在、売掛金の回収状況等につき預金通帳原本と照合する等して実査した際にYも立ち会い、特に問題が指摘されなかった、
6.第1投書で指摘されている国内メーカーの購買部長に対する巨額のストックオプションの付与の存在も確認できなかった等の報告を受けた、
7.常勤監査役にもヒアリングし、F社での監査役の業務態勢に問題がなく、取締役らの説明について裏付けを確認し、
これらの一連の追加調査で、会計監査人の報告内容が裏付けられたため、会計監査人の監査結果(無限定適正意見)に関する信頼性についての疑義が払拭されたと判断したことは合理的であり、Yは、一般の引受証券会社を基準として通常要求される注意義務を尽くしたものであって、会計監査人による監査結果(無限定適正意見)を信頼することが許される、と本判決は判断した。このように「相当な注意を用いた」にもかかわらず、有価証券届出書の虚偽記載を知ることができなかったとして、金商法等の損害賠償責任を負わない、と判示した。」
このような裁判所の判断について、解説記事では以下のように批判しています。異常事態が起きていたのに「通常要求される注意義務」でいいのかというような批判です。
「平時における引受審査ではなく、質・量ともに重大な「粉飾を疑わせる事情」(Red Flag)が存在し、監査結果に関する信頼性について極めて強い疑義が生じている有事の局面では、公認会計士等と引受審査を行う元引受証券会社の役割分担への信頼の前提が崩れさっており、元引受証券会社は、もはや公認会計士等の監査結果を信頼することも、その監査結果に依拠して引受審査を行うことも、許されず、自らあるいは他の公認会計士・監査方針等の専門家を起用して有価証券届出書の正確性を調査する義務を負担するというべきである。
本判決の枠組みが、有事における調査の局面でも平時と同様の調査を行えば足りる(本判決には「特段の事情がある場合を除き、」という留保の文言はない)とするのであれば、会計監査人が精査したことを過大評価して元引受証券会社の審査義務の水準を緩めるに等しく、公認会計士等と元引受証券会社との間で合理的な役割分担の範囲を定めた金商法の趣旨に適うものとはいえないように思われる。」
「クリストファー・チャブリス=ダニエル・シモンズの『錯覚の科学』に登場する「見えないゴリラ」の実験で認知された事項であるが、物事の認知のプロセスにおいて自己の経験や背景などに基づいて情報を選択したり、自己の関心や期待などを反映させる「選択的認知」が働く。元引受証券会社は、信頼性についての疑義を払拭できる事情があるか否かにのみ関心を集中させて調査すれば足りるとなると、元引受証券会社の審査部門の担当者は、監査結果の信頼性についての疑義を強めたり、粉飾の疑義を強めたりする事情については、意図的ではないとしても、見落としたり、過小評価する可能性が生じるとの弊害が懸念される。」
この事件では、会計監査の質が低かったということが、もちろん大問題ですが、監査人の弁護をするとすれば、最低限の監査証拠が入手できた場合、財務数値が異常だ、内部通報があったというだけでは、なかなか無限定以外の監査意見は出しにくいと思われます。下手に不適正などを出すと、会社から訴えられる可能性もあります。実際、東芝のケースでは、監査人がなかなか監査意見(四半期は結論)を表明しなかったり、限定付き意見を出したことに対して、訴訟までは行かなくても、世間的には大きなバッシングを受けています。
証券会社の方は、そういうしばりはないのですから、投資家に安心して勧められる株式かどうかという観点で、厳しく審査し、自由に判断すべきだったのでしょう。会計監査を追認するだけでは、せっかく審査する意味がありません。
(解説の中でふれている「選択的認知」は、会計監査でも注意すべき点でしょう。疑義を解消しようとする方向にばかり気持ちが向かうと、へりくつでも何でも、会社側の説明を受け入れるようとするバイアスがかかります。
記事の中では、不正対応監査基準では「不正リスクが高い可能性のある局面では、監査人は、監査モードを切り替えて、...反証主義に軸足を置いた監査手続への実施にシフトすることを求められる」といって、基準を高く評価していますが、実際の基準では、「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況」でも、「経営者に質問し説明を求める」手続きを前面に押し出すなど、監査人の「選択的認知」を強化する側面もあるように思われます。本来、そういう状況では、経営者の説明以外の証拠の方をより重視すべきでしょう。)
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事