12月13日開催予定の金融審議会公認会計士制度部会の会議資料が公開されています。
主な論点について、「公認会計士制度の見直しの方向性(案)」が示されています。
以下、会議資料より。
論点1 上場会社の監査を担う監査事務所の規律付け
① 登録制の導入
• 上場会社等の財務書類についての監査証明業務(以下、「上場会社監査」)を行う監査事務所は、日本公認会計士協会(以下、「協会」)への登録を受けることとする。
② 登録時の適格性の確認
• 登録を受けようとする監査事務所は、協会に登録申請を行い、協会から上場会社監査を実施する者としての適格性の確認を受けることとする。
> 例えば、業務停止処分中でないことや、「一定の社員数」を有すること等が考えられるか。
> 「一定の社員数」とは、例えば、
- 現行の公認会計士法において、監査法人に対し、公認会計士である社員を5人以上有することを求めていることに倣い、制度導入当初は「公認会計士である社員を5人以上有すること」とした上で、
- 制度導入後、協会が実施する中小監査事務所への育成支援による体制整備の進展を踏まえながら見直していくことが考えられるか。
③ 登録後の継続的な規律付け
• 登録を受けた監査事務所には、上場会社監査に係る体制整備や情報開示について、登録を受けていない監査事務所より高い規律付けを設ける。
>例えば、監査法人のガバナンス・コードの受け入れや、充実した情報開示を求めることなどが考えられるか。
>現行の公認会計士法上、監査法人には、業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、公衆の縦覧に供することが求められている。上場会社監査を行う者に対し、充実した情報開示・付加的な情報開示を求めるべき事項は何か。また、それらを法令で定めるべきか又は自主規制に委ねるべきか。
>現行の公認会計士法上、公認会計士個人が上場会社監査を行うことも許容されているが、単独で監査を行うことは原則として認められておらず、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならないこととされている。
上場会社監査を担う公認会計士については、今後、協会が実施する中小監査事務所への育成支援を通じて、組織的な対応に向けた取組みを促すことが考えられるか。
• 登録後に上場会社監査を公正・的確に実施する体制が整備されていないこと等が確認された場合、協会は、登録を取り消すことができることとする。
④ 被監査会社側の手当て
• 金融商品取引法の規定により上場会社等が提出する財務書類について、登録を受けた監査事務所から監査証明を受けなければならないこととする。
論点2 公認会計士・監査審査会によるモニタリング
• 公認会計士法上の立入検査等の権限について、金融庁から公認会計士・監査審査会へ権限委任する範囲を見直し、業務の運営の状況に関して行われるものか否かに関わらず、公認会計士・監査審査会において権限行使できることとする。
論点3 監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限
• 監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等である場合に当該監査法人の監査証明業務が制限されることとなる社員の範囲を、現行の全ての社員から、当該会社等の財務書類について当該監査法人が行う監査証明業務に関与する社員等に限ることとする。
論点4 組織内会計士の登録事項の整備
• 組織内会計士の登録事項について、監査事務所以外の勤務先を記載することとする。
論点5 実務経験期間の見直し
• 公認会計士の資格要件である実務経験期間(業務補助等の期間)を、現行の2年以上から3年以上とする。
論点6 継続的専門研修の確実な受講
• 継続的専門研修(CPE)の受講状況が著しく不適当な公認会計士について、資格審査会の議決に基づき、登録を抹消することができることとする。
• 併せて、虚偽の申請等に基づいて登録を受けた場合や、2年以上継続して所在が不明である場合についても、資格審査会の議決に基づき、登録を抹消することができることとする。
論点1が最も重要でしょう。上場会社監査事務所登録制といっても、現行の協会が運営するという形はそのままなので、大きくは変わらないのかもしれません。しかし、監査法人の社員の数の下限引き上げや、情報開示拡充などは、影響が出る監査法人もあるでしょう。また、少しふれている個人の会計士事務所がどのような扱いになるのかも、ポイントでしょう。準登録といった甘い基準が認められるのかどうかも気になります。
登録の要件を厳しくすればするほど、新規参入は難しくなりますが、上場会社監査の品質維持・向上のためにはやむを得ないということなのでしょう。
上記の他に、「日本公認会計士協会による会計基礎教育の普及活動に制度的な位置づけを設けてほしい」というのもあって、協会がプレゼンをするようです。その資料を見ると、税理士法における税理士会の会則に関する規定を引用しており、それをまねて法改正してほしいということなのでしょう。
「第四十九条の二
2 税理⼠会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
⼀〜九 (省略)
十 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定」
(補足)
与党の税制改正大綱をみていたら、税理士制度も若干手直しするようです。
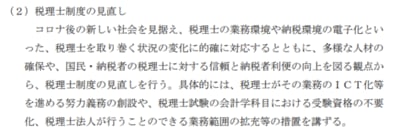
税理士試験の会計科目の受験資格不要ということは、会計科目は大学2年まですぎなくても受験できることになるのでしょうから、従来より早期に受験を始める人が出てくるのでしょう。(学歴要件完全不要の会計士試験には負けますが)




