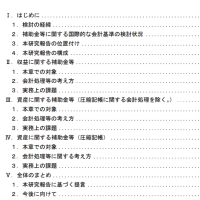弁護人取り調べ立ち会いなど、国連委員会が何度も勧告
ゴーン氏の記者会見では、日本の刑事司法制度を厳しく批判していましたが、この記事(記者会見前に公表されたゴーン氏の声明文を取り上げたもの)によると、その主張はだいたい正しいようです。
「自由権規約の第9条3項では、容疑者・被告の「妥当な期間内に裁判を受ける権利」「釈放(保釈)される権利」のほか「裁判に付される者を抑留することが原則であってはならない」と規定している。第10条には「自由を奪われた全ての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して取り扱われる」とある。起訴前の保釈は認められず、ゴーン前会長は起訴後の保釈請求も2回退けられ、勾留が130日に及んだ。最初の逮捕から1年以上たっても公判日程は決まらず、日本は自由権規約に反していると見えたのだろう。 」
「自由権規約の第14条1項は、全ての者は「裁判所の前に平等とする」「独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する」と定め、2項では「法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」と世界人権宣言の第11条1項から無罪推定の原則を引き継いでいる。
前会長の事件では、東京地裁は1回を除き、特捜部の請求通り逮捕と勾留を認めた。また特捜部が公判前整理手続きで、日産から押収するなどしたパソコンやハードディスクなどの電子媒体から抽出した電子データを公判に証拠提出すると表明したので、弁護人が電子媒体の証拠開示を求めたところ、特捜部は日産から要請されたとして、電子媒体の一部削除を始めた。そこで弁護人は電子媒体を差し押さえて証拠を保全するよう裁判所に求めたが、裁判所は必要性がないとして応じなかった。
前会長は裁判所のこうした姿勢を見て「裁判所の前に平等」ではなく、独立した公平な裁判所での審理は期待できないとの思いを強めたのではなかろうか。無罪推定の原則も、自由権規約第14条3項の「自己に不利益な供述または有罪の自白を強要されない」との条項も、長期勾留と取り調べが合法的に続く国では、絵に描いた餅に見えたのだろう。 」
「日本外務省のHPによると、自由権規約に基づき、その順守状況を監視する国連の自由権規約委員会は1998年と2008年、2014年の総括所見で、日本政府に対し▽弁護人の取り調べ立ち会い、▽取り調べ全過程の録画、▽取り調べ時間を制限する立法措置、▽捜査機関が収集した全証拠を弁護人に開示すること、▽起訴前の保釈制度創設、▽裁判官や検察官に対し、自由権規約の規定に習熟させるためのセミナー開催―などを勧告してきた。
このうち弁護人の取り調べ立ち会いは、日弁連が18年4月に公表した「弁護人を取り調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」によると、米国や欧州連合(EU)各国、韓国、台湾などでは、容疑者・被告の権利として確立しているという。ゴーン前会長の常識からすれば、取り調べに弁護人が立ち会うのは当然であり、特捜部の取り調べは非常識に思えたのではないか。欧米のメディアによる前会長逮捕などの報道でも、弁護人が取り調べに立ち会えないことを、驚きを持って伝えていた。 」
「自由権規約のほか、1984年の国連総会で採択され、日本は99年に批准した拷問等禁止条約にも「拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる」(第2条1項)などの条項がある。同条約に基づく国連の拷問禁止委員会は2013年の総括所見で、日本政府に対し、取り調べ時間の制限や取り調べ全過程の録画、自白中心の捜査手法を改善することなどを求めている。
同年5月22日の拷問禁止委員会による対日審査では、委員から出た「日本の刑事司法は自白に頼りすぎ、中世のようだ」との指摘に対し、日本の上田秀明・人権人道担当大使(当時)が「日本の人権状況は先進的だ。中世のようではない」と反論。場内から笑いが起きると、上田大使は「何がおかしい。黙れ(シャラップ)」と大声を張り上げた。「シャラップ」は公の場では非礼な表現なので、各国で報道された。ゴーン前会長は拷問禁止条約についても知っていた可能性があり、声明の「国際法や条約」には、拷問禁止条約も含まれているかもしれない。 」
記事中で紹介されている高野弁護士のブログ
http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65953670.html
会計士も人質司法に巻き込まれるという例。粉飾ではなかったという主張には賛成できませんが...。
↓

(電子書籍版です)
ゴーン氏の「日本の司法制度は不正義」は本当か?(朝日)