【イエスの聖心の信心の意義】

イエスの聖心の啓示は、私的啓示でありながらも典礼暦に祭日を持つ
重要なものだ。
神からのものだから大事なのは当然だ。しかし神学者ならば、
この意義付けを試み、現代人に分かるように熱心に説いて欲しいものだ。
さて、「聖心の使徒」と言われるマテオ神父という方がおられた。
1900年代初め頃の人だ。
当時はすでに、この信心にさまざまな偉い人々から批判があった
ようだが、マテオ神父はこう答える。
この信心は聖書から外れたものではなく、まさに聖書の真髄、
神の子の愛について語るものだと。
こういう説明は大切だと思う。もともとさまざまな信心を大切にする
人だけでなく、そうでない人にも分かりやすく教えてくれる人が欲しい。
とりわけ第2バチカン公会議以降は、聖書を源泉として再認識した
のだから、信心が誤解を受ける可能性がある。聖書の真髄を照らす
ものとしての説明は正しいと思うし、信心の方向性もそちらのはずだ。
さて、私はこの信心をもともと大事にしていたつもりだが、
最近ちょっとした理解をもたらしてくれた記事に出会った。
聖心の信心の創始者は聖女マルガリタ・マリア・アラコック
(17世紀)だが、実はその前に、もう一人の聖女がいるらしい。
その名は聖女ゲルトルード、13世紀のドイツのベネディクト会修道女
であり、神秘家だ。さまざまな幻視を受け、著作も多いらしい。
神はこの聖女にこの神秘を示された。ゲルトルードはアラコックと
同様、最後の晩餐のキリストの胸に、あの使徒ヨハネのように
寄りかかるという恩恵を受けた。
この幻視のときにゲルトルードは使徒ヨハネからこう告げられたと言う。
「この心臓の鼓動の甘味さを人々に知らせることは、後の世に
残されている。世の愛が冷えた時、この不思議を世に示すことが、
老衰しつつある世を暖めるのです」。
知らせるための「後の世」とは17世紀の聖女アラコックのことであろう。
13世紀に私的にのみ示されたことは、17世紀に公にするようにと神は
望まれた。
時期として選ばれたのは「世の愛が冷えたとき」。目的は
「老衰しつつある世を暖める」こと。信心の中心は「心臓の鼓動の甘美さ」
に示される、人となられた神の不思議な愛だ。
終末に関するキリストのみ言葉に「不正がはびこるので愛が冷える」
というものがある。時代の推移とともに、世を覆う暖かさに変化が
あることを予言しておられる。
聖書を読んでも、十字架のキリストを眺めても、愛が心に入って
こないことがある。あまりにも大きな悩みと苦しみのために。
また人の愛が信じられないがために、神の愛も信じられない。
十字架のキリスト像は神の愛を示すものとしてわれわれに
与えられたものだ。
しかし愛の冷えた時代には、この像は、神の愛を示すものである代わりに、
自己犠牲の要求の大きさを突きつけて、見ていて苦しくなる人もいるだろう。イエズスの聖心の聖画は、もっと分かりやすい。
十字架上のキリストの愛は、ある意味で究極の愛であり、
極限の愛だ。しかし現代人が自己を支えるために必要としているのは、
もっと身近な日常的な愛であるように思う。
つまり、罪を取り除いて永遠の命を約束してくださった十字架
のみならず、日常的に暖かい目で私を見つめてくださっている
キリストの愛、それも必要になってきた。不安があらゆる人を
覆うようになって来た時代だ。
私たちはこのようにして、再び聖書のキリストに結ばれてゆくのだと思う。聖書に記されたキリストによる神の愛を理解するために、現代に生きる
私たちの助けとして「イエズスの聖心の信心」が示されたのではなかろうか。
「世の愛が冷えた時、この不思議を世に示すことが、老衰しつつある
世を暖めるのです」。聖ゲルトルードに示されたこのみことばを、
私なりに解釈するとこうなる。
(「神父の放言」より掲載)















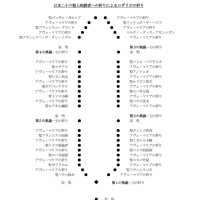

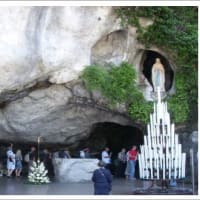
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます