先々週のある休憩時間、夕方の神田界隈を歩いていて、ふと立ち寄ったコンビニで週刊SPAを手にとってみたら、デカデカと「30代から成功した遅咲きパーソンインタビュー」みたいなことを取り上げていて、ふと目をひいたので読んでみた。
元々おいらは、週刊SPAだなんていう雑誌はほとんど読む習慣すらない。
熱を入れて読んでいたのも、小林よしのりが「ゴーマニズム宣言」を連載していた90年代中盤くらいなもので、あの頃はおいらが通っていた専門学校の左寄りの講師が小林よしのりに小難しい論文でケンカを売っていたり、間接的な「当事者」としてもなかなか刺激的な毎日だったのでは…と今更ながら思えるのは、やはり当時の状況を今になって冷静に振り返ることができる賜物なのかなと。あの頃、どれだけビンボーな生活を送っていても、後になればなるほど「あの頃は~(by和田アキ子御大)」なんて言える時代が来るもので、結局はその時代時代の「今」の瞬間を、存分に楽しんだもの勝ちなのかと、今更ながら思う。そう考えると、今のおいらは、過去はともかく、「今」は楽しんでいるか…と言われると、果たしてどうだろうねえ…。
それはともかく、「SPA」自体もおいらはあまり好きではなく、それは何かと言えば、ひとえに「ぼくらの○○」という大見出しがとてつもなく軟弱っぽく見えるのがたまらなく嫌だったから。
今でもこのブログでは「俺の」或いは「俺達の」という表現で、もちろん「僕の」でもいいとは思うが、「僕の」が複数形になった「僕らの」「ぼくらの」という表現になると、途端に軟弱っぽい印象に変化してしまうのはどうしてだろう。
一人称としての「僕」という言葉はごく普通で、少年からお年寄りまで広く使われている言葉だというのに、これが複数形になった「僕ら」「ぼくら」という表現になると、途端に20代ならともかく、いい年扱いて言う言葉かという印象を与えてしまうのは、或いはおいらの自意識過剰なのだろうか…?
先月中旬、寝台急行「銀河」が廃止される前日に東京駅に立ち寄ったが、A寝台の窓に、お手製の大作と思われる「ありがとう!ぼくらの急行『銀河』」という紙を貼りだして、ファンから喝采を浴びていたお客さんがいたが、おいらもその紙はいいとは思うが、「ぼくらの…」という言葉の響きがどうしても受け入れがたく、写真は撮らなかったなあ…。
というより、「俺」「俺達」という言葉に、あまりにも不感症になっている一面を持ち合わせているのは確かですな。
俺達の誇り
俺達のベニー
俺達のDメイ
俺達のフランコ
俺達の神戸
日頃これだけ「俺」「俺達」という言葉を使っていたら、一見粗暴と思えるこの言葉に、どうしても不感症にならざるを得ないのは間違いない(笑)。
実際、このブログを立ち上げた時も、書くスタイル、或いは一人称について迷いに迷い抜いた。
いや、最初なんて「どうせこんなもん誰も読まねえよ」という意識が丸出しで(そのくせてめえのアクセス数だけはやたらと気にしていたのだから知れたものww)、元々大人数にアクセスして頂けるなんていう状況など想像もつかなかったから、元来が種村直樹先生の文体で鍛え上げられた下地もあって、論調風、そして「俺」という一人称、最近は「おいら」という言葉に変化してはいるが、そのスタイルは頑なに…というか、ごく自然にそのようなスタイルになって今に至っている。
論調風の文体も良し悪しで、ともすれば「上から目線で物事を語りやがって」と言われることの諸刃の剣。おいら自身は決してそのようなつもりはないのだが、論調風の文体だけで「上から目線」と言われるのは少々きっついかな…。こればっかりは、ネット環境の変化と捉えるしかないだろう。まあ、そのへんの評価は、いつもお読み頂いている皆さんにお任せ致しますm(_ _)m
話はそれたが、その週刊SPAの特集が、「30代で花開いた遅咲きビジネスマンの『くすぶっていた時代』」だったかなんだかで、20代にフリーターやニートまで経験した人が、如何にして30代で花開くことが出来たのか…という、SPA!にしてはなかなか役立つ特集を組んでいて興味深かった。
遅咲きのビジネスマンに共通していたのは、「時間がある時に何かしらにチャレンジしていたこと」。
それは例えば海外生活であったり、たまたま人生で「これは!」と思える人との出会いがあって、その人に追いつき追い越そうと仕事を展開して成功した人などなど、プロセスは様々だが、「逆転の発想」というのか、ともすれば仕事仕事で忙殺されまくりの時期に伏竜していたからこそ、今の世に竜となって生きていけるのだということ。こんな大事な記事だというのにコンビニの立ち読みで済ませてしまったのがなんともはや…という感じだが、その記事は、フリーターでなんとか社会復帰を賭けているおいら自身にそのまんまはね返ってくる内容だった。
要は、「くすぶっていた時代」があったからこそ、今の世に羽ばたくことが出来たわけである。
そこでハタと思い当たった。
くすぶっているのか、俺?
なかなか日の目が当たらない人を、人はよく「くすぶっている」と表現するが、くすぶっている状態というのは、火の気があってもなんらかの原因で燃えさかることが出来ず、火は焚かれていても火の手は上がらず煙だけがもくもく上がることを言うが、そもそも俺なんていう人間は、くすぶる以前に火の気が全くない状態なのだから、己の状況を例えて「くすぶり続ける」だなんて言うのは、本当にくすぶり続けている人達に対して失礼ではないかと思うのだ。
例えば昨日の野球にしてもそうだが、細谷は昨日急遽浦和から呼び出され、1軍初出場初スタメンのプレッシャーの中で、初安打初打点という裏ドラまでのせてきた。
その影で、せっかく1軍にお呼びがかかっても、監督によっては即座に結果を求められ、プレッシャーに負けて日の目を見ることなく消えていった選手などごまんといる。
そのような選手達に向かって「くすぶっている」と面と向かって言うのはともすれば失礼に当たるが、かような人達でなければ、「くすぶっている」と己を例えるのは、それこそ本当にくすぶっている人達に失礼だと思うのだ。
「火のないところに煙は立たぬ」とは、よく人の噂に例えて言われる言葉だが、これはまさに人間の生き方そのものを表す本質的な言葉ではないだろうか。火のないところでは燻ることも出来ないのだ。
まずはくすぶることから始めよう。
そのためにはまず火を焚かなければ。
火を焚くにはどうするか。
ライターを持ってくるか。
灯油をそのへんにぶちまけるか。
木と木の摩擦熱で火を付けるか。
或いはポーゴ様のようにガソリンを口に含んで火炎放射(以下略
燻るために、まずは何が出来るか。
さあ、今週も始まりだ。頑張ろう。



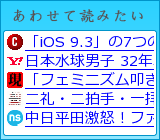
元々おいらは、週刊SPAだなんていう雑誌はほとんど読む習慣すらない。
熱を入れて読んでいたのも、小林よしのりが「ゴーマニズム宣言」を連載していた90年代中盤くらいなもので、あの頃はおいらが通っていた専門学校の左寄りの講師が小林よしのりに小難しい論文でケンカを売っていたり、間接的な「当事者」としてもなかなか刺激的な毎日だったのでは…と今更ながら思えるのは、やはり当時の状況を今になって冷静に振り返ることができる賜物なのかなと。あの頃、どれだけビンボーな生活を送っていても、後になればなるほど「あの頃は~(by和田アキ子御大)」なんて言える時代が来るもので、結局はその時代時代の「今」の瞬間を、存分に楽しんだもの勝ちなのかと、今更ながら思う。そう考えると、今のおいらは、過去はともかく、「今」は楽しんでいるか…と言われると、果たしてどうだろうねえ…。
それはともかく、「SPA」自体もおいらはあまり好きではなく、それは何かと言えば、ひとえに「ぼくらの○○」という大見出しがとてつもなく軟弱っぽく見えるのがたまらなく嫌だったから。
今でもこのブログでは「俺の」或いは「俺達の」という表現で、もちろん「僕の」でもいいとは思うが、「僕の」が複数形になった「僕らの」「ぼくらの」という表現になると、途端に軟弱っぽい印象に変化してしまうのはどうしてだろう。
一人称としての「僕」という言葉はごく普通で、少年からお年寄りまで広く使われている言葉だというのに、これが複数形になった「僕ら」「ぼくら」という表現になると、途端に20代ならともかく、いい年扱いて言う言葉かという印象を与えてしまうのは、或いはおいらの自意識過剰なのだろうか…?
先月中旬、寝台急行「銀河」が廃止される前日に東京駅に立ち寄ったが、A寝台の窓に、お手製の大作と思われる「ありがとう!ぼくらの急行『銀河』」という紙を貼りだして、ファンから喝采を浴びていたお客さんがいたが、おいらもその紙はいいとは思うが、「ぼくらの…」という言葉の響きがどうしても受け入れがたく、写真は撮らなかったなあ…。
というより、「俺」「俺達」という言葉に、あまりにも不感症になっている一面を持ち合わせているのは確かですな。
俺達の誇り
俺達のベニー
俺達のDメイ
俺達のフランコ
俺達の神戸
日頃これだけ「俺」「俺達」という言葉を使っていたら、一見粗暴と思えるこの言葉に、どうしても不感症にならざるを得ないのは間違いない(笑)。
実際、このブログを立ち上げた時も、書くスタイル、或いは一人称について迷いに迷い抜いた。
いや、最初なんて「どうせこんなもん誰も読まねえよ」という意識が丸出しで(そのくせてめえのアクセス数だけはやたらと気にしていたのだから知れたものww)、元々大人数にアクセスして頂けるなんていう状況など想像もつかなかったから、元来が種村直樹先生の文体で鍛え上げられた下地もあって、論調風、そして「俺」という一人称、最近は「おいら」という言葉に変化してはいるが、そのスタイルは頑なに…というか、ごく自然にそのようなスタイルになって今に至っている。
論調風の文体も良し悪しで、ともすれば「上から目線で物事を語りやがって」と言われることの諸刃の剣。おいら自身は決してそのようなつもりはないのだが、論調風の文体だけで「上から目線」と言われるのは少々きっついかな…。こればっかりは、ネット環境の変化と捉えるしかないだろう。まあ、そのへんの評価は、いつもお読み頂いている皆さんにお任せ致しますm(_ _)m
話はそれたが、その週刊SPAの特集が、「30代で花開いた遅咲きビジネスマンの『くすぶっていた時代』」だったかなんだかで、20代にフリーターやニートまで経験した人が、如何にして30代で花開くことが出来たのか…という、SPA!にしてはなかなか役立つ特集を組んでいて興味深かった。
遅咲きのビジネスマンに共通していたのは、「時間がある時に何かしらにチャレンジしていたこと」。
それは例えば海外生活であったり、たまたま人生で「これは!」と思える人との出会いがあって、その人に追いつき追い越そうと仕事を展開して成功した人などなど、プロセスは様々だが、「逆転の発想」というのか、ともすれば仕事仕事で忙殺されまくりの時期に伏竜していたからこそ、今の世に竜となって生きていけるのだということ。こんな大事な記事だというのにコンビニの立ち読みで済ませてしまったのがなんともはや…という感じだが、その記事は、フリーターでなんとか社会復帰を賭けているおいら自身にそのまんまはね返ってくる内容だった。
要は、「くすぶっていた時代」があったからこそ、今の世に羽ばたくことが出来たわけである。
そこでハタと思い当たった。
くすぶっているのか、俺?
なかなか日の目が当たらない人を、人はよく「くすぶっている」と表現するが、くすぶっている状態というのは、火の気があってもなんらかの原因で燃えさかることが出来ず、火は焚かれていても火の手は上がらず煙だけがもくもく上がることを言うが、そもそも俺なんていう人間は、くすぶる以前に火の気が全くない状態なのだから、己の状況を例えて「くすぶり続ける」だなんて言うのは、本当にくすぶり続けている人達に対して失礼ではないかと思うのだ。
例えば昨日の野球にしてもそうだが、細谷は昨日急遽浦和から呼び出され、1軍初出場初スタメンのプレッシャーの中で、初安打初打点という裏ドラまでのせてきた。
その影で、せっかく1軍にお呼びがかかっても、監督によっては即座に結果を求められ、プレッシャーに負けて日の目を見ることなく消えていった選手などごまんといる。
そのような選手達に向かって「くすぶっている」と面と向かって言うのはともすれば失礼に当たるが、かような人達でなければ、「くすぶっている」と己を例えるのは、それこそ本当にくすぶっている人達に失礼だと思うのだ。
「火のないところに煙は立たぬ」とは、よく人の噂に例えて言われる言葉だが、これはまさに人間の生き方そのものを表す本質的な言葉ではないだろうか。火のないところでは燻ることも出来ないのだ。
まずはくすぶることから始めよう。
そのためにはまず火を焚かなければ。
火を焚くにはどうするか。
ライターを持ってくるか。
灯油をそのへんにぶちまけるか。
木と木の摩擦熱で火を付けるか。
或いはポーゴ様のようにガソリンを口に含んで火炎放射(以下略
燻るために、まずは何が出来るか。
さあ、今週も始まりだ。頑張ろう。



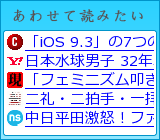




















orz
そっちかい!(笑)
ではみらいちさんとバーンも連れて…。
>にんにん大先生
前がどっちかはわからないけれど、とりあえずやみくもにあがき続けてみますよ。