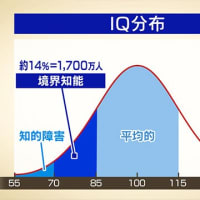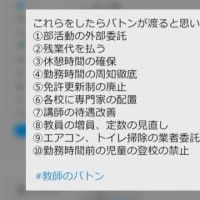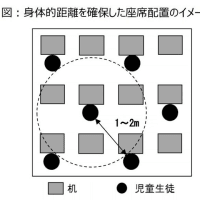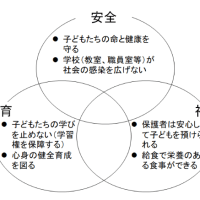最近何かと話題になるキラキラネームです。
より侮蔑的な意味を持たせるために、DQNネームと呼ぶ人もいますね。
自分は、現在高校一年生の子どもたちの学年を受け持っていましたが、特にキラキラ感を感じることは無かったです。
現在、中1の担任をしていますが、この学年も、強い違和感を感じる子は、そういません。
ところが、先日、諸事情で、小学生の名簿づくりを手伝うことがありました。
紙の情報を元に、姓名とふりがなをエクセルに打ち込むという簡単(に最初は思えた)業務でした。
いや、冗談抜きで読めない子が多い。
そして、パソコンで打っても、変換できない。
騎士と書いてないと君とかネット上だけの存在だと思ってたわ、というのが正直な感想です。
さて、今日は、そんなキラキラネームの子どもたちのお話。
我々教師は、キラキラネームの子どもたちに、どのような対応を取るのでしょうか。
結論を先に書くと、関係ないです。
名前は親が付けるもの。
なので、子どもには一切の責任はありません。
名前がキラキラかそうで無いかで、子どもに対する教師の対応が変わることは、あってはならいことだと思います。
まあ、内心では、名簿を作ったりするときに、めんどくせーなー、と思うことはあり得ますけれども、決して外に出していい感情ではありません。
しかしながら、下記の2点については、他の子よりも「警戒」します。
警戒1:家庭環境・親
例えば、「伽」という漢字が使用されている女の子がいたとしましょう。
インターネットで、「伽 子ども 名前」と検索してみてください。
すると、この字にはセクシャルな意味があり、子どもの名前には使うべきではない漢字である、という見解がたくさん出てきます。
それでも、この字を使う親はいます。
そのような親は
1.子どもに名前を付ける際、その漢字には一般的にどのような見解がを調べようとしない、すなわち興味がない。
または
2.調べたけれども、そのような他者の見解は考慮するに値しないと考えている。または考慮した結果、そこまで気にすることはないと結論した。
だと考えられます。
だから悪い親だ、と言うつもりは全くありませんよ。
ただ、他者の意見や前例にとらわれない親なのだろうな、とは思います。
その傾向が、良い方向に働くか、悪い方向に働くかは、我々にはわかりません。
他者の意見に聞く耳を持たない人である可能性もあれば
先入観やデマに踊らされずに、自分の信念を持って筋を通してくれる人である可能性もあります。
情報の伝播って結構恐ろしいですよ……
「○○先生がこんなひどいことをした」という情報がご近所ネットワークに流れたが
実はそれはかなり歪曲・誇張された、デマとも言える話だった……ありうる話です。
ただ、悪い方向に働かないでくれよ、と思いながら、常に見てしまうというのは否定できません。
で、その傾向が悪い方向に働いた場合、それは間違いなく子どもにマイナスの影響を及ぼします。
だから、そうゆう特徴のある家庭環境・親なのだな、と警戒はしてしまいます。
これが本音。
警戒2:いじめリスク
いじめは火事みたいなものです。
まずは起きないようにしたい。
起きちゃってもボヤのうちに鎮火したい。
残念ながら火事になっちゃっても、せめて延焼を食い止めたい。
で、いじめを行う子どもにとっては、火だねは、何でも良いのです。
「他者とちょっと違うところがある」と言うだけで、それは燃料になります。
すなわち、キラキラネームは、無視できない燃料になります。
その燃料に火を付けることは許せないことですが、それでも火遊びをしたがる者がいるのが現実です。
なので、その燃料のまわりを、よく見張る必要性があるのです。
もちろん、燃料という書き方をしてしまいましたが、そのキラキラネームの子が悪い訳ではないですよ。
理想は、学級内でお互いが認め合いが成立していて、そんなことで「いじめてやろう」という発想にだれもが至らなくなることです。
でも、それは学級の完成形であり、ローマは一日にしてならず、です。
最後に……どこからがキラキラネームでしょうか。
これは私の個人的見解です。
漢字の意味に関しては、別に「キラキラ」ではないと思います。
先ほどの、「伽」と言う字。
セクシャルな意味があるのは事実かも知れませんが、100%そうではありません。
他人に尽くせる人になりなさい、という意味ともとらえられます。
ですから、親および本人が納得してれば、別に第三者が騒ぐほどのことではないのでは、と思います。
ところが、「どう考えてもその漢字でそうは読めないだろう」と思うのは、自分は「キラキラ」だと思います。
最初に紹介した、騎士と書いてないと君。
これはもう完全に、日本語および漢字文化の言語のルールを無視しており、いかがなものかと自分は感じます。
「どう考えてもその漢字でそうは読めないだろう」と感じる難読地名が昔から存在するのも事実ですが……
だから子どもに難読名を付けて良いって訳ではないでしょう。
ただ、何度も言いますが、悪いのは子どもではありません。
より侮蔑的な意味を持たせるために、DQNネームと呼ぶ人もいますね。
自分は、現在高校一年生の子どもたちの学年を受け持っていましたが、特にキラキラ感を感じることは無かったです。
現在、中1の担任をしていますが、この学年も、強い違和感を感じる子は、そういません。
ところが、先日、諸事情で、小学生の名簿づくりを手伝うことがありました。
紙の情報を元に、姓名とふりがなをエクセルに打ち込むという簡単(に最初は思えた)業務でした。
いや、冗談抜きで読めない子が多い。
そして、パソコンで打っても、変換できない。
騎士と書いてないと君とかネット上だけの存在だと思ってたわ、というのが正直な感想です。
さて、今日は、そんなキラキラネームの子どもたちのお話。
我々教師は、キラキラネームの子どもたちに、どのような対応を取るのでしょうか。
結論を先に書くと、関係ないです。
名前は親が付けるもの。
なので、子どもには一切の責任はありません。
名前がキラキラかそうで無いかで、子どもに対する教師の対応が変わることは、あってはならいことだと思います。
まあ、内心では、名簿を作ったりするときに、めんどくせーなー、と思うことはあり得ますけれども、決して外に出していい感情ではありません。
しかしながら、下記の2点については、他の子よりも「警戒」します。
警戒1:家庭環境・親
例えば、「伽」という漢字が使用されている女の子がいたとしましょう。
インターネットで、「伽 子ども 名前」と検索してみてください。
すると、この字にはセクシャルな意味があり、子どもの名前には使うべきではない漢字である、という見解がたくさん出てきます。
それでも、この字を使う親はいます。
そのような親は
1.子どもに名前を付ける際、その漢字には一般的にどのような見解がを調べようとしない、すなわち興味がない。
または
2.調べたけれども、そのような他者の見解は考慮するに値しないと考えている。または考慮した結果、そこまで気にすることはないと結論した。
だと考えられます。
だから悪い親だ、と言うつもりは全くありませんよ。
ただ、他者の意見や前例にとらわれない親なのだろうな、とは思います。
その傾向が、良い方向に働くか、悪い方向に働くかは、我々にはわかりません。
他者の意見に聞く耳を持たない人である可能性もあれば
先入観やデマに踊らされずに、自分の信念を持って筋を通してくれる人である可能性もあります。
情報の伝播って結構恐ろしいですよ……
「○○先生がこんなひどいことをした」という情報がご近所ネットワークに流れたが
実はそれはかなり歪曲・誇張された、デマとも言える話だった……ありうる話です。
ただ、悪い方向に働かないでくれよ、と思いながら、常に見てしまうというのは否定できません。
で、その傾向が悪い方向に働いた場合、それは間違いなく子どもにマイナスの影響を及ぼします。
だから、そうゆう特徴のある家庭環境・親なのだな、と警戒はしてしまいます。
これが本音。
警戒2:いじめリスク
いじめは火事みたいなものです。
まずは起きないようにしたい。
起きちゃってもボヤのうちに鎮火したい。
残念ながら火事になっちゃっても、せめて延焼を食い止めたい。
で、いじめを行う子どもにとっては、火だねは、何でも良いのです。
「他者とちょっと違うところがある」と言うだけで、それは燃料になります。
すなわち、キラキラネームは、無視できない燃料になります。
その燃料に火を付けることは許せないことですが、それでも火遊びをしたがる者がいるのが現実です。
なので、その燃料のまわりを、よく見張る必要性があるのです。
もちろん、燃料という書き方をしてしまいましたが、そのキラキラネームの子が悪い訳ではないですよ。
理想は、学級内でお互いが認め合いが成立していて、そんなことで「いじめてやろう」という発想にだれもが至らなくなることです。
でも、それは学級の完成形であり、ローマは一日にしてならず、です。
最後に……どこからがキラキラネームでしょうか。
これは私の個人的見解です。
漢字の意味に関しては、別に「キラキラ」ではないと思います。
先ほどの、「伽」と言う字。
セクシャルな意味があるのは事実かも知れませんが、100%そうではありません。
他人に尽くせる人になりなさい、という意味ともとらえられます。
ですから、親および本人が納得してれば、別に第三者が騒ぐほどのことではないのでは、と思います。
ところが、「どう考えてもその漢字でそうは読めないだろう」と思うのは、自分は「キラキラ」だと思います。
最初に紹介した、騎士と書いてないと君。
これはもう完全に、日本語および漢字文化の言語のルールを無視しており、いかがなものかと自分は感じます。
「どう考えてもその漢字でそうは読めないだろう」と感じる難読地名が昔から存在するのも事実ですが……
だから子どもに難読名を付けて良いって訳ではないでしょう。
ただ、何度も言いますが、悪いのは子どもではありません。