最近、幼少期に見ていたドラえもんのアニメを見るのがマイブームです。
それを見ていると、宿題を忘れたのび太に対し、先生が
「野比、また宿題を忘れたのか!?」
「バカモンー!廊下に立ってなさい!!!」
と叱責するシーンが普通に見られます。
時代だなぁ、と感じます。
そのドラえもんが作られたのは、おおむね30年前ですか。
当時と今では、まるで状況が違います。
今は、厳しい指導を行なうと、すぐに体罰だ人権侵害だという話になり
最近は、指導死などという言葉が聞こえるようになりました。
今、先ほど述べたドラえもんの先生のような指導をしたら、暴言というジャンルの体罰だと言われかねませんし
廊下に立たせる=学習する権利を侵害している=人権侵害である、というドラが乗るでしょう。
教師が悪者になって終わる可能性があります。
体罰や、それに近いような厳しい指導は、今日では教師はやるべきではありません。
そのような今の社会情勢が良いことなのかどうかをここで議論するつもりはありません。
単純に、教師にとって、やる意味が無いしリスクが大きすぎるのです。
体罰はもちろん、始めに例示したドラえもんの先生のような叱責は、現在ではほぼ効果の無い指導です。
理由はいくつかあります。
まずは、親がやらない。
(もちろん、すべての親がそうでは無いでしょうが、その傾向が昔よりも強い、という意味です。)
親がやらない指導を、教師がやったところで、子どもが反省することはありません。
子どもの中で
「ああ、悪いことをして叱られてしまった」という気持ちよりも
「先生にひどいことをされた」
という感情が勝る可能性が大なのです。
また、今の子どもは、昔の子どもよりも、マスメディアの情報に良く触れます。
そのため、メディアの「体罰は悪だ」「人権侵害のような指導を無くそう」という論に感化されています。
ですから、体罰・厳しい指導を受けた子どもは
「悪いのは自分では無く先生だ」となるのです。
そして、体罰は文部科学省が全面的に禁止しているので、もめ事になった場合、錦の御旗は生徒・保護者側になるのです。
体罰とは行かないまでも、厳しい指導を行なった場合、大きなリスクを背負うことになります。
「体罰」と「体罰まではいかない厳しい指導」の線引きは難しい部分でもあるので
教師側が体罰と認識していなくても、生徒側が体罰と認識すれば、教師は窮地に立たされるのです。
というわけで、「子どものため」とか「社会のため」とかそんな価値観は棚上げしての論になりますが
体罰や厳しい指導は、教育的効果がほぼ期待できず、教師にしてみたら自分の立場を悪くするだけなので
やるべきではありません。
先日、こんなことがありました。
自分のクラスでは無かったのですが、某クラスで、授業中に、お菓子の包み紙の切れ端を教室内で発見してしまいました。
その場では、「こんなものが教室で見つかって、残念だ」と生徒達に告げるのみにとどめ、犯人捜しはしませんでした。
授業後、事の委細を、学年主任とそのクラスの担任に話し
「学年全体で、持ち物検査でもしますか?それで犯人が分かるとは思いませんが、プレッシャーにはなるかと思います」
と学年主任に意見を具申したところ
「いや、それは人権侵害になる時代になったらしい。管理職からやるなと言われている」
と言われ、却下されました。
時代は変わったようです。
結局、学年集会を開き、全員に説諭して、終わりました。
というか、それ以上やれることがありません。
「身内かばいだ」と批判をされるでしょうけど
学校と教師は、昔はどの大人も(程度の差はあるだろうが)当然のようにやっていた指導の選択肢の1つをを封じられたわけです。
「○○はいけないことだから、やめなさい」と言ってやめてくれるような子どもばかりなら、誰も苦労はしませんが
そうでないのは、あきらかです。
教師がひどい体罰をして処分されたとか、書類送検されたなんてニュースをしばしば聞きますが
これは、悪戦苦闘・試行錯誤の末、ついに我慢ならなくなってやっちゃったんだろうな、と極めて同情的な想像をしてしまいます。
ま、どのような同情的な事情があれ、キレちゃって子どもをケガさせた段階で、教師側の負けなんですけれども。
「暴力事件」を起こす前に、その先生は、その先生なりに、一生懸命生徒と向き合い、生徒を更正させようとしていたのだろうな、と私は想像してしまい、なんとも切ない気分になります。
続く……
それを見ていると、宿題を忘れたのび太に対し、先生が
「野比、また宿題を忘れたのか!?」
「バカモンー!廊下に立ってなさい!!!」
と叱責するシーンが普通に見られます。
時代だなぁ、と感じます。
そのドラえもんが作られたのは、おおむね30年前ですか。
当時と今では、まるで状況が違います。
今は、厳しい指導を行なうと、すぐに体罰だ人権侵害だという話になり
最近は、指導死などという言葉が聞こえるようになりました。
今、先ほど述べたドラえもんの先生のような指導をしたら、暴言というジャンルの体罰だと言われかねませんし
廊下に立たせる=学習する権利を侵害している=人権侵害である、というドラが乗るでしょう。
教師が悪者になって終わる可能性があります。
体罰や、それに近いような厳しい指導は、今日では教師はやるべきではありません。
そのような今の社会情勢が良いことなのかどうかをここで議論するつもりはありません。
単純に、教師にとって、やる意味が無いしリスクが大きすぎるのです。
体罰はもちろん、始めに例示したドラえもんの先生のような叱責は、現在ではほぼ効果の無い指導です。
理由はいくつかあります。
まずは、親がやらない。
(もちろん、すべての親がそうでは無いでしょうが、その傾向が昔よりも強い、という意味です。)
親がやらない指導を、教師がやったところで、子どもが反省することはありません。
子どもの中で
「ああ、悪いことをして叱られてしまった」という気持ちよりも
「先生にひどいことをされた」
という感情が勝る可能性が大なのです。
また、今の子どもは、昔の子どもよりも、マスメディアの情報に良く触れます。
そのため、メディアの「体罰は悪だ」「人権侵害のような指導を無くそう」という論に感化されています。
ですから、体罰・厳しい指導を受けた子どもは
「悪いのは自分では無く先生だ」となるのです。
そして、体罰は文部科学省が全面的に禁止しているので、もめ事になった場合、錦の御旗は生徒・保護者側になるのです。
体罰とは行かないまでも、厳しい指導を行なった場合、大きなリスクを背負うことになります。
「体罰」と「体罰まではいかない厳しい指導」の線引きは難しい部分でもあるので
教師側が体罰と認識していなくても、生徒側が体罰と認識すれば、教師は窮地に立たされるのです。
というわけで、「子どものため」とか「社会のため」とかそんな価値観は棚上げしての論になりますが
体罰や厳しい指導は、教育的効果がほぼ期待できず、教師にしてみたら自分の立場を悪くするだけなので
やるべきではありません。
先日、こんなことがありました。
自分のクラスでは無かったのですが、某クラスで、授業中に、お菓子の包み紙の切れ端を教室内で発見してしまいました。
その場では、「こんなものが教室で見つかって、残念だ」と生徒達に告げるのみにとどめ、犯人捜しはしませんでした。
授業後、事の委細を、学年主任とそのクラスの担任に話し
「学年全体で、持ち物検査でもしますか?それで犯人が分かるとは思いませんが、プレッシャーにはなるかと思います」
と学年主任に意見を具申したところ
「いや、それは人権侵害になる時代になったらしい。管理職からやるなと言われている」
と言われ、却下されました。
時代は変わったようです。
結局、学年集会を開き、全員に説諭して、終わりました。
というか、それ以上やれることがありません。
「身内かばいだ」と批判をされるでしょうけど
学校と教師は、昔はどの大人も(程度の差はあるだろうが)当然のようにやっていた指導の選択肢の1つをを封じられたわけです。
「○○はいけないことだから、やめなさい」と言ってやめてくれるような子どもばかりなら、誰も苦労はしませんが
そうでないのは、あきらかです。
教師がひどい体罰をして処分されたとか、書類送検されたなんてニュースをしばしば聞きますが
これは、悪戦苦闘・試行錯誤の末、ついに我慢ならなくなってやっちゃったんだろうな、と極めて同情的な想像をしてしまいます。
ま、どのような同情的な事情があれ、キレちゃって子どもをケガさせた段階で、教師側の負けなんですけれども。
「暴力事件」を起こす前に、その先生は、その先生なりに、一生懸命生徒と向き合い、生徒を更正させようとしていたのだろうな、と私は想像してしまい、なんとも切ない気分になります。
続く……










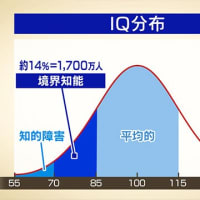

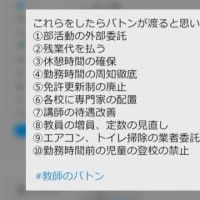
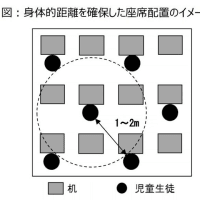
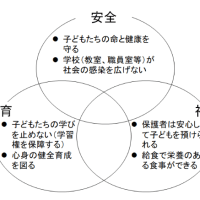




「当たり前」は時代と共に変遷するものですけれども
教育に関しては、それがちと急すぎるように感じます。