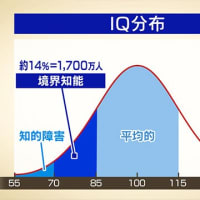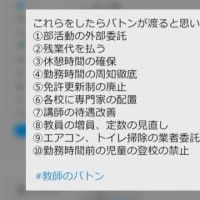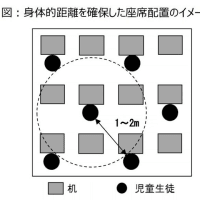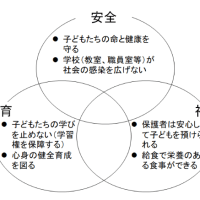以前より、記事で国語力の低さを嘆いてみたり、
新井紀子先生の著作を紹介したりしている私ですが
先日、なかなかにパンチきいた事態に遭遇しました。
今、入試を間近に控えた生徒たちには、授業でひたすら問題演習をさせています。
問題を解かせ、教師が解答解説、というオーソドックスなやつです。
で、諸事情により、解答用紙を用意していません。
「問題用紙のあいているところに自由に答えは書けば良い」
そんなスタイルです。
そして、先日、ある問題に取り組ませたら、事件は起きました。
問題のプリントの問題は下記の通りです。
問1
実験1から,4種類のプラスチックを燃焼させたときに同じ気体が発生したことが確認できました。発生した気体の名称を書きなさい。また,このことから4種類のプラスチックに共通してふくまれていることが確認できる原子の記号を書きなさい。
もちろん、この問1の前には、「こんな実験やったらこんな結果になったよ」というような文章や、表・グラフ等があり
それを読み取った上で、問1~に取り組むのです。
さて、問1の前の部分を割愛しているので、読者の皆さんはこれの答えにたどり着くことはできないでしょう。
しかし、ちゃんと文を読むと、この問1は、「2つの答えを書くべき問題」だというのがわかるはずです。
ところが、原子記号しか書かない生徒が各クラス1割~2割程度出るという始末。
要するに、ちゃんと問題文を読めていないのです。
この問題、答えは「二酸化炭素、C」なんですけれども
二酸化炭素と書くべきところを、酸素と書いてしまった、とか、Cと書くべきところを、Oと書いてしまったとか
そういう誤答は、理科の範疇です。
ところが、それにすらたどり着けていない生徒も結構いるということがわかり、衝撃でした。
文科省は、プログラミングを通して、思考力を身につけさせたいと言っています。
果たして、その前提となる国語力は大丈夫でしょうか。
私は大いに疑問です。
ブログ評価をお願いします。
新井紀子先生の著作を紹介したりしている私ですが
先日、なかなかにパンチきいた事態に遭遇しました。
今、入試を間近に控えた生徒たちには、授業でひたすら問題演習をさせています。
問題を解かせ、教師が解答解説、というオーソドックスなやつです。
で、諸事情により、解答用紙を用意していません。
「問題用紙のあいているところに自由に答えは書けば良い」
そんなスタイルです。
そして、先日、ある問題に取り組ませたら、事件は起きました。
問題のプリントの問題は下記の通りです。
問1
実験1から,4種類のプラスチックを燃焼させたときに同じ気体が発生したことが確認できました。発生した気体の名称を書きなさい。また,このことから4種類のプラスチックに共通してふくまれていることが確認できる原子の記号を書きなさい。
もちろん、この問1の前には、「こんな実験やったらこんな結果になったよ」というような文章や、表・グラフ等があり
それを読み取った上で、問1~に取り組むのです。
さて、問1の前の部分を割愛しているので、読者の皆さんはこれの答えにたどり着くことはできないでしょう。
しかし、ちゃんと文を読むと、この問1は、「2つの答えを書くべき問題」だというのがわかるはずです。
ところが、原子記号しか書かない生徒が各クラス1割~2割程度出るという始末。
要するに、ちゃんと問題文を読めていないのです。
この問題、答えは「二酸化炭素、C」なんですけれども
二酸化炭素と書くべきところを、酸素と書いてしまった、とか、Cと書くべきところを、Oと書いてしまったとか
そういう誤答は、理科の範疇です。
ところが、それにすらたどり着けていない生徒も結構いるということがわかり、衝撃でした。
文科省は、プログラミングを通して、思考力を身につけさせたいと言っています。
果たして、その前提となる国語力は大丈夫でしょうか。
私は大いに疑問です。
ブログ評価をお願いします。