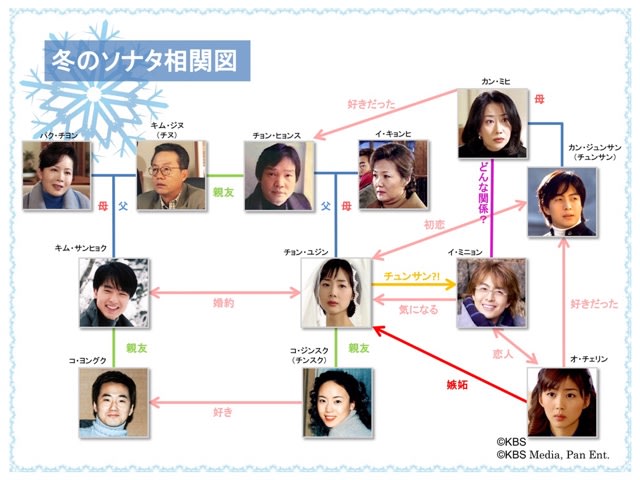
サンヒョクとユジンがチンスクたちの家に行くと、チンスクたちは大歓迎してくれた。しかし、娘のチヒョンの紙おむつなどが無くなってしまったため、二人で買い物に出かけると言って車で出て行った。その間、サンヒョクとユジンは外でチヒョンの相手をしていた。チヒョンは可愛らしい子だったがおてんばで、そのくせ人見知りをする。そのため、母親を探してそこらじゅうを走り回るので、サンヒョクとユジンは追いかけまわしてへとへとになっていた。

「ちょっとチヒョン、こっちよ。」
「止まって止まって!」
すると空腹とおもらしで我慢の限界に達したチヒョンが大声で泣きだした。いつも相手をして慣れているサンヒョクがすかさず抱き上げた。
「ちょっと、泣くなよ。本当に強情なのは誰に似たのかな?」
すると、ユジンがヨングクを思い浮かべて言った。
「そんなのパパに決まってるでしょ。いい子ね。もう泣かないで。ほら、かわいい子。ね?」
今度はサンヒョクが叫んだ。
「ちょっと、チヒョンがおもらししてる!」
「本当?」
そういうと二人はチヒョンを一緒にだっこしてあやした。その姿は何処から見ても仲の良い夫婦で、チヒョンは二人の娘に見えた。
その姿を少し遠くからじっと見つめている男性がいた。そしてそばにただずむ男性に呟いた。
「彼らから本当に僕の姿は見えていないですか?」
「チュンサン、大丈夫だよ。でも、あの子はきっとユジンさんとサンヒョクさんの子だろうね」
「、、、はい。僕はユジンが元気な様子を感じられたのでもう帰ります」
「本当にいいのか?」
その二人はチュンサンとキム次長、いや今は韓国のマルシアンの常務理事になっているキムだった。この日、チュンサンは韓国に久しぶりに帰国しており、こっそりとユジンを見に来たのだった。情報源はキム常務理事の今は彼女であるポラリスのジョンアさんで、今日ユジンがチンスクの家に遊びに来ると聞いたのだった。チュンサンが今の自分の姿をユジンに見られたくないけれど、それでも一目会いたいというので、こうして物陰からユジンを眺めているのだった。キム理事は複雑な顔で言った。
「なあ、あの二人が結婚して子供までいるなんてな」
「それが僕の望んだことです。サンヒョクが約束通り彼女を幸せにしてくれたから、僕も幸せです。さあ帰りましょう」
そういうと、チュンサンは寂しそうに背をむけた。チュンサンとキム理事は静かに立ち去るのであった。

「ユジン、久しぶりの韓国は慣れたか?」とヨングク。
「うん、ありがとね」
「ほんと、全然連絡くれないんだから」とチンスク。
「ごめん、すごく楽しかったのよ」ユジンはうそぶいた。

その時、部屋の窓からチェリンの叫ぶ声が聞こえてきた。
「ちょっと、チヒョンのママ!人を呼んでおいて遅いじゃないの。もう30分も待ってるのよ!」
チェリンは相変わらずわがままで気がつよい。以前のように派手なパーマの髪型はやめて、茶色がかったゆるいパーマが顔を縁取っていた。そして、前にもまして洗練されたジャケットとブラウスを着ており、さながらキャリアウーマンというところか。今では韓国期待の新進デザイナーになっていた。

「ごめんごめん、今行くね」
チンスクも今や一児の母でチェリンの店のマネージャーでもある。チェリンの言うことなどものともせず、我ながら強くなったものだと思うのだった。
「ごめんな、チェリン」


5人がおしゃべりしながらアパートの中に入っていくと、一番後ろを歩いていたユジンが視線を感じて、きょろきょろとあたりを見回した。なぜかとても懐かしくて切ない感情が胸を通り抜けた。しかし、誰もいないのを確認すると、サンヒョクにそっと促されて建物に入って行くのだった。


5人は部屋に入ると、ヨングクとチンスクが買ってきた総菜やお酒を並べてユジンの帰国祝いと称した同窓会を始めた。3年もまともに会っていなかったのに、まるで昨日別れたばかりのように話題が尽きず、笑い声が絶えなかった。チェリンはチンスクと続けているブティックの話や、最近別れたイギリス人の彼氏の愚痴をぶちまけていたし、サンヒョクはラジオ局の人事で幹部に昇格したこと、チヨンが何件もお見合いを持ってくるのに気が乗らずいつも断られてしまうと面白おかしく話していた。



ヨングクが経営している動物病院の話をすると、チンスクが横やりを入れてまた笑わせた。最後にヨングクは、得意の占いでチェリンとサンヒョクの相性を読むと「まあまあだな」と言って、それを聞いた二人はお互いに嫌そうな顔をしてまた笑いを誘った。そんな中でも、ユジンは笑っているばかりで、フランス留学中の話は全くしなかった。たまに誰かが水を向けても「楽しかった」「フランス語が大変だった」と言うばかりで、詳しく説明しなかったので、誰もがユジンの留学のことは触れないようにしようと感じていた。また、チュンサンのことも皆の頭の中には浮かんでいたが、ユジンが話したくなるまでは口に出すまいと名前を出すのもやめていた。こうして、楽しい同窓会はお開きとなった。
















