2017年度の所報を1つ、2018年度の所報を1つ、2019年度の所報を3つ。
以上5所報の冒頭部とタイトルまわりを並べる。
倍率は一様でない。
まず各所報の冒頭部。
▼No.307冒頭部▼

▼No.326冒頭部▼
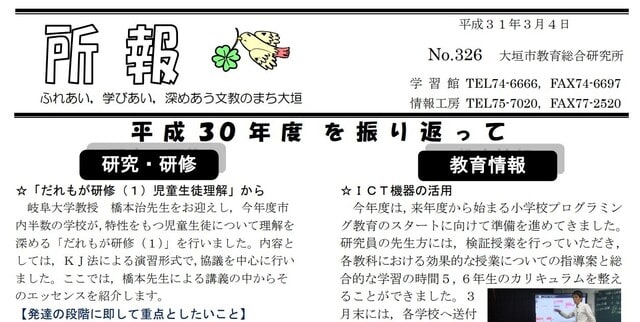
▼No.327冒頭部▼

▼No.328冒頭部▼

▼No.329冒頭部▼

次は各所報のタイトルまわり。
▼No.307タイトルまわり▼

▼No.326タイトルまわり▼

▼No.327タイトルまわり▼

▼No.328タイトルまわり▼

▼No.329タイトルまわり▼

強烈なメッセージ「しばられるな」を擁したNo.327の画期的な画期的さがよく分かる。
翌号からタイトルまわりのデザインがチャーミングになった。
IER所報史上、No.327の威力は突出していると断言して間違いあるまい。
なお、5所報のオリジナルは運次第で見られるだろう。
No.307
No.326
No.327
No.328
No.329










IER所報について、興味深くまとめて下さり、ありがとうございます。
所報No.329の「IER」の説明(英語表示)は、勇気ある変化を求めた見出しと、従来の考え方にこだわるフッター、この違い=共存は面白かったです。
この表示のズレを平気で取扱うIER勇気を参考に、大垣市教育界が「OPEN」かどうかを考えてみました。https://blog.goo.ne.jp/wozequi/e/e90d5e30f4339a27dd0ecb16abbaf379
ところで、所報No.327を参考にすると、身勝手な主張さんがIER(背景はOKI?)に問い合わされた内容の回答が、こうした所報ではなく、氏名を伏せて簡単にまとめたペーパーにされたなど、IERのサービスの悪さが印象的です。こちらが身勝手な主張さんのブログです。https://blog.goo.ne.jp/mh0920-yh/e/a8d817dc58c50b72501dc682663a69d3/?cid=f1076eb1ead97212274ef5456a792b28&st=0
勇気を出すのは、IERの説明見直しでなく、サービスの見直しであってほしいです。
> 所報No.329の「IER」の説明(英語表示)は、
> 勇気ある変化を求めた見出しと、
> 従来の考え方にこだわるフッター、
> この違い=共存は面白かったです。
先代所長の意志は明確です。
「教育総合研究所」の前に、
見出しは「大垣市」が付くので和製英語
フッターは「大垣市」が付かないので一般的英語
きちんとした理屈があります。
IER:先代所長の意思について、ご解説ありがとうございました。ヘッダーとフッターで、日本語/英語どちらも違いあり=バラバラ ← 市民・保護者などを混乱させるように思いました。ただ、細かな部分を気にする人はいないようにも思いますが。本音で言えば、気づかいはこの程度の組織なのか、と…
気になるのは電話番号。良く見ると、**-6666。
6が4つ = ムがシ = 無視 という具合に思えてしまいます。
大垣市教育界の情報は「無視」や「CLOSE」でなく、「OPEN」であってほしいです。
先日はこちらでIERの所報について、情報ありがとうございました。
前はリンク先の所報を運良く見れていましたが、今はOPENすべきIERがCLOSEとなってしまったようです。大垣市民として、残念です。
大垣市民として、次の情報を見つけました。
ブログ「身勝手な主張」さんのコメントに投稿した内容とほぼ同じですが(少し加筆修正しました)、IER情報公開の姿勢を考える参考になれば幸いです。
***
大垣市教育界の情報閉鎖性は、教育執行機関として、いかがなものか、と思います。
私は素人のため、良く分かりませんが、少し、順序立てて見てみますと…
まず、大垣市教育委員会文書取扱規程です。
https://www2.city.ogaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i303RG00001038.html
この規程を見ますと、準用規定としてこの規程に定めるものの他は大垣市の例による、とされています。
次に、大垣市文書取扱規程です。
https://www2.city.ogaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i303RG00001026.html
こちらの第26条に保存期間が規定されています。
6種類の区分が定められています。
下の方に別表第3があり、保存期間が詳しく記載されています。
第5種(1年保存)を見ますと…
1 軽易な照会、回答、願、届、伺書等の書類
となっています。
教育総合研究所の報告書は、軽易な内容なのでしょうか?
次に、1つ上、第4種(3年保存)を見ますと…
1 消耗品及び材料に関する書類
2 調査、統計、報告、証明、復命等に関する書類
3 予算、決算及び出納に関する重要でない書類
4 給与に関する書類
5 その他3年間保存の必要があると認める書類
となっています。
私見になりますが、私は研究所の文書は、第4種(3年保存) 2 調査、統計、報告、証明、復命等に関する書類が有るように(該当するように)思います。
原本の文書(記録)があれば、まだ良いでしょうが、仮に原本も処分したとなると、規程の考え方を軽んじている(または、規程に違反している)となるように思います。
文書の保存期間の適切さを考える中でのご参考になれば、幸いです。
文書を廃棄する場合は、
いつ・誰が・どの文書を・なぜ破棄したか
等を記録した文書が必要でしょう。
その記録文書だけは永久保存しないと後世に対して無責任です。
なお、IER所報No.327はサバイバルゲームを楽しんでいるようです。
やはりNo.327の威力は突出しています。