在庫切れでなかなか入手できなかった
「銀座のツバメ」金子凱彦(著)、 佐藤信敏(写真) 学芸みらい社
をやっとゲット。
銀座のツバメ30年間の記録をまとめた本だが
ツバメのみならず大都市に生息する都市鳥の
30年のデータや分析もあり興味深い。
ツバメの生態は謎が多い。
幸運にもツバメの大家3年めを迎えた今も
わからないことがいっぱいだ。
この本のおかげで、3年前の疑問が解決した。
2011年7月、荒川でのツバメのねぐら探しのとき
見かけたツバメたちの運動会さながらのスタートダッシュは、
ツバメたちの協同採餌シーンだったのだ。
→http://20110513.at.webry.info/201107/article_12.html
ツバメのことを端的に表現している文章があったので、
本文から引用させてもらおう。
ツバメは昔から人のそばで子育てをし、もちつもたれつで
繁殖してきた特異な鳥なのだ。農業離れや農薬の普及で
益鳥としての役割が薄まってきている昨今、ツバメたちの
運命は苛酷だ。
p120~121から以下、青字引用。
◆ツバメをまもるのは地方出身者?
「子どもの頃ツバメに親しんだ地方出身者によって、
本書のこの部分だけは、ちょっと違うと言いたい。
我が家の近隣のケースでは、若い人や子どものほうが
ツバメにやさしい。
春、ツバメの飛来を待ちわびて、「まだツバメさん来ない?」
と聞いてくる小学生がいたり、ヒナの成長を楽しみにしてくれてる
若い母がいたり・・去年聞いた話だが小学校でツバメの授業があるそうだ。
それに比べ、ツバメが益鳥であったことを身を以て知っているだろう
世代の人たちのなかにツバメにひどく冷たい人もいて
今年はとうとう信じられないようなことを言われ、
悩まされた。
ツバメは人の庇護がないと生きていけない。
人を信じ、家先に巣を作り子育てをする。
そうしたツバメと人の今までの歴史や生態、
そして今まさに消えようとしているツバメの現状を
多くの人に知ってもらいたい。
この本はツバメのほかに、カラス、キジバト、カルガモといった
よく見かける都市鳥のことも書かれており、
ちょっとした野鳥豆知識が得られる。
巻頭の躍動感あふれるツバメの写真も必見!
サクッと読め、ツバメのみならず、都市部で
これからバードウォッチングをはじめようという人に
おススメ本です♪
 |
銀座のツバメ |
| クリエーター情報なし | |
| 学芸みらい社 |


















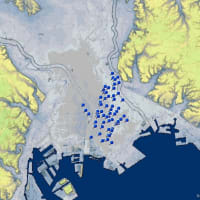

「銀座のツバメ」のご紹介ありがとうございます。
「田んぼの生き物」や「つばめのくるまち」の佐藤さんが共著なのですね。
さっそく購入しました。
それにしてもすばらしい書評ですね。
ゼヒ amazon にもレビューしてください!!