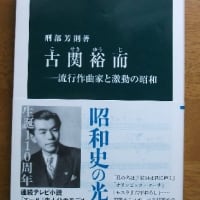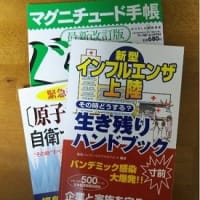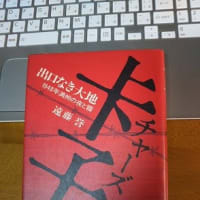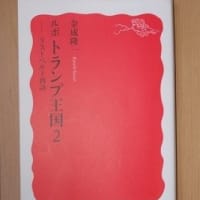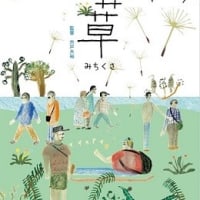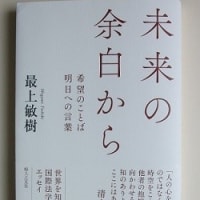天皇、皇室の務めについて、これまで目に映ってきたのは、日曜朝のTV番組で、見かける程度だった。「おことば」にある象徴天皇としての柱としての務めは、第一に宮中祭祀であり、第二は全国を回られた行幸。それらの背景を、詳細、具体的に説明されているが、今まで、不明で明らかになった事柄が多数あった。宮中祭祀について。新嘗祭が、勤労感謝の日というように戦前の天皇の祭祀の日がカレンダーの祝日になった。TVに映る田植え、養蚕。これらが祭祀に使われるという程度の理解だった。しかし、P34の表にあるように、年間、これほど多数の祭祀があること。また、四方拝、新嘗祭以外は、明治以降の作られた伝統であることに改めて気づかされれた。行幸啓について。これも、巻末に、相当の頁をとっているが、皇太子時代も含め、いかに全国を回られたかに目を見張った。自分は、昭和天皇の行幸啓を小学生の時に体験したが、当日は、私たち生徒が、日の丸を手作りし振ったこと。道路わきにお年寄りが、ござに座り、頭を下げていた光景が記憶に残っている。高度経済成長期間の行幸が、地方の道路などのインフラの整備につながったとのことだが、確かに、砂利道が舗装され、法面がきれいにされた覚えがある。一方、都市と地方との格差、人口減少…、少子高齢化、頻発する災害、そうした中での平成の行幸は、国民の目線に合わせる、寄り添う、そうした姿勢があった。しかしながらも、そこでは、「ミクロ化した国体」、昭和初期の超国家主義につながる意味合いを、自然と持ってきたのではないかいう指摘は、うなづけるものがある。行幸については、国体、全国植樹祭等出席した際に、会場となる県内周辺にも行かれる訳だが、そこには宮内庁の緻密な準備があるのだろう。そこには、文中にホームレスの排除に触れていたが、福祉施設訪問にあっても、公立、公立民営、日赤等のあたりさわりのない所が選ばれているのではないだろうか。 自衛隊のと列については、平成の初めから始まったとあるが、自衛隊の駐屯地のHPのいくつかを見てみたら、掲載された写真の光景と同様のものが見られた。「 提灯奉迎」、日の丸旗については、日本会議が動いているようだが、この会議について、青木理の著書も読んでみたが、資金提供は、会議の構成団体である神社本庁、他新宗教からなされているらしい。地方から草の根的な手法は、元号法制化運動から積み上げてきているようだが、本質は、 天皇制を戦前に戻す超国家主義を拠り所にしている。そうした流れの中で、憲法改正もそうだが、靖国神社国家護持についても新たに動き出すのかなという印象を受けた。