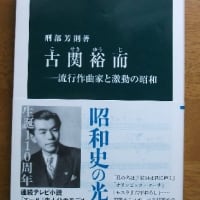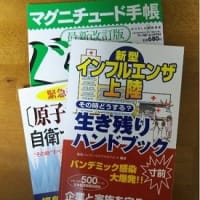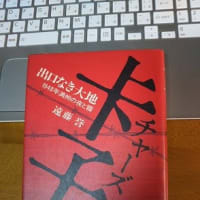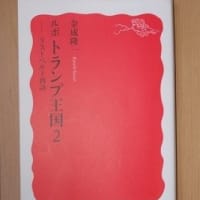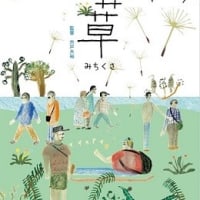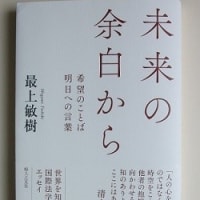書店で、表紙が、ブリューゲルのバベルの塔に引かれて購入した。2012年10月、2日間に渡り行われたシンポジウムの記録。内容を自分なりにまとめてみた。
前半は、物理学者北澤宏一氏による講演「原発と代替エネルギー―科学・技術の視点から(原子力の魅力と問題点)」。
全電源喪失、メルトダウンに至る福島原発事故の概要説明。これは過酷事故であり、当時、イギリス以外は、自国民へ国外避難が伝えられ、首都圏住民も避難という最悪のシナリオが想定された。特に、2号機は、最も放射性物質が漏れた。4号機の建屋内プールに保管中の使用済核燃料は、工事の遅れで隣のプールに水があり、隙間があって流れ込んだというカミカゼのような出来事で辛うじて難を逃れた。
世界の原発と代替エネルギーの移り変わり。ヨーロッパでは再生可能エネルギーを導入し、脱原発の方向へ行く中で、日本は逆行し、2011年時、54基にもなっていた。フィンランドは、天然ガスなどロシアに依存している事情があるが、最初に、放射性廃棄物地下埋蔵に着手した。スペインは、8基を、段階的に廃止。40%再生可能エネルギーにより、また、電力系統が独立しており自給自足を果たしている。
中国は、再生可能エネルギーに熱心で、投資額は、ドイツ、アメリカを抜いて世界第1位である。ドイツは、フランスから電力を輸入しているという風評があるが、余剰電力を夜間買い、日中、仏が不足の際供給しているわけで、実は、輸出しているわけで、こうした風評に惑わされてはいけない。
日本の、洋上風力発電、太陽光パネルなど、再生可能エネルギーのポテンシャルをさらに高めていくことは実現可能。国民の所得を減らしても対外純資産を増やすという方向から、再生可能エネルギーに投資する方向へと転換することが今必要。
後半は、神学者・栗林輝夫氏による講演「キリスト教は原発をどう考えるか―神学の視点から」
キリスト教界では、広島・長崎の惨禍から、核兵器に対しては、悪。しかし、原発は善という倫理が70年代後半まで続く。例えば、核実験反対と決議した絶対平和主義をとるメノナイト教会でさえも同様であった。1961年米国の聖公会から立教大学に実験用原子炉が寄贈され、原子炉奉献祈祷が執り行われたということもあった。しかし、スリーマイル、チェルノブイリ以降、原発は安全ではないと声が、エキュメニカルな教会から声があげられ始め、プルトニウムの軍事転用、中央集権的な秘密主義、技術過信の危うさ、放射性廃棄物の次世代への棚上げなどの問題も明らかにされ始めた。
旧約聖書のバベルの塔は、科学技術の総力をかけた大事業、中央集権的官僚制度、それによる人間管理システムを物語るのではないか。塔の完成が、豊穣をもたらし、外敵の侵入、川の氾濫から民を守る。そのために、使役と労苦に耐えたが、結局は、災いでしかなかった。これは、イスラエルの神の意図のもと、巨大テクノロジーから自由をもとめた民衆の物語であると言える。一大国家事業としての原子力開発(例マンハッタン計画)、原発の維持は国防に不可欠であるという点で、原発はバベルの塔と重なる。
「いのちを選べ」というのが脱原発のキリスト教倫理。原発はいのちを守れないテクノロジーであり、放射能汚染は、今の私たち、さらに未来世代の命、また自然の命も危うくする。様々な代替えエネルギーを視野に入れ、どれが神の創造に適しているのか、どれが「幸いに至る道」なのかキリスト教的に問うていくことが必要。内村鑑三は、「デンマルク国の話」で、国の危機は好機になりうるとし、太陽光、海の波頭、風、火山、これを利用すれば富となると述べている。日本人が経済的人間からエコロジー的人間に転換し得る。より安全な代替エネルギーをめざすことへの転換は、命に満ちた神の国のビジョンに近づくことである。
前半の、福島原発事故の概要については、事故調報告と重複で略したが、次第に記憶が薄れていくのに気が付かされた。中国が、原発増設の一方、再生可能エネルギーへの投資額が一位であるのは意外(現在はどうなのだろう?)。エコロジー的人間への転換は、仏教とも共通なところがある。内村鑑三の先見性にも目を見張った。残念ながら、両先生とも2011年以降他界されてしまったが、再生可能エネルギーや脱原発という議論は、伝えられなくなってきた感じがする。
前半は、物理学者北澤宏一氏による講演「原発と代替エネルギー―科学・技術の視点から(原子力の魅力と問題点)」。
全電源喪失、メルトダウンに至る福島原発事故の概要説明。これは過酷事故であり、当時、イギリス以外は、自国民へ国外避難が伝えられ、首都圏住民も避難という最悪のシナリオが想定された。特に、2号機は、最も放射性物質が漏れた。4号機の建屋内プールに保管中の使用済核燃料は、工事の遅れで隣のプールに水があり、隙間があって流れ込んだというカミカゼのような出来事で辛うじて難を逃れた。
世界の原発と代替エネルギーの移り変わり。ヨーロッパでは再生可能エネルギーを導入し、脱原発の方向へ行く中で、日本は逆行し、2011年時、54基にもなっていた。フィンランドは、天然ガスなどロシアに依存している事情があるが、最初に、放射性廃棄物地下埋蔵に着手した。スペインは、8基を、段階的に廃止。40%再生可能エネルギーにより、また、電力系統が独立しており自給自足を果たしている。
中国は、再生可能エネルギーに熱心で、投資額は、ドイツ、アメリカを抜いて世界第1位である。ドイツは、フランスから電力を輸入しているという風評があるが、余剰電力を夜間買い、日中、仏が不足の際供給しているわけで、実は、輸出しているわけで、こうした風評に惑わされてはいけない。
日本の、洋上風力発電、太陽光パネルなど、再生可能エネルギーのポテンシャルをさらに高めていくことは実現可能。国民の所得を減らしても対外純資産を増やすという方向から、再生可能エネルギーに投資する方向へと転換することが今必要。
後半は、神学者・栗林輝夫氏による講演「キリスト教は原発をどう考えるか―神学の視点から」
キリスト教界では、広島・長崎の惨禍から、核兵器に対しては、悪。しかし、原発は善という倫理が70年代後半まで続く。例えば、核実験反対と決議した絶対平和主義をとるメノナイト教会でさえも同様であった。1961年米国の聖公会から立教大学に実験用原子炉が寄贈され、原子炉奉献祈祷が執り行われたということもあった。しかし、スリーマイル、チェルノブイリ以降、原発は安全ではないと声が、エキュメニカルな教会から声があげられ始め、プルトニウムの軍事転用、中央集権的な秘密主義、技術過信の危うさ、放射性廃棄物の次世代への棚上げなどの問題も明らかにされ始めた。
旧約聖書のバベルの塔は、科学技術の総力をかけた大事業、中央集権的官僚制度、それによる人間管理システムを物語るのではないか。塔の完成が、豊穣をもたらし、外敵の侵入、川の氾濫から民を守る。そのために、使役と労苦に耐えたが、結局は、災いでしかなかった。これは、イスラエルの神の意図のもと、巨大テクノロジーから自由をもとめた民衆の物語であると言える。一大国家事業としての原子力開発(例マンハッタン計画)、原発の維持は国防に不可欠であるという点で、原発はバベルの塔と重なる。
「いのちを選べ」というのが脱原発のキリスト教倫理。原発はいのちを守れないテクノロジーであり、放射能汚染は、今の私たち、さらに未来世代の命、また自然の命も危うくする。様々な代替えエネルギーを視野に入れ、どれが神の創造に適しているのか、どれが「幸いに至る道」なのかキリスト教的に問うていくことが必要。内村鑑三は、「デンマルク国の話」で、国の危機は好機になりうるとし、太陽光、海の波頭、風、火山、これを利用すれば富となると述べている。日本人が経済的人間からエコロジー的人間に転換し得る。より安全な代替エネルギーをめざすことへの転換は、命に満ちた神の国のビジョンに近づくことである。
前半の、福島原発事故の概要については、事故調報告と重複で略したが、次第に記憶が薄れていくのに気が付かされた。中国が、原発増設の一方、再生可能エネルギーへの投資額が一位であるのは意外(現在はどうなのだろう?)。エコロジー的人間への転換は、仏教とも共通なところがある。内村鑑三の先見性にも目を見張った。残念ながら、両先生とも2011年以降他界されてしまったが、再生可能エネルギーや脱原発という議論は、伝えられなくなってきた感じがする。