今日は、道立帯広美術館開館25周年記念の特別展「国立美術館・煌めく名作たち」を観に
行ってきました。

京都の近代日本画壇の作品が40点、日本の近代洋画が27点、京都をめぐる工芸が17点、合計84点で
日本近代美術史の歩みをたどるという大変贅沢な展覧会でした。
京都国立近代美術館所蔵品が大部分で東京国立近代美術館所蔵品が洋画の7点だけでした。
日本画や工芸は余り馴染みがありませんでしたが、洋画では、小磯良平、安井曽太郎、青木繁、
岸田劉生、黒田清輝など見覚え・聞き覚えのある画家の生の作品を直近に心行くまで見られ、
久しぶりに時間の経つのも忘れてしまいました。上の作品は、結核の為28歳の若さで亡くなった青木繁の
「女の顔」(1904年)です。
特に、岸田劉生の以下の作品は、約100年前、作者が住んでいた東京代々木4丁目辺りの写生で「道路と土手と塀」と言う
作品です(1915年)。初めて見たのですが、余りにリアルで遠近感があるのに感動しました。

まるで自分が正にその道路に立って見上げている感覚を覚えました。
人物画より風景画が好きな私にとって、何気ない風景ですが、構図といい、色彩といい、日当たりと影の部分の色調の
使い方などこれぞ風景画の真髄を教えられた気がしました。
今回の展覧会で唯一の「重要文化財」でもありました。
特に、今日は、「プレミアム鑑賞会」と称して、地元十勝在住の画家・美術家を講師として迎え、
各々のお勧めの出品作について見どころや魅力を1時間半にわたって解説してくれたので、
作者の背景や作風の変遷なども分かって、作品がより身近に感ずる事が出来ました。
こうした企画は大変有難いものです。
行ってきました。

京都の近代日本画壇の作品が40点、日本の近代洋画が27点、京都をめぐる工芸が17点、合計84点で
日本近代美術史の歩みをたどるという大変贅沢な展覧会でした。
京都国立近代美術館所蔵品が大部分で東京国立近代美術館所蔵品が洋画の7点だけでした。
日本画や工芸は余り馴染みがありませんでしたが、洋画では、小磯良平、安井曽太郎、青木繁、
岸田劉生、黒田清輝など見覚え・聞き覚えのある画家の生の作品を直近に心行くまで見られ、
久しぶりに時間の経つのも忘れてしまいました。上の作品は、結核の為28歳の若さで亡くなった青木繁の
「女の顔」(1904年)です。
特に、岸田劉生の以下の作品は、約100年前、作者が住んでいた東京代々木4丁目辺りの写生で「道路と土手と塀」と言う
作品です(1915年)。初めて見たのですが、余りにリアルで遠近感があるのに感動しました。

まるで自分が正にその道路に立って見上げている感覚を覚えました。
人物画より風景画が好きな私にとって、何気ない風景ですが、構図といい、色彩といい、日当たりと影の部分の色調の
使い方などこれぞ風景画の真髄を教えられた気がしました。
今回の展覧会で唯一の「重要文化財」でもありました。
特に、今日は、「プレミアム鑑賞会」と称して、地元十勝在住の画家・美術家を講師として迎え、
各々のお勧めの出品作について見どころや魅力を1時間半にわたって解説してくれたので、
作者の背景や作風の変遷なども分かって、作品がより身近に感ずる事が出来ました。
こうした企画は大変有難いものです。











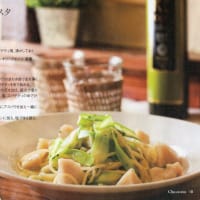
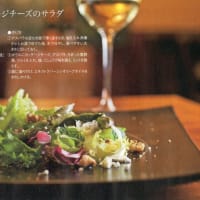

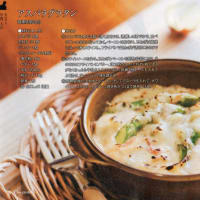

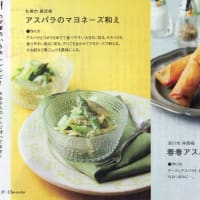
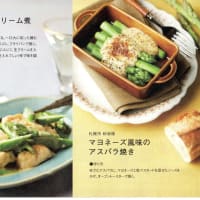


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます