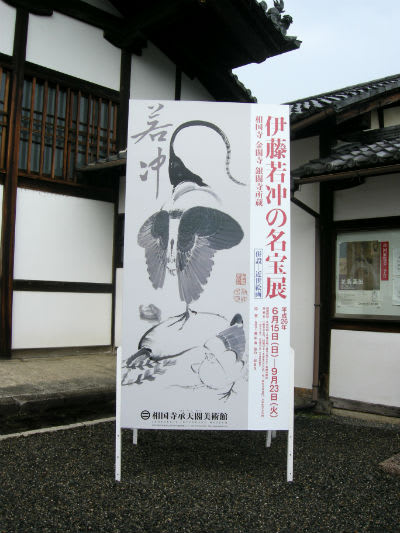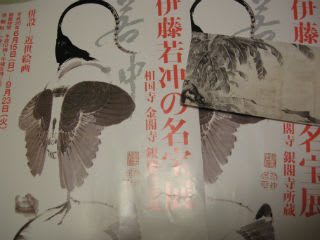美術館レポは久しぶり。行ったとしても最近はここに書かないから。
↓ Tweetしたテキストをほぼそのまま・・・
******
「無言館展」初日の講演会より。
「ここにあるのは無観客画家たちの絵です。誰かに見せるためでも、賞をとるためでも、有名になるためでもなく、ただ描いた。だから胸を打つんです」
無言館館長の窪島さんの言葉に背筋が伸びた。若者たちが遺した作品には家族や愛や夢や生の輝きが描かれている。展示の章ごとに添えられた窪島さんの言葉とともに、一点一点ゆっくり見ることができた。
戦争で亡くなった画学生たちの作品を収集・展示している長野県上田市にある美術館「無言館」の作品が神戸へ。無観客だけど無名ではない。一人一人にちゃんとした名前がある。せっかくの機会だから作品に添えられた作家たちの名前をしっかり見た。展示ケースにあった戦地からの軍事葉書。時間のある限り、生ある限り、描かずにいられなかったのだと思うと、1枚1枚に描き残された絵の緻密さ、美しさに思わず落涙。



>> 神戸新聞の動画「神戸ゆかりの美術館で「無言館」展 戦没画学生の130作品」
●神戸ゆかりの美術館
11月29日(日)まで。月曜休館。※9月23・24日は休館。