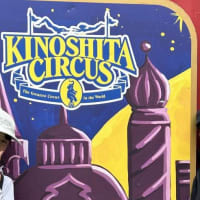本当は「大報恩寺」といいます。
通称「千本釈迦堂」だそうです。

中はけっこう広い境内です。

大きな枝垂桜の木があります。

桜の季節には見ごたえたるでしょうね~?
おふくさんの像が祭られています。

本堂を建てた大工の棟梁である夫の失敗を助けたうえ、女の助言で完成できたといわれては名誉を傷つけると、自ら命を絶った妻のおかめの伝説があります・・・・・行く前ににわか仕立てで覚えたことですが。
そのため京都で棟上げ式を行うときおかめの面を御幣に付ける習慣があるそうです。
おふくさんとはおかめさんともいわれます。
本来古代において、太った福々しい体躯の女性は災厄の魔よけになると信じられ、ある種の「美人」を意味したとされている・・・・らしいです。
だが縁起物での「売れ残り」の意味、あるいは時代とともにかわる美意識の変化とともに、不美人をさす蔑称としても使われるようになったとも言われている・・・・そうです。
まあ、自分がおふくさんみたいな人は、自分の都合のいいように解釈していればいいですよね、私はおふくさんぽくないのでどっちでもいいけど。
次回は12月の大根炊きの時に来たいです。