「生物多様性」と南方熊楠
環境科学A 2012/05/07 中京大学 豊田 新村安雄
○生物多様性はなぜ重要なのか?(前回の復習)
いろいろな視点から考える
・人間存在の根源である。
倫理的な価値
「万物の霊長」「ノアの箱船」
→ 一神教的な倫理観
・人間生活の生態系サービスへの依存
功利的(経済的)な価値
上記の視点は人間主体の視点ともいえる。
・「生物多様性」それ自体が重要
→ 生物多様性には「内在的な価値」がある。
倫理 功利性を越えた「崇高な価値」が生物多様性には備わっている。
人間の存在を必ずしても想定していない。
「八百万の神々」「森羅万象
→ 日本的な自然観との親和性がある。
○「エコロジー(Ecology)」 2つの意味
1、動植物の経済(economy)の科学、生命体とその周辺環境、習慣、生活様式との関係を扱う生物学の一部門。
2、(付加的に、また単独で)政治。社会活動の文脈において、産業汚染・自然破壊のような生態系を破壊する問題に関しての抵抗ないしは対抗する思想として用いられる。特に、環境への、また「グリーンな」関心を示す様々な(特に西欧での)運動について用いられる。自然保護運動
○熊楠による「エコロジー」の説明はどうだったか?
熊楠は「エコロジー」という言葉を日本に最初に紹介したとされている。
熊楠はecology という語に「植物棲態学」という訳語を当てている。
「諸草木相互の関係はなはだ密接錯雑致」するような、人間の活動から影響されていない環境で観察される「この相互の関係を研究する特種専門の学問
→ 熊楠は学問的な意味で捉えている。
○神社合祀に反対する理由としてあげた8箇条
白井光太郎(植物学者 東京大学)に書き送った「神社合祀に関する意見(原稿)」
(明治四十五年二月九日 付、『全集』7―五三○頁以下)での反対理由八箇条(ただしこの書簡で熊楠は、これらを一項目ずつ詳論しており、このように箇条書きにして いるのではない)。
• (一)神社合祀で敬神思想を高めたりとは、政府当局が地方官公吏の書き上げに欺され居るの至りなり。
• (二)神社合祀は民の融和を妨ぐ。
• (三)合祀は地方を衰微せしむ。
• (四)神社合祀は国民の慰安を奪ひ、人情を薄ふし、風俗を害する事おびただし。
• (五)神社合祀は愛国心を損ずる事おびただし。
• (六)神社合祀は土地の治安に大害あり。
• (七)神社合祀は史蹟と古伝を滅却す。
• (八)合祀は天然風景と天然記念物を亡滅す。
→ 「生態系サービス」としての視点から反対している。
(二)-(五)文化的サービス(七)も (六)は調整サービス
○南方熊楠は自然保護活動家だったか?(狭義のエコロジストだったか?)
「第一に植物保存の点のみより願わしきは、(…)差し当たり当紀伊国は、三好教授の『植物講義』にも見るごとく、上は本州ながら、生物帯は熱帯、半熱 帯のもの多き、まことに惜しむべき地なれば(…)、学者の一通りの研究がせめてすむまで(事務行政上、実際何の害なきことなれば)、生物および古物、勝 景、史跡(…)土俗、里風を保存するために、(…)(『全集』7―四九○頁)」
研究対象としての価値のみによっても保全が必要と主張するというこうした彼の姿勢は、ときとして「標本室的保存」ともいうべき学者的独善の気配を示すことすらあった。
「そんなあやふやなことを強行して、このクラガリ谷の勝景、植物を滅却するは、いかにも惜しきことのみならず、せっかく大金かけ岩石開鑿、山林滅徐した後には、その水力果たして乏しく水源は涸れ、数年ならずしてこの電燈会社もつぶるるとせば、実に隋侯の珠を雀に擲ち失うようなことで、つまらぬことと存じ候。 (『全集』7―四八二頁)」
こうした研究者の視点(学術的功利性といってもよい)と並び、あるいはそれに先だって、熊楠の自然資源保護の主張には、産業的功利性の側面があることにも注意したい。それは、地域社会にとっての利得の観点からの議論である。
南方熊楠の「エコロジー」 「熊楠研究」 第五号 田村義也(2003) より
→「生物多様性」を「価値あるもの」として捉える視点 ?
田村はエコロジスト(=自然保活動家)として見た場合南方熊楠には限界があったとしているが、むしろ、標本第一主義(生態系情報の収集)、産業的功利性(生態系サービス)という行動・視点は現在の生物多様性保護の方法論に近いと考えられるのではないか?
神社合祀反対運動では、抽象的な論点を避けて、日本国民に訴える反対項目を述べている。その視点は生態系サービスからみた神社合祀反対というべきものだ。また、日本に紹介した「エコロジー」という言葉も、自然保護という特定の意味づけではなかったと考えられる。これらは自然保護の運動を通じて「実用的?」な戦略だったのではないか?
以下は私見です。
ボクは南方の行動のなかに{「生物多様性」のもつそれ自体の意味}に類する思想が見られてないかと探してみたのだが、現時点では明らかではない。
熊野の森に熊楠が感じた「霊」的なものに、現在の「生物多様性」を示す「存在」があったのではないかと、夢想している。続く。
○南方熊楠 年譜
慶応3年(1867年)4月15日 - 和歌山城下橋丁(現、和歌山市)
1881年(明治14年) - 『和漢三才図会』105巻をうつし終える。(12歳)
1884年(明治17年) - 大学予備門(現・東京大学)に入学。
同窓生には塩原金之助(夏目漱石)、正岡常規(正岡子規)、秋山真之、など
1886年(明治19年) - 中間試験で落第したため予備門を中退、和歌山へ帰郷。
12月22日 - 神戸港より渡米。
アメリカ時代
1887年(明治20年)
8月 - ミシガン州農業大学(現・ミシガン州立大学)入学
1888年(明治21年) - 寄宿舎での飲酒を禁ずる校則を違反して自主退学。
キューバへ植物採集 サーカス団員として中南米旅行。
大英博物館
1892年(明治25年)
9月 - イギリスに渡る。
1893年(明治26年) - 科学雑誌『ネイチャー』に初めて論文「極東の星座」を寄稿。大英博物館に出入りするようになる。考古学、人類学、宗教学などの蔵書を読みふける日々が続く。
1895年(明治28年) - ディキンズと知り合う。大英博物館で東洋図書目録編纂係としての職を得る。
孫文 土宜法竜(ときほうりゅう)との出会い
1897年(明治30年) - ロンドンに亡命中の孫逸仙(孫文)と知り合い、親交を始める
(孫文32歳、熊楠31歳)。
1898年(明治31年) - 大英博物館で暴力事件をおこす。
1900年(明治33年) - 大英博物館から出入り禁止の処分を受ける。
14年ぶりに日本に帰国。
1901年(明治34年) - 孫文が和歌山に来訪し、熊楠と再会して旧交をあたためる。
1902年(明治35年) - 熊野にて植物採集、田辺を永住の地と定める。
真言宗の高僧 土宜法竜(ときほうりゅう)と書簡交わす
1904年(明治37年) - 田辺に家を借りる。
1905年(明治38年) - ディキンズとの共訳『方丈記』完成。
1906年(明治39年) - 田辺の闘鶏神社宮司田村宗造の四女松枝と結婚
(熊楠40歳、松枝28歳)。
1907年(明治40年) - 前年末発布の神社合祀令に対し、神社合祀反対運動をおこす。
7月 - 長男熊弥誕生。
1909年(明治42年)9月 - 新聞『牟婁新報』に神社合祀反対の論陣を張る。
1910年(明治43年) - 紀伊教育会主催の講習会場に酩酊状態で押し入り
翌日「家宅侵入」で逮捕。
柳田國男(1940年ころ)
1911年(明治44年) - 柳田國男との文通がはじまる(1913年までつづく)。
9月 - 柳田『南方二書』を出版。
10月13日 - 長女文枝誕生。
1912年(明治45年/大正元年) - 田辺湾神島(かしま)が保安林に指定される。
1913年(大正2年) - 柳田國男、田辺に来て熊楠と面会する
(熊楠47歳、柳田39歳)。
1917年(大正6年) - 自宅の柿の木で粘菌新属を発見。
1922年(大正11年) - 南方植物研究所設立資金募集のため上京。
1926年(大正15年/昭和元年) - 『南方随筆』刊行。
イタリアのプレサドラ大僧正の菌図譜出版に際し、名誉委員に推される。
1929年(昭和4年) - 紀南行幸の昭和天皇に田辺湾神島沖の戦艦長門艦上で進講。
1935年(昭和10年)12月24日 - 神島が国の天然記念物に指定される。
1941年(昭和16年)12月29日 - 自宅にて死去。満74歳没。
田辺市稲成町の真言宗高山寺に葬られる。
環境科学A 2012/05/07 中京大学 豊田 新村安雄
○生物多様性はなぜ重要なのか?(前回の復習)
いろいろな視点から考える
・人間存在の根源である。
倫理的な価値
「万物の霊長」「ノアの箱船」
→ 一神教的な倫理観
・人間生活の生態系サービスへの依存
功利的(経済的)な価値
上記の視点は人間主体の視点ともいえる。
・「生物多様性」それ自体が重要
→ 生物多様性には「内在的な価値」がある。
倫理 功利性を越えた「崇高な価値」が生物多様性には備わっている。
人間の存在を必ずしても想定していない。
「八百万の神々」「森羅万象
→ 日本的な自然観との親和性がある。
○「エコロジー(Ecology)」 2つの意味
1、動植物の経済(economy)の科学、生命体とその周辺環境、習慣、生活様式との関係を扱う生物学の一部門。
2、(付加的に、また単独で)政治。社会活動の文脈において、産業汚染・自然破壊のような生態系を破壊する問題に関しての抵抗ないしは対抗する思想として用いられる。特に、環境への、また「グリーンな」関心を示す様々な(特に西欧での)運動について用いられる。自然保護運動
○熊楠による「エコロジー」の説明はどうだったか?
熊楠は「エコロジー」という言葉を日本に最初に紹介したとされている。
熊楠はecology という語に「植物棲態学」という訳語を当てている。
「諸草木相互の関係はなはだ密接錯雑致」するような、人間の活動から影響されていない環境で観察される「この相互の関係を研究する特種専門の学問
→ 熊楠は学問的な意味で捉えている。
○神社合祀に反対する理由としてあげた8箇条
白井光太郎(植物学者 東京大学)に書き送った「神社合祀に関する意見(原稿)」
(明治四十五年二月九日 付、『全集』7―五三○頁以下)での反対理由八箇条(ただしこの書簡で熊楠は、これらを一項目ずつ詳論しており、このように箇条書きにして いるのではない)。
• (一)神社合祀で敬神思想を高めたりとは、政府当局が地方官公吏の書き上げに欺され居るの至りなり。
• (二)神社合祀は民の融和を妨ぐ。
• (三)合祀は地方を衰微せしむ。
• (四)神社合祀は国民の慰安を奪ひ、人情を薄ふし、風俗を害する事おびただし。
• (五)神社合祀は愛国心を損ずる事おびただし。
• (六)神社合祀は土地の治安に大害あり。
• (七)神社合祀は史蹟と古伝を滅却す。
• (八)合祀は天然風景と天然記念物を亡滅す。
→ 「生態系サービス」としての視点から反対している。
(二)-(五)文化的サービス(七)も (六)は調整サービス
○南方熊楠は自然保護活動家だったか?(狭義のエコロジストだったか?)
「第一に植物保存の点のみより願わしきは、(…)差し当たり当紀伊国は、三好教授の『植物講義』にも見るごとく、上は本州ながら、生物帯は熱帯、半熱 帯のもの多き、まことに惜しむべき地なれば(…)、学者の一通りの研究がせめてすむまで(事務行政上、実際何の害なきことなれば)、生物および古物、勝 景、史跡(…)土俗、里風を保存するために、(…)(『全集』7―四九○頁)」
研究対象としての価値のみによっても保全が必要と主張するというこうした彼の姿勢は、ときとして「標本室的保存」ともいうべき学者的独善の気配を示すことすらあった。
「そんなあやふやなことを強行して、このクラガリ谷の勝景、植物を滅却するは、いかにも惜しきことのみならず、せっかく大金かけ岩石開鑿、山林滅徐した後には、その水力果たして乏しく水源は涸れ、数年ならずしてこの電燈会社もつぶるるとせば、実に隋侯の珠を雀に擲ち失うようなことで、つまらぬことと存じ候。 (『全集』7―四八二頁)」
こうした研究者の視点(学術的功利性といってもよい)と並び、あるいはそれに先だって、熊楠の自然資源保護の主張には、産業的功利性の側面があることにも注意したい。それは、地域社会にとっての利得の観点からの議論である。
南方熊楠の「エコロジー」 「熊楠研究」 第五号 田村義也(2003) より
→「生物多様性」を「価値あるもの」として捉える視点 ?
田村はエコロジスト(=自然保活動家)として見た場合南方熊楠には限界があったとしているが、むしろ、標本第一主義(生態系情報の収集)、産業的功利性(生態系サービス)という行動・視点は現在の生物多様性保護の方法論に近いと考えられるのではないか?
神社合祀反対運動では、抽象的な論点を避けて、日本国民に訴える反対項目を述べている。その視点は生態系サービスからみた神社合祀反対というべきものだ。また、日本に紹介した「エコロジー」という言葉も、自然保護という特定の意味づけではなかったと考えられる。これらは自然保護の運動を通じて「実用的?」な戦略だったのではないか?
以下は私見です。
ボクは南方の行動のなかに{「生物多様性」のもつそれ自体の意味}に類する思想が見られてないかと探してみたのだが、現時点では明らかではない。
熊野の森に熊楠が感じた「霊」的なものに、現在の「生物多様性」を示す「存在」があったのではないかと、夢想している。続く。
○南方熊楠 年譜
慶応3年(1867年)4月15日 - 和歌山城下橋丁(現、和歌山市)
1881年(明治14年) - 『和漢三才図会』105巻をうつし終える。(12歳)
1884年(明治17年) - 大学予備門(現・東京大学)に入学。
同窓生には塩原金之助(夏目漱石)、正岡常規(正岡子規)、秋山真之、など
1886年(明治19年) - 中間試験で落第したため予備門を中退、和歌山へ帰郷。
12月22日 - 神戸港より渡米。
アメリカ時代
1887年(明治20年)
8月 - ミシガン州農業大学(現・ミシガン州立大学)入学
1888年(明治21年) - 寄宿舎での飲酒を禁ずる校則を違反して自主退学。
キューバへ植物採集 サーカス団員として中南米旅行。
大英博物館
1892年(明治25年)
9月 - イギリスに渡る。
1893年(明治26年) - 科学雑誌『ネイチャー』に初めて論文「極東の星座」を寄稿。大英博物館に出入りするようになる。考古学、人類学、宗教学などの蔵書を読みふける日々が続く。
1895年(明治28年) - ディキンズと知り合う。大英博物館で東洋図書目録編纂係としての職を得る。
孫文 土宜法竜(ときほうりゅう)との出会い
1897年(明治30年) - ロンドンに亡命中の孫逸仙(孫文)と知り合い、親交を始める
(孫文32歳、熊楠31歳)。
1898年(明治31年) - 大英博物館で暴力事件をおこす。
1900年(明治33年) - 大英博物館から出入り禁止の処分を受ける。
14年ぶりに日本に帰国。
1901年(明治34年) - 孫文が和歌山に来訪し、熊楠と再会して旧交をあたためる。
1902年(明治35年) - 熊野にて植物採集、田辺を永住の地と定める。
真言宗の高僧 土宜法竜(ときほうりゅう)と書簡交わす
1904年(明治37年) - 田辺に家を借りる。
1905年(明治38年) - ディキンズとの共訳『方丈記』完成。
1906年(明治39年) - 田辺の闘鶏神社宮司田村宗造の四女松枝と結婚
(熊楠40歳、松枝28歳)。
1907年(明治40年) - 前年末発布の神社合祀令に対し、神社合祀反対運動をおこす。
7月 - 長男熊弥誕生。
1909年(明治42年)9月 - 新聞『牟婁新報』に神社合祀反対の論陣を張る。
1910年(明治43年) - 紀伊教育会主催の講習会場に酩酊状態で押し入り
翌日「家宅侵入」で逮捕。
柳田國男(1940年ころ)
1911年(明治44年) - 柳田國男との文通がはじまる(1913年までつづく)。
9月 - 柳田『南方二書』を出版。
10月13日 - 長女文枝誕生。
1912年(明治45年/大正元年) - 田辺湾神島(かしま)が保安林に指定される。
1913年(大正2年) - 柳田國男、田辺に来て熊楠と面会する
(熊楠47歳、柳田39歳)。
1917年(大正6年) - 自宅の柿の木で粘菌新属を発見。
1922年(大正11年) - 南方植物研究所設立資金募集のため上京。
1926年(大正15年/昭和元年) - 『南方随筆』刊行。
イタリアのプレサドラ大僧正の菌図譜出版に際し、名誉委員に推される。
1929年(昭和4年) - 紀南行幸の昭和天皇に田辺湾神島沖の戦艦長門艦上で進講。
1935年(昭和10年)12月24日 - 神島が国の天然記念物に指定される。
1941年(昭和16年)12月29日 - 自宅にて死去。満74歳没。
田辺市稲成町の真言宗高山寺に葬られる。











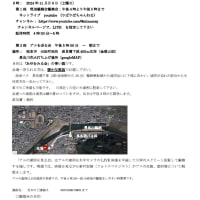














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます